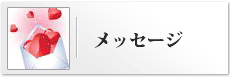「誰にも知られなかった神の働き」 ルカによる福音書2章8~20節
幼稚園の園児たちが演じた「クリスマスページェント」が、保護者と教職員の方々の感激を誘っています。 サンタやツリーやケーキやプレゼントではない「世界で最初のクリスマス」の思いもよらなかった驚きと喜びに満たされているように感じます。 果たして多くのキリスト者が同じように、年中行事ではないクリスマスに新しい驚きと感激と喜びを感じ取っておられるだろうか、人間として生まれてくださった主イエスと新しく出会っておられるだろうかと思わされます。 ルカは主イエスの誕生の出来事が、ローマ帝国最初の皇帝アウグストゥスの時代、その皇帝からの住民登録の勅令が発せられた時、ヨセフとマリアという二人の住民登録のための移動の途中、ベツレヘムというダビデの町の家畜小屋において起こされたと詳しく記します。 この出来事を最初に知らされたのは、先祖代々受け継がれてきた「メシア」の誕生を待ち焦がれていたイスラエルの多くの人々ではなく、「野宿しながら夜通し羊の番をしていた羊飼いたちであった」と言うのです。 イザヤは神に信頼しようとしないアハズ王に絶望し、「王によってもたらされる平和」ではなく、「神によってもたらされる平和」を祈り求めるのです。 それが11章の預言です。 「彼は主を畏れ敬う霊に満たされる。 目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。 弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。 その日がくれば、エッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。 そのとどまるところは栄光に輝く。」とメシア預言をするのです。 ルカはこの700年前のイザヤのメシア預言の中に、イエス・キリストの誕生を見るのです。 イエスはこのイザヤの巻物を開かれ、「主の霊がわたしの上におられる。 貧しい人に福音を告げ知らせるために、主がわたしに油を注がれたからである。 主がわたしを遣わされたのは、捕らわれている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。 この聖書の言葉は、今日、あなたがたが耳にしたとき、実現した。」(4:18-21)と語られたのでした。 主イエスの誕生は、深い暗闇の中に、諦めが漂うだれも声をかけられない沈黙の中に、夜通し羊の番をしていた羊飼いたちに最初に告げられたのです。 ありふれた羊飼いたちの日常生活の中で、今まで何も見えていなかった夜の暗闇を主の栄光の輝きが照らし出した。 誰からも呼びかけられなかった沈黙を破って神の呼びかけが真っ先に響いた。 恐れた羊飼いたちに、「恐れるな。 わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。 今日ダビデの町で、あなたがたの救い主がお生まれになった。 この方こそメシである。」と、700年前にイザヤによって語られた神の約束が今や果たされたと告げ、これが「最初のクリスマス」の夜の光景であったとルカは語るのです。 「あなたがたは、布にくるまって飼い葉桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるだろう。 これがあなたがたへのしるしである。」と言われ、羊飼いたちは神への賛美を聞いて動き出した。 「さあ、ベツレヘムへ行こう。 そのしるしを見ようではないか。」 羊飼いたちは、「すべて天の使いの話したとおりだった。」ことを見聞きし、今度はそれを人々に知らせるまでになった。 ごく限られた人たちに託された神の隠された働きであったとルカは語るのです。 人の前ではなく、神の前に生きるように変えられる。 神はひとりひとりの名を呼んで、主イエスに出合わせ、それぞれに託された務めを終えて、私のもとへ帰ってくるようにと招いておられるのです。 クリスマスとは、「飼い葉桶」に寝かされた主イエスを自分自身が迎え入れる日、自分自身の救いを事実として受け取り、味わって、その確信を「さあ出かけよう、さあ戻ろう」と証し始める喜びの日であるのかもしれません。
[fblikesend]「新しくされるもの」 ルカによる福音書1章5~20節
ルカによる福音書だけが主イエスの誕生の直前に、バプテスマのヨハネの誕生の次第を記しています。 バプテスマのヨハネは、「最期の預言者」とも言われています。 それと同時に、「最初の主イエスの証人」とも言われています。 ヨハネ自身は「悔い改めに導くために、あなたたちに水でバプテスマを授けているが、わたしの後から来る方は、わたしよりも優れておられる。 その方は、聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。」 「自分はメシアではない。 自分はあの方の前に遣わされた者だ。 あの方は栄え、わたしは衰えねばならない。」と告白するのです。 ヨハネの父親はザカリアと言い、多くの祭司のうちの一人です。 母親はエリサベトと言い、子供が与えられず、すでに子をもてる年齢を越していた。 二人は熱心に「子を与えてくださるように」と神に祈っていたと言います。 ある日、ザカリアが祭司の務めを行っている際に、「主の天使が現れ、それを見て不安になり、恐怖の念に襲われた」と言います。 神と出会うことを願っていなかったのでしょうか。 神の使いは恐れるザカリアに、「恐れることはない。 あなたの願いは聞き入れられた。 あなたの妻エリサベトは男の子を産む。」と告げられたのです。 今になって自分の子どもが与えられると告げられてもにわかに信じることのできなかったザカリアは、「何によって、それを知ることができるでしょうか。 わたしは老人ですし、妻も年をとっています。」と神に迫ります。 長い間祈って待っていたのに、子供を与えてくださらなかった神に、その「しるし」を見せてくださいと迫るのです。 神が約束されたことは、私たちの信念や努力によって果たされるものではないでしょう。 神の恵み、深いみ心から生まれ出てくるものでしょう。 神が何も働いていないように思わされる時が、人生の節々では必ずあります。 苦しみや悲しみの只中で、神が共におられることを忘れてしまう時があります。 右往左往し漂う私たちとて、後で神が変わらず働いてくださったことに気づかされる時があります。 共にいてくださったことを思い起こす時がくるのです。 そのような神に事実として出会い、受け入れ、信じる時が必ずくるのです。 私たちは神を信じることができたから、救われたのでしょうか。 信じることのできなかったザカリアに、神はザカリアの口を閉ざすという「しるし」を与えられたのです。 ザカリアが神の約束を信じなかった罰として、この「しるし」が与えられたとは思えない。 むしろ、神の約束を信じる者へと導くための「しるし」でしょう。 神の使いは、「この事の起こるまで話すことができなくなる。 時がくれば実現するわたしの言葉を信じなかったからである。」と告げ、その時が来ればあなたは新しくつくり変えられると言われたのではないでしょうか。 神が告げたとおり、妻エリサベトは月が満ちて男の子を産み、人々は喜び合い、口のきけないザカリアは字を書く板に、「この子の名はヨハネ」と神の使いに言われたとおり書いたと言う。 約束のみ言葉が事実としてザカリアの心に刻まれた瞬間ではなかったでしょうか。 新しくつくり変えられたザカリアの口は開かれ、神への賛美とわが子の務めを預言するまでになったのです。 この直後にマリアにも主イエスの誕生が告げられ、新しく整えられたエリサベトが、挨拶に来たマリアを自らの体験から力強く励ますのです。 私たちの神は一人一人の名を呼んで出会って、それぞれにふさわしく祝福に招いてくださるお方です。 私たちにとって不都合な受け入れ難い出来事と思わされても、神の周到な準備と隠されたみ心と働きが込められているのです。 しっかりと神の約束を受け取って、支えられて、神のみ子イエスを仰いでご一緒に歩んで参りましょう。 神がみ心を込めて贈り届けてくださっているものを、私たちが受け取り損ねている神の側の忍耐があることを忘れてはならないのです。
[fblikesend]「クリスマスの喜びとは」 ガラテヤの信徒への手紙4章1~7節
旧約聖書では、「あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない」と言われる。 偉大な指導者モーセが神から召命を受けた際には、「モーセよ、ここに近づいてはならない。 あなたの立っている場所は聖なる土地だから。」とまで言われ、モーセは恐れて顔を覆ったと言う。 ほど遠い存在であるかのように思わされる神が、今やイエス・キリストによって語りかけてくださっている神、だれ一人例外なく出会い味わうことのできる「近しい神」であるように思わされます。 創世記の最後には、イスラエルの人々がエジプトに移り住んだ経緯が記されています。 アブラハムに神が約束したとおり、イスラエルの人々は力を持ち始めエジプト中に溢れるまでになったのでした。 その脅威を感じたエジプト王は、イスラエルの民に強制労働を課し、奴隷として苦しめたのです。 ついには、イスラエルの民の出産に対し、男の子を殺すという命令を降すまでになったのです。 そのような時に生まれたのがモーセでした。 モーセの両親はその誕生を三か月間隠していたと言います。 隠しきれなくなった母親は、パピルスの籠に防水の処置をしてその中に赤ちゃんを入れ、ナイル川の葦の茂みの間に置いた。 自分の力ではどうすることもできないこの赤ちゃんの行く末を主に委ね、自分の娘に遠くから様子を見させていた。 その赤ちゃんを拾い上げたのが、そこで水遊びをしていたエジプトの王女であったと言います。 その赤ちゃんがイスラエルの赤ちゃんだと分かった王女は不憫に思い、王女の子どもとして育てるようになった。 その様子を一部始終見ていた姉が「イスラエル人の乳母を呼んで参りましょう」と言い、実の母親を連れてくるのです。 モーセはその幼少期、エジプトの王女から委託を受けて、実のイスラエル人の母親の手によって育てられるという数奇な道を歩むことになるのです。 エジプト王は、ナイル川を赤ちゃんを投げ込む殺戮の場としたが、神はその川から赤ちゃんを救い上げ、命を救い、エジプト王の宮廷の中で教育を受けさせ、指導者としてふさわしい器として育てるのです。 切羽詰まった母親の選択の中にも神は共におられ、見えていないところでご自身の救いの約束のために働いておられるのです。 この「ほど遠い神」がたった一人の人物を選び出し、イスラエルの民の奴隷状態から解放の恵みを与えようとして用いられるのです。 パウロは新約聖書の時代に生きるキリスト者として、神のみ子でありながら人として遣わされた主イエスを通して、「ほど遠い神」から「近しい神」への大転換の喜び、クリスマスの喜びを語るのです。 私たち人間が神の恵みにふさわしくなったからではなく、神ご自身の恵みと憐みによる真の救いの出発点が、主イエスの出現、クリスマスの突然の出来事であったとパウロは語るのです。 福音の恵みとして、神の国の世界から神がみ子を遣わした。 同時に、人の世の世界の「女性から」、またこの世の人々が縛られていた「律法の下に」、そして神の国の世界とは相容れないこの世の諸霊の支配の真っ只中に、この世の人間と同じ子として神のみ子が生まれ出たと言うのです。 「律法の支配下にある者を贖い出すため、わたしたちを神の子となさるため」に現れ出てくださった。 これが神の救いの出来事の始まりであったと言うのです。 この喜びは主イエスがなされていたように「父よ」と呼びかけることができる喜びだとパウロは言います。 律法の下にあった厳しい神であるからこそ、「ほど遠い神」から味わい触れることのできる「近しい神」へと大転換された喜び、恵みとしか言いようがない喜びにパウロは満たされているのです。 「あなたはもはや奴隷ではなく、神の子です。 神の子であるなら、この世の諸霊に支配されている只中において、神によって立てられた相続人である。」と言うのです。 神の子となった喜びは、この世の諸霊に覆われている所にこそ指し示すことができるのではないでしょうか。
[fblikesend]「ダビデのひこばえ、輝く明けの明星」 エレミヤ書23章1~6節
新約聖書では、旅の途中で宿るところもなく、神の子イエスが家畜小屋で生まれた。 その時、神の使いが近寄って来て主の栄光をもって周りを照らし、「恐れるな。 わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。 今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。 この方こそ主メシアである。 あなたがたは布にくるまって飼い葉桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。 これがあなたがたへのしるしである。」と告げられたのでした。 メシアが父なる神から届けられた。 それが大きな喜びに変えられる。 それも民全体に対して、分け隔てなく一人ももれなくです。 神に真っ向から敵対し神ならぬものによりすがっていた民に向けて、それでも神が民を救うために神の裁きのもとに降るメシアが与えられるという預言が、目に見える形となって届けられたと告げるのです。 BC七百年代に預言者として神より召命を受けたイザヤは、神の厳しい裁きが下されると示すと同時に、神に信頼する「残された者」がいると希望をも語るのです。 その確信が、「エッサイの株からひとつの芽が萌えいで、その根からひとつの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。 彼は主を畏れる霊に満たされる。 その日がくれば、エッサイの根は、すべての民の旗印として立てられる。」と言うのです。 約七百年の時を経て、イエス・キリストの誕生という「しるし」に、神のご愛と神の裁きが結実したのです。 一方、エレミヤはイザヤから送れること約百年後の時代に生きた神に選ばれた預言者です。 あまりにも現実をありのまま見つめようとするエレミヤは、希望を語ろうとしない悲観論者に見えてしまう。 しかし、エレミヤは物事の両面を見ていて、神の厳しい裁きと共にその背後にある大きな神のみ心に目を向けるのです。 もし、イスラエルの民が神に固くつながっているのであれば、たとえ国が滅んでも、イスラエルの民は滅ぶことはない。 イスラエルの民が敵国バビロンに捕囚として移動させられたとしても、彼らを通して神が蒔かれた種は、その自らの命でもってその芽を出し実を結ぶ。 異教の地であってもその実を刈り取って新たな群れを起こしていくはずである。 エレミヤこそ、国の滅亡をむやみに悲観することなく、事実を事実として希望的に見て、現実を遥かに超えたところにある神の力と知恵を確信していたのではないかと思わされるのです。 「群れの残った羊を、追いやったあらゆる国々から集め、もとの牧場に帰らせる。 彼らを牧する牧者を立てる。 群れはもはや恐れることも、脅えることもなく、また迷い出ることもない。 ダビデのために正しい若枝を起こす。 その名は『主は我らの救い』と呼ばれる若枝を起こす。」と言うのです。 このエレミヤの信仰こそ、現実の苦しみや悲しみに真正面から向かい、事実を事実として味わうことから滲み出てくる希望なのではないでしょうか。 イザヤもエレミヤもクリスマスの出来事を予告した預言者でした。 主イエスが訪れてくださった新約聖書の時代を恵みにより与えられた私たちは、苦悩の中に主イエスの誕生を見つめ続けてきた旧約聖書の時代の預言者たちの苦しみと悲しみ、あまりにも厳しい神の裁きのうえに立った、恵みとしか言いようがない救いの業であることを忘れてはならないのです。 すでによみがえられてすべての人に対して招き続けておられるイエスの「わたしはダビデのひこばえ、その一族、輝く明けの明星である。」というみ言葉が響きます。 神の裁きのもとに自ら進んで降って死んでくださったイエスです。 新しく霊なる命に生きる存在となられて、今もなお私たちに働きかけてくださるイエスです。 暗い夜を過ぎ去らせ、新しい朝を備えてくださるイエスです。 「恐れることも、脅えることもなく、また迷い出ることもない。」と言われる主イエスに、今年のクリスマスもまた出会い、触れて味わうことができますよう心より願います。
[fblikesend]「まだ見ぬ恵みの種」 マルコによる福音書4章26~32節
ユダヤのなじみ深い何気ない日常生活に関わる二つの「種のたとえ」です。 イエスは、「人々の聞く力に応じて、多くのたとえで御言葉を語られた。」とあります。 人々のあらゆる病いを癒すという奇跡をもって、あるいは当時の人々にとっては衝撃的な教えをもって神の福音の恵みを宣べ伝えておられたイエスは、その締めくくりの言葉として「たとえ」を語られていたのかもしれません。 しかしイエスは、「たとえを用いずに語ることはなかったが、御自分の弟子たちにはひそかにすべてを説明された。」とも言います。 見えにくい神の恵みの支配を示すために、見えていない神の国を見えるようにするために「たとえ」をもってなぞらえるのでした。 捉える力も、見抜く力も乏しく貧しい者であっても、イエスを通して語られるみ言葉を受け入れるなら、イエスを信頼する心が与えられるのなら、見えないものが見えるようになる。 聞こえていなかったものが聞こえるようになる。 イエスの弟子となって、イエスを主と迎え入れるなら、はっきりと見えていない神の国、この奥義の秘密が明かされると言うのです。 「成長する種」のたとえには、「神の国は次のようなものである」と言い、「からし種」のたとえでは、「神の国を何にたとえようか」と言い、目に見えない神の恵みと憐みが支配している世界を譬えようとしています。 この直前にイエスが語られた「種を蒔く人」のたとえでは、「あなたがたには神の国の秘密が打ち明けられている。 種を蒔く人は、神の言葉を蒔くのである。 この御言葉を聞いて受け入れる人たちは多くの実を結ぶ。」と言います。 もうすでに「種」である神のみ言葉はあらゆるところに蒔かれている。 蒔かれた場所には、「種」の成長を阻む力、「種」を奪う力が働いている。 せっかく蒔かれた「種」を手離し、見失うという弱さも働く。 それでも「種」を蒔く人は、収穫される実がなると信じて蒔いている。 手入れをし、成長することを祈り、待ち続けている。 最初は小さな存在が、大きく養われて、形を変えて想像もつかないほどの実となっていく。 なぜなら、神が「種」に命を注ぎ、育て、実を結ぶことを約束されているからだと言うのです。 イエスこそ、私たちの中に蒔かれた福音の「種」です。 「わたしにつまずかない人は幸いである。」と言われている。 イエスの語られるみ言葉を自分に語られる言葉として受け入れるなら、神の恵みが支配されている世界をはっきりと見ることができるようになる。 目の当たりに味わうことができ、「天地は滅びるが、わたしの言葉は滅びない。」というみ言葉に立つことができるようになると言うのです。 「成長する種」のたとえでも、人が土に種を蒔いて、夜昼、寝起きしているうちに、種は芽を出して成長する。 しかし、種を蒔く人は、それがどうしてそうなるのか知らない。 「まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。」というプロセスを経ている。 「成長させてくださったのは神」なのです。 「種」という神の言葉には命が隠されていて、神のみ心に従って事は進み実がなっていくのです。 最初は「からし種」のように小さな存在も、成長すると大きな存在に変えられる。 イエスは、「人々の聞く力に応じて」、「種」の成長の謎と、成長の大きさを説き明かし、最もふさわしい「時、ところ」で神が約束を果たしてくださると語るのです。 すでに種は蒔かれている。 その種がなぜ成長するのかその理由は分からない。 しかし、やがて豊かな実がなるという神の約束が種には込められている。 私の弟子であるなら、その「種」を持ち運ぶことも蒔くこともできる。 神の働きに委ねて、いずれ育った実を収穫し、感謝して受け取ることもできる。 命をも左右することのできる神の働きの一端を味わい知ることができるようになる。 「隠されたもので、顕れ出ないものはない。 目に留まらないような小さな現実の中にこそ蒔かれた種がある。」と言われるのです。
[fblikesend]「力強く苦難に向かうイエス」 ヨハネによる福音書18章1~9節
「イエスは弟子たちと一緒に、キドロンの谷の向こうへ出て行かれた。 そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。」とあります。 他の福音書は、このオリーブ山のふもとにある園をゲッセマネと呼び、「苦闘の祈り」をイエスがささげられたと言います。 「わたしは死ぬばかりに悲しい。 父よ、できることなら、この杯をわたしから過ぎ去らせてください。 しかし、わたしの願いではなく、御心のままに。」と祈られたと記されています。 しかし、ヨハネによる福音書は、この「ゲッセマネの祈り」は語られておらず、むしろ、「父がお与えになった杯は、飲むべきではないか。」と、苦悩の祈りの葛藤は克服されたものとして、自ら引き受ける決意の強さを感じさせるのです。 「イエスは弟子たちと共に度々、この園に集まっておられた。 イエスを裏切ろうとしていたユダも、その場所を知っていた。」と言います。 この直前の最後の晩餐で、イエスは「あなたがたのうちの一人がわたしを裏切ろうとしている。 わたしがパン切れを浸して与えるのがその人だ。」と言われ、ユダにそのパン切れをお与えになり、「しようとしていることを、今すぐ、しなさい。」と言われ、ユダはそのパン切れを受け取ると、すぐ出て行った。 夜であった。」と言います。 このような顛末があるなら、危険からご自身の身を守るためには、いくらでも逃げ延びることができたでしょう。 どう考えても、イエスは逃げるためではなく、捕らえられるためにユダもよく知っている場所に出向かれたとしか言いようがありません。 逮捕され、裁判にかけられ、十字架に処刑され、命を奪われることを承知のうえで、人としての苦難を敢えて自ら選び取られたイエスのお姿。 先が見えておられ、最も危険な行動を自ら取り、捕らえられるところに自ら進んで身を置かれた無防備なイエスのお姿に映るのです。 そこに、手に松明やともし火や武器を持っていた兵士たちが、ユダに導かれてやってきます。 「暗闇」の中に出て行ったユダが、再び、「暗闇」のような大勢の存在を引き連れてイエスのもとにやってきた。 イエス自らが「暗闇」の真っ只中に身を置くことによって、私たち人間の「暗闇」が引きずり出されるのでしょう。 「イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられた。」と言います。 もうすでに、父なる神のご意志とご計画の中にあること、動かし難いものとしてイエスの心に受け止められていたのでしょう。 「だれを探しているのか」と兵士たちの前に進み出て、兵士たちが「ナザレのイエスだ。」と答えると「わたしである。」と答えたと言います。 かつてモーセに「わたしはあるという者だ。」と答えられた父なる神の名を、ここで、この時に、ご自身を表すものとしてイエスが答えられたのです。 これを聞いた兵士たちは、「後ずさりして、地に倒れた。」とあります。 他の福音書では、このような状態に「弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。」と言いますが、このヨハネによる福音書では、イエスご自身が弟子たちを逃れさせたと言います。 「それは父なる神が与えてくださった人を、わたしは一人も失いませんでした」というイエスの御言葉が実現するためであったと言います。 イエスが立ち向かって進み出られたのは、兵士たちの前ではありません。 イエスは人間による裁きのためではなく、父なる神の御心を果たすための裁きの前に進み出られたのです。 そして、あらゆる人々を、この裁きから立ち去らせるようにと父なる神に向けて、とりなしの祈りをささげ続けてくださっているのではないでしょうか。 イエスご自身を裁きの場に立たせようとされているのは、父なる神です。 イエスはその父なる神に向けて、ご自身と同じ裁きの場に立たせないでくださいと祈ってくださっているのです。 罪のない神の子であるイエスが、その「神の怒りの杯」を飲み、本来飲むべきはずの杯を私たちが免れているのです。
[fblikesend]「交わりと慰めの回復」 コリントの信徒への手紙二7章8~16節
「あの手紙」とは、パウロが涙ながらにコリントの教会の人たちに書き記し、テトスに託して送った「涙の手紙」、パウロ自身に侮辱を加えた人物を除名するよう促す厳しさをもった手紙です。 直接話し合いをしようとコリントの教会に訪れたパウロに、激しい罵りの言葉を浴びせた人物がいたと言われています。 「確かに、あの手紙が一時にもせよ、あなたがたを悲しませたことは知っています。」とパウロは言っています。 「わたしたちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。 外には戦い、内には恐れがあったのです。」と言うまでに、悶々とした状態であったそのパウロが、「しかし、気落ちした者を力づけてくださる神が、わたしたちを慰めてくださいました。 今は喜んでいます。」と言うのです。 その理由は、コリントの教会の人たちが「ただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。」と言い、悲しみには「この世の悲しみ」と「神の御心に適った悲しみ」がある。 この二つの悲しみは、それぞれ異なったゴール、出口に私たちを導くと言うのです。 ユダの姿を思い起こしてみてください。 ユダはイエスの十二弟子のうちの一人です。 そのユダが、自分が描いていたメシアとは異なるイエスの姿に失望し、イエスを銀貨30枚で最後の晩餐の夜、祭司長たちに引き渡したのです。 イエスに有罪判決が下ったのを知って、ユダは「わたしは罪を犯しました」と言い、銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首をつって死んだと言います。 ユダは罪を後悔したけれども、再び主イエスを仰ぎ神のもとに立ち帰ることなく、自分で自分を裁いたのです。 聖書の言う「悔い改め」が生まれることなく、「この世の悲しみ」、出口のない悲しみに止まったのです。 一方、ペトロの姿を思い起こしてみてください。 ペトロは12弟子の代表者です。 「あなたはメシア、生ける神の子です。」と告白したその信仰の上に、主イエスは「わたしの教会を建てる」とまで言われた人物です。 そのペトロが、イエスが捕らえられた時、自分の身に迫る恐れにかられて今までこよなく慕ってきたイエスを、「このような人は知らない」と三度も否定したのです。 ユダに優るとも劣らない罪を犯したのです。 しかし、ペトロはそのような自分を悲しみながら、イエスの後を追い続け、ついによみがえられた主イエスによって三度の否定を打ち消すかのように三度も赦されたのです。 ペトロは自分の犯したことだけを後悔したのではありません。 神のみ前に立ち続け、自分の本当の姿に悲しんだのです。 「神の御心に適った悲しみ」とは、神の前に立ち続ける人の悲しみです。 神を見つめながら、今まで縛られていたものから神の方へ向き直したことからくる「悲しみ」です。 霊なる神の働きによって与えられる、信仰なしには起こりえない神の業です。 「神の御心に適った悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせる。」と言う。 主イエスが「時は満ち、神の国は近づいた。 悔い改めて福音を信じなさい。」と言われたように、自分の本当の姿を直視し、主イエスによる赦しと救いが備えられていることを知ることです。 離れてしまっていた神のもとに、赦されて立ち帰ることです。 パウロの「涙の手紙」は、自分自身の名誉回復のためでも、「例の事件」を引き起こした人たちの処罰のためでもなく、神の御前であなたがたの熱心を明らかにするため、パウロたちとコリントの教会の人たちとの間に、和解と赦しが与えられるためです。」と言うのです。 パウロはコリントの教会の人たちの「悔い改め」の姿からも、その吉報を持ち帰ったテトスの喜びの姿からも、「気落ちした者を力づけてくださる神」が働いてくださったことからも喜んでいるのです。 互いに経験した「悲しみ」は、神によってもたらされた、なくてならない「悲しみ」であったのです。 「神の御心に適う悲しみ」は、悲しみで終わることはありません。
[fblikesend]「自由にされるということ」 ヨハネによる福音書8章31~38節
主イエスは、ユダヤ教の会堂から外に出て「御自分を信じたユダヤ人たちに」、「わたしの本当の弟子とは、わたしの言葉にとどまる者である。 そうであるなら、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。」と言われたのです。 ヨハネの言う「ユダヤ教の会堂に未だに留まっている者」を、パウロもまた「石に刻まれた文字」をいかに守るべきかという「古い契約に仕える者」と言います。 モーセが神から二枚の掟の板を授けられた時、自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかった。 そのため、モーセは自分の顔に覆いを掛けたと言います。(出エジプト34:29-35) モーセの顔に現れている神の輝きを、当時の人々は「顔の覆い」によって見ることができなかった。 主なる神そのものの輝きを表す「真理」に近づくことができなかった。 その「顔の覆い」が、イスラエルの人々の心を鈍くさせているとパウロは言うのです。(コリント二3:14) 文字に記された「戒め」を守っているという自分の熱心さによって、神に認めてもらえると信じている。 救いの根拠を自分たちの側に置き、神に受け入れられるものかどうかを念頭に置いていない。 この「覆い」によって、真理そのものである主イエスが隠されてしまっているとパウロは主張するのです。 主イエスは、「ご自身の言葉として」、「ご自身をメシアと信じ告白した者」に対し語られているのです。 ローマ総督の尋問に際しても、「わたしは真理について証しするために生まれ、そのためにこの世に来た。 真理に属する人は皆、わたしの声を聞く。」と言われました。 また、「わたしは道であり、真理であり、命である。 わたしを通らなければ、だれも父のもとに行くことができない。」とも宣言されておられます。 聖書の言う「真理」とは、客観的な事実のことではなく、神自らが目に見える形としてこの世に現れてくださった主イエスのことです。 このお方に出会い、味わい、そこに注がれる父なる神のご愛とご真実に触れて、その御心を味わうことが「真理を知る」ということでしょう。 ユダヤ人たちはこのイエスの呼びかけに、「今まで奴隷になったことはありません。」と言い、「あなたたちは自由にされるとどうして言われるのですか。」とイエスに尋ねるのです。 ユダヤ人たちは「自由にされる」とは、奴隷からの解放とだけ理解するのです。 しかし、主イエスは「罪を犯す者はだれでも罪の奴隷である。」と言います。 聖書の言う「罪」とは、神のみ前に進み出ることを拒む、神から注がれる祝福を受け取ることを拒むことです。 主イエスの言葉にとどまるなら、主イエスを通して父なる神との正しい関係に回復される。 「罪」の結果である、この世の「生」が途絶えるところで終わってしまう「死」、この「死」からも解放される。 今、この世の神ならぬものに懸命に縋っている「自分自身」からも、パウロが警鐘を鳴らしている「心を鈍くしているあらゆる覆い」からも、その時々に移り変わるようなはかない「道徳、ヒューマニズム、常識、伝統」といったものからも自由にされる。 「石に刻まれた文字」、人に罪を示し、罪に定める務めではなく、裁かれて向きを変えて霊の働きによって新しい契約に仕える者へと変えられる。 「十戒」というモーセを通して与えられた神の戒めは、神の民として生きる指針です。 やがて来られる救い主によって贖われなければ、その戒めからも解放されないものです。 それを自分たちの権威や正しさのために膨大な枠組みを作ってしまった。 もはや救い主を待ち望む時代は終わり、救いの恵みが明らかにされている時代を迎えている。 主イエスご自身の方に向き直ることによって、この心の「覆い」は取り除かれることになる。 「わたしの言葉にとどまるなら、父なる神との関係に取り戻される。 父なる神そのものである真理を知り、その真理はあなたたちを自由にする。」と、私たちの努力ではなく主イエスが約束してくださっているのです。
[fblikesend]「神を完全に信頼できないヤコブ」 創世記32章2~22節
父イサクを騙して、兄エサウを出し抜いて、エサウが受け継ぐはずであった神の祝福を、自らの知恵と策略で強引に奪い取ったヤコブでした。 後でこのことを知った兄エサウは、「いつの日か、必ず弟のヤコブを殺してやる。」と心に秘めるのでした。 そのことを察知した母リベカは、自身の兄ラバンのもとに逃げなさいとヤコブを促し、この逃走劇が始ったのです。 その逃亡の途中ヤコブは、主なる神が傍らに立って、『あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。 わたしは、あなたと共にいる。 あなたがどこへ行っても、わたしはあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。 わたしは、あなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。』という約束を語るのを聞く。 その逃亡先のラバンの家で、ヤコブは20年間も労働を強いられる。 神の約束を果たされる時がついにきたと、神が再び『あなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。 わたしはあなたと共にいる。』と呼びかける。 ヤコブは妻や子どもたち、すべての財産を携え、再び逃亡の旅が始まったのでした。 神の約束があるとはいえ、故郷に帰れば兄エサウと顔と顔を突き合わせなければならない。 ヤコブは忘れていた過去の過ちを思い出し、エサウの復讐を恐れ、知恵を働かせ、様々な対策を練り実行する。 そうした準備をしたうえで、ヤコブは神に祈るのです。 過去に示された神の約束を訴える。 神の恵みの数々を憶え神に感謝するとともに、「受けるにふさわしくない者である」と告白する。 エサウが家族をも殺すかもしれないとただ神の約束にすがる。 そう祈りながらも、なおも抜け目のない才覚に溺れ、エサウに会うまでの作戦を立て、すべての準備を整え「ヤボクの渡し」に皆を渡らせ、何も持たず独りとなったヤコブでした。 神への信頼と人への恐れ、神への祈りにすがりながら知恵による策略に依り頼むヤコブでした。 しかし、ヤコブは兄エサウに、自分が故郷に戻ってきたことを予め伝えている。 神のみ前では、やり方はどうであれ神の約束に従っている。 心の憶測にある恐れを素直に訴え、懇願し祈る。 与えられた神の恵みこそ身に余るものであると告白する。 和解のため精いっぱいの慎重さをもって対処しようとしている。 考えてみれば、ヤコブはエサウとの関係を絶ち切って、逃亡先のラバンのもとで過ごすこともできたはずです。 神の呼びかけに立ち上がり、和解のために自分の身を再びもっていこうとしているではありませんか。 このヤコブに対する神の応えが、「ベヌエルの格闘」と「兄エサウとの再会」でした。 「祝福してくださるまでは離しません」と、今までと変わらず神と格闘するヤコブに、自分の知恵に頼るヤコブの腿の関節をはずし、無力なものとして砕く。 20年ぶりに自らの過ちの前にヤコブを再び立たせる。 「人を押しのける者ヤコブ」ではなく、イスラエルの12部族の族長となると「イスラエル」という新しい名を与え、兄エサウに再会させるのです。 「エサウが400人のものを引き連れて来るのを見て、ヤコブは兄エサウのもとに着くまでに七度ひれ伏した。」と言う。 無力とされたヤコブには、兄エサウへの恐れは微塵もなかった。 兄エサウの恨みも、20年の月日を経て消えてなくなっていた。 エサウはヤコブのもとに「走って来てヤコブを迎え、抱きしめ、首を抱えて口づけし、共に泣いた。」と言う。 神はご自身が語られた約束を、自らの働きをもって果たされたのです。 ヤコブは兄エサウの中に、約束を必ず果たされる神、赦しを与えてくださる神を見たのです。 このヤコブの姿は族長という一人の個人の姿ではなく、神の子とされた私たちキリスト者の姿に映ります。 ヤコブの時代にはなかったキリストの福音が、私たちにはすでに与えられ成し遂げられています。 完全に信頼し切ることのできない弱い私たちを、神がキリストの福音を通して自ら果たしてくださるのです。
[fblikesend]「拡がるキリストを知る香り」 コリントの信徒への手紙二2章12~17節
トロアスは、キリストの福音がヨーロッパにもたらされたその契機となった、パウロにとってとても印象深い町です。 一人のマケドニア人が、「マケドニア州に渡って来て、わたしたちを助けてください。」と願った幻をパウロは見たのでした。 そのトロアスに「キリストの福音を伝えるために」再び訪れたパウロは、「主によってわたしのために門が開かれていました」と証言するまでに、そこでの宣教活動は順調でした。 トロアスを訪れたもう一つの理由に、この地で弟子テトスと落ち合う約束があったのです。 コリント教会の混乱ぶりに対し、パウロが書きテトスに託した「涙の手紙」をコリントの教会の人たちが読んでどのような反応を示したのか、パウロは一刻も早く知りたかったのです。 その肝心のテトスが約束通りにトロアスに来なかった。 そのテトスに少しでも早く近づくため、トロアスの宣教活動を切り上げてマケドニア州に入って行ったのでした。 その時の心境を、「不安の心を抱いたまま人々に別れを告げて、マケドニア州に出発しました。」と記しています。 パウロは、様々な教会の心配事に常時悩まされていたのです。 そのような状態にある中で、パウロは「神に感謝します。」と言っています。 パウロが感謝していることは、「キリストの勝利の行進に連ならせてくださっていること」だと言います。 それも「いつも」です。 そして、「神が」主イエス・キリストを通してそうしてくださっていると言うのです。 古代ローマの凱旋の行進をもって、イエス・キリストがこの世で歩む姿をパウロはなぞらえるのです。 「イエス・キリストの凱旋する勝利の行進」とは、父なる神のもとから私たちのために遣わされ、この地上の生涯を経て、父なる神のもとへと帰り着く全く新しい道を歩まれたお姿そのものを示すのでしょう。 私たちのために父なる神に献げられた「十字架の死」、そこからの「よみがえり」という道。 神が備えて与えてくださった、この世からの解放と救いと赦しの入り混じった人間が歩むべき唯一の道の行進です。 それに私たちを招いて、呼びかけ、加えてくださっている。 パウロ自身がこれまで味わってきた様々な苦しみ、不安、痛みはそのためのものだった。 主イエスが辿った道のほんの一端を味わうものだった。 私たちと同じように人間として「苦しみ、不安、痛み」を味わいながら歩まれた主イエスの新しい命を携えての行進に加えられるためのものだったとパウロは思い起こすのです。 パウロが感謝しているもうひとつのことは、「キリストを知るという知識の香りを漂わせてくださっていること」だと言います。 「キリストを知る知識」とは、主イエスに出会い、呼びかけられ、とりなしの祈りに支えられ、それに従ったがゆえに味わった体験、知らされた神の知恵と力の味わいを指すのでしょう。 その味わった「香り」が、「わたしたちを通して」、「至るところに」漂うと言うのです。 この「香り」は、パウロたちを用いておられる神ご自身が漂わさせてくださっていると言い、そこに留まらず自分たちのことを「わたしたちはキリストによって神に献げられる良い香りです。」とまで言うのです。 「キリストの香り」という犠牲の香りが、神に向かって献げられ、神が受け入れてくださっていることが大切なのです。 「良い香り」が、救われる者にとって幸いをもたらし、滅びる者にとって裁きとなるとしても、その働きはすべて神のみ手の中にあるはずです。 その働きに「与ること」が赦されていることに、パウロは気づかされ神に感謝しているのです。 パウロのごとく、不安や弱さを憶えつつも神にその働きを感謝しつつ、委ねつつ、逃げることなく委ねて結果はどうであれ進むのです。 そうすれば、自分を見つめることから始まって、主イエスを仰ぎ、励まされ、主イエスの神のもとへと凱旋していく行進に加えられていることに気づかされ、神に受け入れられる「良い香り」を漂わせてくださるのです。
[fblikesend]« Older Entries Newer Entries »