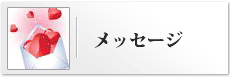「もう用意ができましたから」 ルカによる福音書14章15~24節
主イエスは、「神の国」は盛大な宴会を催しているようなものである。 特別に大勢の人が招かれる、喜ばしい交わりの場であると言います。 招く家の主人は、父なる神である。 遣わされる僕は、主イエスである。 家の主人が用意して、その準備が整ったら、僕を遣わして人々を招く。 僕である主イエスによって招かれる、父なる神と共にある喜びの場所であると言います。 当時のイスラエル社会では、招かれた客は招き返すのが習わしでした。 その招きも、一度あらかじめ招いておいて、時期が来てその準備が整ったいよいよという時に、僕を遣わし再び招くのでした。 もし、その招きをその時に及んで断るというのは、その家の主人に対する「侮辱」になったというのです。
「ファリサイ派のある議員の家に招かれた食事」でした。 招き、招かれる、いつものメンバーで溢れていた食事であったのでしょう。 律法の教えを第一とする道徳的にも、宗教的にも、イスラエルの人びとの模範となるファリサイ派の人たちを相手にして、イエスは「神の国」を「たとえ」で語ったのでした。 「神の国」は大勢の人を招くものである。 時刻になったら招くものである。 用意ができたから招くものである。 父なる神が自ら計画を立て、準備をして、み子イエスを遣わしてまで「もう用意ができましたから、おいでください」と言っているようなものだとイエスは言います。 今まで一貫して語ってこられた「時は満ちた。 神の国は近づいた。 悔い改めて、福音を信じなさい。」と、「宴会」のたとえを用いてこの「神の国」を語っておられるのです。 もし、この招きを断れば、その家の主人に対する大きな侮辱となるのです。 三人の客がその招きを断っています。 畑を買った人。 牛を買った人。 結婚したばかりの人です。 理由は様々なことを言っています。 「~しなければなりません。 今~しているからできません。」 私たちがよく使う言葉です。 父なる神が周到に備えたものを、選ばれたイスラエルの民が主イエスによって再び招かれている。 その招きを今、イスラエルの民が拒んでいる。 そのことを、僕から報告された家の主人は怒ります。 しかし、その招きを家の主人は決して止めないのです。 「急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、からだの不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れて来なさい。 通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れて来なさい。 この家をいっぱいにしてくれ。」と「神の国」の祝宴に強く招こうとされるのです。 ファリサイ派の議員の家で催された宴会に招かれているのは、神が第一であることを教える人たちの筈です。 しかし、彼らは自分の持ちものが大切なのです。 自分の事情、自分のことが大切なのです。 自分を招く人たちだけを招く交わりだけに、意を注いでいる人たちです。 「神の国」の宴会は、父なる神が用意して、僕イエスを一人一人の家に出向かせ、扉をたたいて招く宴会です。 人を招くようなものを何ひとつもっていない人たちこそ招かれる宴会です。 招かれた者がたたかれた扉を開けて、その招きに応えるだけで入れてもらえる宴会です。 ですから、主はそのことを「恵み」、「祝福」と言われるのです。 信仰は私たちが用意したり、つくり上げるものではありません。 父なる神がイエス・キリストを通して用意してくださるものです。 私たちはそのイエスの呼びかけに、扉を開いて応えるだけです。 主イエスは、いつまで経っても「神が用意してくださった恵み」を受け取ろうとしない私たちのために、「聖なるささげもの」となるために十字架に上がってくださいました。 その十字架のうえで「すべては為し遂げられた」と頭を垂れて息を引き取り、私たちにその霊を分け与えてくださったのです。 このイエスのご真実によって私たちは「神の国」に招かれたのです。
「耳が聞こえず舌の回らない人」 マルコによる福音書7章31~37節
弟子たちがどうしても忘れることができなかった、「エッファタ」というイエスが発した短い言葉の響き。 イエスが語られた、聖書の中に今もなおアラム語のままで記されている言葉、「エッファタ」、「開け」という意味の言葉に注目したい。 聖書によると、イエスと弟子たちはティルス、シドン、デカポリス、そしてガリラヤという地を辿って旅をしています。 地図で確認してみると、どう考えてもわざわざ大変な回り道をしているとしか思えません。 ガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスは、イエスをユダヤの体制を壊す者とし捕らえようとしました。 ユダヤ教の指導者たちは、イエスを自分たちに逆らう者として憎みました。 イエスはそのような身に迫る危機を回避しながら、異邦の地においても、一人の人物のために、その人物を支える人々のために、そして、愛する弟子たちの養いのために働いておられたのです。
ひとりの「耳が聞こえず舌の回らない人」に、イエスは出会われます。 「人々が、イエスのもとに連れてきた」人でした。 人と交わることのできない、そう諦めて心を閉ざした人であったのでしょう。 しかし、人々はイエスに何とかしてほしいと、「この人の上に手を置いてください」と願ったのでした。 耳が聞こえるようにしてください。 舌が回るようにしてくださいという祈りでした。 人々のそのような思いで連れて来られた人にイエスがなさったこと、それが弟子たちに大きな驚きと強烈な印象を刻んだのでしょう。 ここに詳しく述べられています。 「この人だけを群衆の中から連れ出した」 「指をその両耳に差し入れた」 「唾をつけてその舌に触れられた」 「天を仰いだ」 「深く息をついた」 そして、最後に、その人に向って「エッファタ」と言われたのです。 イエスは連れて来られただけの人を迎え入れ、受け入れました。 多くの群衆の中から連れ出して、二人きりで向き合われました。 その人はイエスの前に立ち、イエスはその人のからだに触れて、働きかけています。 イエスは、人と通じ合える言葉を持ち合わせないその痛みを、からだに触れてともに味わってくださっています。 ですから、イエスは「天を仰いだ」のです。 そして、「深く息をつかれた」のです。
天を仰ぐとは、「イエスの祈りの姿」です。 「深く息をつかれた」とは、祈るすべすら知らないこの心閉ざした人に替わって、天からの力と憐れみを強く求めてくださったということです。 これが「深く息をつかれたイエスの呻きの祈り」です。 イエスは目を天に向けて、耳を聞えなくさせているもの、口を語らせなくしているもの、父なる神との交わりを一切途絶えさせているその苦しみを背負って、呻いて、天を仰いで祈られたのです。 人々はその人のからだが癒されることだけを願いました。 イエスは心を閉ざした人と神との交わりの回復のために、人々が望んだ以上のことを、全身全霊で天を仰いで、深く息をついて、呻いて、最後のひと言の祈りを「彼に替わって」、父なる神の力と憐れみを願い求め「エッファタ、開け」と叫ばれたのではないでしょうか。 イエスは神との交わりの回復のために、「聞くこと」を願われました。その耳を開かれたのも、その舌のもつれをほどいたのも、このイエスの「天を仰いだ祈り」です。 それを成し遂げてくださるのは、このイエスの「とりなしの呻きの祈り」が働くところに届けられる神の霊だけです。 ですから、私たちはイエス・キリストのみ名によって祈ります。 「耳が聞こえず舌の回らない人」の最大の恵みは体の癒しではなく、イエスそして父なる神との出会いでした。 その人を連れて来た人々の最大の恵みは、神との交わりが途絶えていた人の苦しみを共に担ったことによって、群衆の中からこの人と共に連れ出されたことでした。 ですから、私たちは共に苦しみ、悲しみを担い合うのです。
「イエスのみ業を承き継ぐ教会」 使徒言行録10章34~43節
聖霊が降って、力を得て語り出した弟子たちの働きにより、ユダヤ、サマリアへとその宣教が拡がり、信者の数が増えていきました。 その有様を使徒言行録は、1章から12章まではペトロを主人公にして、13章からはパウロを主人公にして語っています。 34節に、「そこで、ペトロは口を開きこう言った。」 「神は人を分け隔てなさらないことが、よく分かりました。」 「どんな国の人でも、神に受け入れられるのです。」と、コルネリウスという異邦人の家で福音を語り始めました。 コルネリウスはローマの軍隊の百人隊長であり、ユダヤ人ではありません。 しかし、「信仰あつく、一家そろって神を畏れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた」ほどの信仰者でした。 そのコルネリウスに、神の言葉が届きます。 「あなたの祈りと施しは、神の前に届き、覚えられた。 今、ヤッファへ人を送って、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。」と、神は促したのです。 一方、そのペトロにも同じように、神の言葉と幻が届いたのです。 大きな布のような入れ物の中に、いろいろな動物が入っていた幻でした。 その中には、地を這っていく動物など、ユダヤ人にとって食べてはならない動物が混じっていたのです。 その不思議な幻の中で、神は言います。 「ペトロよ、身を起こして、それらを屠って食べなさい。」というものでした。 そのような汚れたものを食べたことがありませんとペトロが答えるしかない、神のご命令であったのです。 しかし、神は「神が清めた物を清くないなどと、あなたは言ってはならない。」と譲りません。 なぜそのようなものを食べなさいと言うのだろうかと思案に暮れていたペトロに、コルネリウスから差し向けられた者が尋ねて来たのです。 その時、神の霊が「ためらわないで、この者たちと一緒に出発しなさい。 わたしがあの者たちをよこしたのだ。」と、ペトロを促したのです。 ユダヤ人が異邦人を尋ねて、交わるということは律法違反です。異邦人と交われば汚れると教えられて育ったペトロでした。 最初のころの教会は、ユダヤ人以外には福音の宣教などしなかったのです。
そのような時に、ペトロはこの幻の意味を初めて知りました。 「神が清めた物を清くないなどと、あなたは言ってはならない。」と神が導いている。 民族を越え、違いを越え、宗教を越えて、汚れたものと映るところに遣わされようとしている。 そのために、神の導きにより自分が招かれていることに気づいたのです。 ペトロは決断しました。 当時考えられない大きな溝を越えようと決心しました。 律法に従った生活を捨てようと、神の幻とみ言葉による導きによって一歩踏み出しました。 コルネリウスもまた、犬猿の仲であった民族の壁を越えようとして、ペトロを招きました。 ですから、ペトロは「神は人を分け隔てなさらないことが、よく分かりました。」 「どんな国の人でも、神に受け入れられるのです。」と語り始めたのです。 そして、イエスご自身の生涯を語り出します。 「神がイエス・キリストによって、平和を告げ知らせてくださった。 御言葉を送ってくださった。」 その「イエスは方々を巡り歩いて人びとを助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒された。」 私たちはその証人ですと、イエスのみ言葉を忠実に承き継いだのです。 イエスの行ったみ業もまた、「イエス・キリストが癒してくださる。」と忠実に承き継いだのです。 ペトロに特別な力が与えられたのではありません。 ペトロは、イエスによって命を受けることができるようにと、ただひざまずいて祈っていただけです。 天に昇られたイエスが見えない姿となって、イエスの業をペトロに注いだのです。 ペトロが承き継いだイエスのみ言葉とみ業が、私たちにも承き継がれているのです。 ひざまずいて祈り、イエスによって命を与えられる生きた教会とされたいと願います。
「生きた教会とは」 使徒言行録9章26~31節
使徒言行録は、イエスのそば近くにあってイエスがどのようなお方であるのかを直接見てきた使徒たちが、イエスが天に戻られた後、どのようにして群れをつくっていったのか。 その使徒たちが宣教し、信者を仲間に加えていったその姿と、加えられていった信者がどのような教会生活、信仰生活を送っていったかを語っています。 「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を得る。 そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる。」 このみ言葉から最初の教会の宣教が始まり、初めは12人の使徒たちから、その後、ステファノ、フィリポ、パウロなどを通して多くの信徒たちが加えられていきました。 9章31節に、「こうして、教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地方で平和を保ち、主を畏れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。」とあります。 ステファノは石を投げつけられ殺された最初の殉教者でした。 フィリポは素晴らしい働きをしたサマリアから、寂しく何もない、荒れ果てた地に主に従って遣わされて行った者でした。 パウロはキリスト者を迫害する指導者から転換し、キリスト者の群れの働き人となったが、なかなか人びとに受け入れてもらえなかった者でした。 しかし、これらのキリスト者の戦いの中にあっても、新しく立ち上がった生まれたての教会は、「一つの教会」(エクレシア)として、「平和を保っていた」というのです。 「わたしは、平和をあなたがたに残し、わたしの平和を与える」とイエスが約束された平和とは、「この世が与えるような平和ではない。 心を騒がせるな。 おびえるな。」と言われた平和です。 戦いの中、悩みの中、心騒がせる中にこそ与えられる「イエスにある平和」です。 イエスと共にある、このお方によって救い出されたという確信の中に、「一つの教会」となって「平和を保ち、主を畏れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった」のです。 たくさんの信者が群れに加えられたサマリアを、フィリポは離れたくなかったでしょう。 しかし、フィリポは何が何だか分からない状態でも、「行け」と言われる主のみ言葉に従うのです。 そこに、フィリポと同じように主が働きかけ、導き出した人物に出会うのです。 この二人の交わりの幸いは、「主を畏れて」従ったことによって与えられたものでした。 主が導いたその場所でバプテスマが起こされ、新しい宣教の道が開かれていったのです。 最初の群れはこのことが分かるまで、「聖霊の慰めを受けていた」と表現されています。 ステファノが自分に石を投げつけている人びとに、「主よ、この罪を彼らに負わせないでください」と祈る姿を失わなかったのも、パウロがまったく正反対の働きに導かれ、受け入れられなくても「ますます力を得てイエスが救い主であることを論証し、ユダヤ人たちをうろたえさせた」のも、聖霊の慰めがあったからでした。 生まれたての教会がユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地方にまで拡がっても、「一つの教会」としてイエス・キリストの平和の中に保たれていた。 人を恐れることなく、主だけを畏れて、主に従い、主のみ心だけを尋ねていくことができた。 どのような戦い、悩み、恐れ、煩いの中にあっても、彼らはよみがえられたイエス・キリストの霊によって慰められていた。 この土台が固められ、教会は発展し、信者の数が増えていったと語っているのです。 この聖霊が注がれた使徒たちの宣教を通して、その使徒たちの証言である聖書のみ言葉を通して、今もなお、私たちをそばに呼び寄せ語ってくださっています。 どうにもならなかった私たちをつくり変え、生まれ変わらせてくださっています。 その一人一人の群れが、今日の教会となっています。 その土台は、イエス・キリストであり、このお方に対する私たちの信頼です。
[fblikesend]「父なる神にささげる祈り」 ヨハネによる福音書17章6~19節
十字架のために捕らえられるその直前にも、イエスは父なる神に祈っておられます。 ご自身のこと、この世に残される弟子たちのこと、そして、これから遣わされる弟子たちによってご自身を信じる人々のためにも祈っておられます。 その中で6節から19節の、後に残される弟子たちのことを祈っておられる「祈り」に注目したいと思います。 イエスは弟子たちのことを、「世から選び出してわたしにくださった人々」、「父なる神のものであったものからわたしに与えられた人々」と言います。 その弟子たちは、父なる神から受けたみ言葉が伝えられた者、そのみ言葉を守った者、受け入れた者、そのみ言葉に生きた者であると言うのです。 確かに、この弟子たちは目に見える形で父なる神がどのようなお方であるのかを、イエスを通して知りました。 父なる神のみ言葉が、イエスを通して与えられました。 イエスは弟子たちのことを、「父なる神がわたしをお遣わしになったことを信じるようになった」と言います。 そのイエスが弟子たちのために、「お願いします」と父なる神に祈ってくださっています。 その祈りは、「聖なる父よ、わたしに与えてくださった御名によって彼らを守ってください。」 それは、「わたしたちのように、彼らも一つとなるため」と言うのです。 「わたしたちのように」、「父なる神と子なる神が一つであるように」です。 この弟子たちがイエスを通して、父なる神と結ばれるようにして一つになるよう祈っておられるのです。 私たちは与えられている賜物も、姿も、生い立ちも違います。 個性も違います。 考え方も、物事の進め方も違います。 それがすべて一つになる、同じような人間になることは不可能です。 しかし、イエスはそれらの違いを超えて、イエス・キリストに結ばれて一つになるという一点において、私たちは一つになることができると言います。 私たちは、ひとりの罪人としてみ前に立っています。 その罪がすでに赦されています。 その恵みに与かるようにと招かれています。 これがイエス・キリストに結ばれて一つになることの、唯一の根拠ではないでしょうか。 イエスは、それは「聖書が実現するためです。 ご自身の喜びが私たちに満たされるためです。」と祈ります。 み言葉が語られ、伝えられ、受け入れられ、信じられるところに、そのみ言葉が成し遂げられる。 イエスが父なる神との交わりの中で味わっている喜びに満たされると言うのです。 そのために、「守ってください」と父なる神に祈ってくださっているのです。 もうひとつイエスは祈っておられます。 「彼らを世から取り去ることではなく、悪い者から守ってください。」 「悪より救い出したまえ」という主の祈りです。 愛する弟子たちを、この世から取り出して守ると言っているのではありません。 この世にあって生きることができるように「悪より救い出したまえ」と祈ってくださっているのです。 この世から選び出して守ってくださいという祈りとともに、もうひとつ、神のご用のためにささげられるようにと祈っておられるのです。 この世から選び出す祈りとともに、再び、この世に送り出す祈りが込められています。 この世を愛し、すべての人を救い出すために遣わされたイエスは、失われた父なる神の民を取り戻すために、私たちを再び送り出すのです。 この世とは、自分の力に依り頼む人びとの世界、神を必要としない世界です。 ですから、イエス・キリストを無用として捨てたのです。 ですから、イエスは父なる神に、このような世にあって、「弟子たちを、私たちを悪い者から守ってください」と執り成すのです。 守るだけではない、ご自身の民を取り戻すために、神に属する者、聖なる者として再び送り出すのです。 私たちが、この務めにささげられる者となるため、イエス・キリストにあって一つとなるためです。
[fblikesend]「天の国はその人たちのもの」 マタイによる福音書5章1~12節
イエスのもとに集まって来た人々は、この世の幸いから見離されたような人々、貧しく、弱く、無力な人々でした。 そのような群衆をよくご覧になって、その代表として、また、その群衆に遣わされていく弟子たちに、直接、語られたイエスのみ言葉。 ガリラヤで始められた宣教活動の初めに、「幸いである」という祝福の言葉をもって福音を語られたイエスのみ言葉。 それが、今日の聖書箇所のみ言葉でした。 イエスは、「幸いである」という人を、「心の貧しい人々、悲しむ人々、義に飢え渇く人々、義のために迫害される人々」と、この世の道理では真逆の人びとのことを言います。 また、「柔和な人々、憐れみ深い人々、心の清い人々、平和を実現する人々」には、そのことを貫き通すことには困難を極める、克服するには覚悟が要求されることが容易に分かります。 しかし、イエスは、そのような人々を「幸いである」と、新しい世界をお示しになりました。 最初に、「心の貧しい人々は、幸いである。 天の国はその人たちのものである。」と言われています。 イエスは、心を貧しくしなさいとか、豊かにしなさいと戒めておられるのではありません。 あなたがたの心の貧しさのゆえに、「幸いである」。 すでに心の貧しさを知っているので「幸いである」と、弟子たちに向けてその祝福を語っているのです。 「心の貧しい人々」とは、「霊の貧しい人々」、「霊において貧しい人々」とも訳すことができる言葉です。 人間には、神を求める「霊性」があると言われています。 大人も子ども例外なくです。 この神を求める「霊性」の貧しさを知らない人は、神を求めることも、神を感じることさえできません。 神を求めるという霊において、その貧しさが分からないからです。 しかし、神に依り頼む人は、益々、神を求める霊性が増し加えられます。 神のもとを離れてしまった本当の自分の姿に気づかされます。 神のもとを離れてしまう苦しみ、悲しみ、痛みを更に憶えます。 自分の中の奥深くに巣くう「罪」に敏感になります。 この自分の貧しさに気づいて、神のもとへ立ち帰った人々、あなたがたは神との交わりを回復したのである。 自分で自分を救うことなどできないと、その自分の貧しさを神の前に知ったのです。 ですから、「あなたがたは幸いである。 天の国はすでに、この私とともに来ている。 あなたがたのものである。」とイエスは言われたのです。 マルティン・ルターは、十戒の第一の戒め「わたしをおいて、ほかに神があってはならない」という戒めこそ、自分を誇らず、神の恵みによってのみ生きることを語る、「まことの貧しさ」であると言っています。
神の豊かさは、私たちの貧しさのなかに働かれます。 ですから、イエスは貧しい人たちのところへ、悲しみ嘆いている人たちのところへ出かけて行って、共に歩まれたのです。 私たちのもっているちっぽけな、吹けば飛ぶようなはかない誇りにしがみついている時には、決して経験することのできない大きな豊かさを知ることができる。 だから「あなたがたは幸いである」と、祝福してくださるのです。 この世とは、まったく逆の価値観をもって、イエスは「天の国はその人たちのものである」と宣言されました。 私たちは、この語りかけておられるお方のみ言葉を受け入れることもできるし、否定することもできます。 私たちは、信じるようにとこのお方に招かれています。 あなたがたは信じることもできるし、自分たちの貧しさを凌駕する神の豊かさを体験することができる。 だから、「喜びなさい。 大いに喜びなさい。 天には大きな報いがある。」と言われたのです。 「自分を空しくして、受け取りなさい。 喜びなさい。 大いに喜びなさい。大きな恵みがある。」と言われたのです。 私たちは、イエスの口から直接語られたこのみ言葉を、信じる者の群れでありたいと願います。
「みこころの天になるごとく」 ルカによる福音書22章39~46節
十二弟子のうちのひとり、イスカリオテのユダが裏切って、イエスをまさに捕らえるその直前に、イエスが最後に弟子たちに教えられたことが「祈ること」でした。 その祈りが、「わたしの願いではなく、御心のままに行ってください」という祈りでした。
地上での最後の場面にもかかわらず、ルカは「いつものように」、「いつもの場所」に行かれたと言います。 その場所はオリーブ山でした。 イエスは、そこを祈りの場所としておられました。 当然、その場所をユダは熟知した場所であったでしょう。 まるで、ユダが大祭司の手下を連れてやってくるのを、イエスは待っておられるかのようです。 そのような時に、イエスは弟子たちに「誘惑に陥らないように祈りなさい」と言われたのです。 そして、弟子たちと離れて祈り始められました。 ご自身の「祈りの姿」を見せるため、ご自身の「祈りの言葉」を聞かせるためでした。 剣を置いて「祈りなさい」と弟子たちに言われただけでなく、父なる神を仰ぐ「祈りの姿」を見せて、赤裸々に語られる「祈りの言葉」を敢えて聞かされたのです。 イエスの「祈りの姿」は、ひざまずいて祈られています。 「苦しみもだえ、いよいよ切に祈られて」います。 いつものように、いつもの場所で祈る時と場所をもっておられます。 「汗が血の滴るように地面に落ちる」までに祈っておられます。 「祈りの言葉」の内容は、「父よ、御心なら、この杯をわたしから取りのけてください。」というものでした。 イエスが「取りのけてください」と切に願うその「杯」こそ、イエスにつきつけられたままの「杯」です。 何度イエスが祈っても、答えの返って来ない「杯」です。 神ご自身が、愛するみ子の願いを聞き入れることのできない、イエスと共に苦しんでおられる父なる神の沈黙です。 ですから、「汗が血の滴るように地面に落ちる」までに祈られたのです。 そしてついに、「しかし、わたしの願いではなく、御心のままに行ってください」という祈りに達したのです。 そこには、父なる神には間違いがないというイエスの「信頼」があります。 「御心のままに」というイエスの「服従」があります。 父なる神は、私たちの「信頼」と「服従」によってご自身の御心を果たされます。 その御心は、必ず私たちのうえに、私たちを通して現わされます。 この「祈りの姿」と「祈りの言葉」を、これからこの世を去って父のもとに帰るにあたって、遺される弟子たちに伝えたのです。 この最後の祈りを終えて、ユダの裏切りに身を委ねられたのです。 これが、祈りの中の祈りと言われる、ゲッセマネの祈りです。 御心が分からない苦しみが、私たちにはあります。 答えが与えられないから、苦しいのです。 確信の祈りに至らされたイエスに、父なる神は「力づけた」とあります。 神はイエスに、その「杯」を取りのけたのでも、過ぎ去らせたのでもありません。 この「杯」を乗り越えることのできるようにと、力を与えてくださったのです。 祈り終えたイエスは立ち上がっておられます。 ですから、イエスは相も変わらず「眠り込んでいる弟子たち」に、「なぜ眠っているのか。 誘惑に陥らぬよう、起きて祈っていなさい。」と重ねて言われたのでした。
「母と子の祈り」 サムエル記上3章1~11節
ある人物の少年時代の姿です。 この人物こそ、イスラエルのダビデ王朝を造り上げるという大きな役割を果たした人物です。 主の言葉を厳しくとも隠さず語り告げ、初代の王サウルに油を注ぎ、二代目の王ダビデに油を注いで、イスラエルにダビデ王朝を備えた預言者サムエルです。 そのサムエル少年が、「祭司エリのもとで主に仕えていた」とあります。 しかし、この時代は「主の言葉が臨むことは少なく、幻が示されることもまれであった」のです。 当時の指導者たちは、神の言葉に聞く者がいなかった。 神の言葉を包み隠さず語り告げる預言者もまた、まれでした。 しかし、聖書は「まだ神のともし火は消えておらず、サムエルは神の箱が安置された主の神殿に寝ていた」、「サムエルが主に仕えていた」と語っています。 私たちの主は、直接、ご自身の言葉によって私たちにご自身を現わそうとされるお方です。 直に語りかけてくださる交わりを、心から喜んでくださるお方です。 そのために、直接「祈ること」が私たちに赦されています。 ここにあるサムエル少年の姿を見てください。 幼いながらも、「神の箱が安置された主の神殿」で祈りをささげ、礼拝をささげて神のそば近くにいます。 「サムエル」と直にその名を呼ばれる主に、「ここにいます」と祈りで答えています。 しかしサムエル少年には、それが主の声だとは分かりませんでした。 先生である祭司エリの声だと思った。 ですから、エリのもとに急いで走って行って、「お呼びになったので参りました」と言っているのです。 そんなことが三度もありました。 それは、「サムエルはまだ主を知らなかったし、主の言葉はまだ彼に示されていなかった」からであると、聖書は言います。 そうであるなら、主のことが未だに分からなくても、主の言葉が未だに示されていなくても、主は私たちの名を呼んでくださっている事実を、このことは示しています。 祭司エリは「サムエルを呼んでおられるのは主である」と悟り、「もしまた呼びかけられたら、『主よ、お話しください。 僕は聞いております。』と言いなさい。」と、サムエルに教えたのです。
祈りには、二つの祈りがあります。 「僕は、話をします。 主よ、どうぞ聞いてください。」という私たちの「語りかける祈り」と、「主よ、お話しください。 僕は聞いております。」というエリがサムエルに教えた「聞く祈り」です。 私たちの祈りは徹底的に「聞いてください」という祈りです。 しかし、三度も呼びかける主の並々ならぬ思いを悟った祭司エリは、主の言葉を静かに聞き取る祈りをサムエルに教えたのです。 そのサムエルに、そば近くに立たれた主の四度目の呼びかけが届いたのです。 「どうぞお話しください。 僕は聞いております。」 これが少年サムエルの祈りです。 この祈りは、祭司エリに整えられた祈りでした。 それと同時に、サムエルの母ハンナの「待ち続ける祈り」の結晶でもありました。 子どもの与えられないハンナの「私に子どもを与えてください」という祈りが、「自分に子どもが与えられるなら、その子は主に仕えるためにおささげします」という祈りに変えられた母ハンナの「待ち続ける祈り」です。 私たちの身に起きるすべてのことが、主のみ業に結びついています。 語りかけておられる主の声に応える私たちの小さな祈りもまた、主のみ業に結びついています。 たとえ、私たちの求めるものが間違っていたとしても、求める方法ですら間違っていたとしても、私たちの主の名によって主のみ心に適うものに変えてくださるのです。 私たちの小さな祈りが、主の大きなみ業に結びつけられていくのです。 すべてご存じのお方の声に、「主よ、お話しください。 僕は聞いております。」と耳を傾けることです。 祈りは、主と私たちとの交わりです。 主のみ言葉に聞いて、それに応える私たちの働きです。
「三度目に現れた復活の主」 ヨハネによる福音書21章1~14節
ひとりの女性の「わたしは主を見ました」という証言から、驚くべき復活の事実が拡がっていきます。 この証言にも、弟子たちは信じようとはしませんでした。 ユダヤ人たちの追手を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけて家の中に閉じこもっていたのです。 弟子たちの閉ざされた心を乗り越えて、よみがえられたイエスが入って来られて、真ん中に立って、ご自身の手とわき腹をお見せになったのが弟子たちに現れた最初の光景でした。 「あなたがたに平和があるように。 父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」と言われ、息を吹きかけられて「聖霊を受けなさい。」と言われたのでした。 それでも、トマスに代表されるように、「あの方の手に釘の跡を見、この指を入れてみなければ、わたしは決して信じない」と本音で思っていた弟子たちは、相も変わらず家の中に閉じこもっていたのです。 その弟子たちに、「あなたの指をここに当てて、わたしの手を見なさい。 また、あなたの手を伸ばし、わたしのわき腹に入れなさい。 信じない者ではなく、信じる者になりなさい。」と言われたのが、二度目の光景でした。 そして、これらの弟子たちに三度目に現れたのが今日の聖書箇所です。
その三度目の場所は、弟子たちがかつての日常生活に戻っているかのような場所でした。 ペトロの呼びかけに様々な弟子たちが一緒になって、魚を取りに舟に乗り込んでガリラヤ湖に行く。 聖書が語る「舟」とは、弟子たちの群れを象徴します。 手慣れたガリラヤ湖であったにもかかわらず、一晩中、かつてやっていたと同じような漁の仕方で試みたが何も取れなかった。 その弟子たちの姿を、イエスは岸辺に立って、その一部始終をご覧になっておられたのです。 弟子たちは、そのイエスに気づきません。 その弟子たちにイエスの声が届きます。 「子たちよ、何か食べるものはあるか。 舟の右側に網を打ちなさい。」 これが、その時のイエスの言葉でした。 聖書の言う「右側」とは、神の側のことです。 弟子たちの群れが一緒になって、かつてのような漁をしていた。 しかし、それは神の側の働きではない、 舟の左側に網を打っている。 一晩中、全力を傾けても、彼らが望むものは何も得ることができなかった。 しかし、神の側に目を向け、網を下ろしなさいとイエスは言われたのです。 それがイエスの声だとは分からなかったけれども、聞えて来た声の通りに網を打ってみると、網を引き揚げることができないほど多くの魚がもたらされたと言うのです。 その「しるし」を見て、弟子たちは岸辺で叫んで折られたお方がイエスであることを知ったのです。 私たちは、復活の主が現れる時、それがイエスであると直ちには分かりません。 イエスの方から私たちに働きかけられて、そのよみがえりの霊を吹き入れられて初めて、その出会いが始まります。 そして、私たちがその呼びかけに応えて、従って行って初めて、その存在が分かります。 弟子たちは喜んで、岸辺のイエスのもとに戻ってきたのでしょう。 そこには、炭火が起こされていた。 その上には、魚がのせてあった。 そして、よみがえられたイエスが、そこで待っておられた。 そのイエスが、「今とった魚を何匹か持ってきなさい。」 「さあ、来て、朝の食事をしなさい。」と招いてくださったのです。 恵みの大きさが大事なのではありません。 私たちがどれだけ、イエスが与えようとしてくださっているものを受け入れたかどうか。 み心に応えて従ったかどうか。 イエスは、「人間を取る漁師」にするために、決して破れることのない網を用意してくださっているのではないでしょうか。 そのために、「わたしもまたあなたがたを遣わす。 ですから、聖霊を受けなさい」とイエスは言われたのです。
「復活のいのちに生きる」 コリントの信徒への手紙二 4章16節~5章5節
順風満帆であったユダヤ教の指導者であったパウロが、よみがえられたイエスに出会い一変したその生涯には、次から次へと苦難と絶望が訪れました。 牢獄に囚われ、最後には殉教の死を迎えたと言われているパウロでした。 傍から見れば、愚かな、損な人生を自ら選んだ人と見えるでしょう。 そのパウロが、「だから、わたしたちは落胆しません。」 それは、「たとえわたしたちの外なる人は衰えていくとしても、わたしたちの内なる人は日々新たにされていく」からであると言います。 これはどういうことでしょうか。 「外なる人」とは、死に向って行く私たちの肉体のことを語っているのでしょう。 年齢を重ねるにつれて、この「外なる人」のもろさ、はかなさを私たちは痛感します。 しかし、パウロは、その「外なる人」の中に、「内なる人」がある。 それは、日々新たにされると言うのです。 パウロはこのことを、「わたしたちは、このような宝を土の器に納めています。」 「この土の器の中に、神のもとからくる並外れて偉大な力を納めている」とも表現しています。 イエスによってもたらされた復活の力が、パウロの「からだ」の中に生きているからです。 そのことを、「キリストがわたしの内に生きておられるのです。 わたしが今、肉において生きているのは、わたしを愛し、わたしのために身を献げられた神の子に対する信仰によるものです。」(ガラテヤ2:20)と言っています。 パウロは実に、「イエスの復活」がもたらした、「自分自身の復活」を実体験していたのです。 ですから、「わたしたちの一時の軽い艱難とは、比べものにならないほど重みのある永遠の栄光をもたらされた」と証言できたのです。 私たちは、自分自身の「からだ」を見つめれば見つめるほど落胆します。 絶望もします。 目に見えるものが、落胆、絶望させるのです。 しかし、「比べものにならないほど重みのある永遠の栄光」、それがイエス・キリストの復活であった。 これに与かることが「比べものにならないほど重みのある」恵みであった。 「私たちの復活」の初穂が、「イエスの復活」であった。 ですから、「わたしたちは落胆しません。」とパウロは宣言したのです。
「内なる人」が日々新たにされていくとは、私たちが素晴らしい姿に変身することではありません。 どこまで行っても、「土の器」に変わりはありません。 しかし、この「土の器」こそ、神が息を吹きかけてくださった「からだ」です。それは、「死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるため」(4:11)です。 そのために、私たちの「からだ」が用いられるのです。 「比べものにならないほど重みのある」神の創造の業が、この取るに足りない私たちの小さな存在を日々新たにしてくださるのです。 このはかない、もろい「外なる人」を通して、神の業が現れると言うのです。 パウロは苦しみもだえている「外なる人」のうえに、やがて着ることになる「内なる人」を、今、苦しみの中に着ていると言っています。 イエスこそ「外なる人」をかぶせられて、ただ黙って苦しみを引き受けて神のみ心に従ったお方でした。 そのイエスが復活させられて、私たちの復活の初穂として、命を与える復活の霊となってくださった。 人間の「からだ」をもったイエスの中に、この「並外れたよみがえりの力」が隠されていた。 そのことにパウロは気づかされたのでした。 私たちの「からだ」の中にも、この「宝」が納められています。 私たちは、このことを伝えるために、この世に遣わされています。 この「比べようのないほどに重みのある力」、「天にある永遠の住みか」を宿しながら、苦しみもだえながらも希望をもって、「わたしたちは落胆しません」と宣言することのできる恵みが与えられているのです。
« Older Entries Newer Entries »