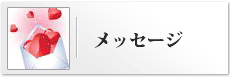「キリスト者の誇りとは」 コリントの信徒への手紙二1章12~14節
パウロは、コリントの教会の人たちとの間に発生した問題を赤裸々に語ります。 パウロが危惧したことは、パウロ個人に対する批判のことではなく、パウロが使命としている異邦人宣教として語ってきた主イエスの福音が歪められて、その福音に対する疑いが起こっていることです。 自分自身に対する弁明ではなく、福音の内容に対する誤解を解くことだけを念頭にパウロは行動したのでした。 「このような確信に支えられて、わたしはあなたがたがもう一度恵みを受けるように」と呼びかけています。 前もって書き送った「涙の手紙」により、コリント教会の人たちとの関係が好転したとは言え、今もなお完全に一つとなり得ていないコリントの教会の人たちを「あなたがた」と呼んで、パウロは個人的な私信ではなく主イエスの福音に支えられているすべての信仰者を含めて「わたしたちは」と言って呼びかけるのです。 「わたしたちは世の中にある」と言います。 教会の群れはこの世の中に存在し、決して現実の外にあるのではありません。 従って、少し気を許してしまうと、いつの間にか「世の中」と全く変わらない、人間の知恵が闊歩する事態に容易く陥るのです。 教会は神のみ心を尋ね求めながら歩む群れである。 なのに、今やコリントの教会がそうした教会であることを捨て去ろうとしている姿にパウロには映ったのでしょう。 創立に関わった指導者パウロ個人との人間関係に関わる枝葉末節の軋轢の問題ではなく、神のみ心に従った群れとして今後も存立することができるのかという問題であると見極めたのです。 パウロは、「人間の知恵によってではなく、神の恵みの下に行動してきました。」と明確に述べています。 教会は私たち人間の働きや知恵によってではない、主イエスの働きである。 その都度のご都合で自分勝手に判断し、宣教を推し進めてきたのではない。 神の憐れみ、神の赦しに支えられて、「神から受けた純真と誠実によって、神の恵みの下に行動してきました」と言うのです。 ここでパウロは「良心」という相対的な言葉をもって、「信仰そのもの、神のご真実そのものにかかわること」を忍耐しながら呼びかけるのです。 自己中心的な思いと、神のみ心に従おうとする思いの狭間で、「神の恵みの下に行動してきました。 このことは、良心も証しするところです。」と、マルティン・ルターが語る「神の言葉に縛られている良心」を痛めることなく、偽りなく語るのです。 外に現れ出てくる言葉と行動と、内に秘められている思いとが一致していないのは、今、コリントの教会を席巻している偽教師たちの方である。 正しく導いているようで、パウロ個人を無きものとし、自分たちの思いを果たそうとする巧みに人間の知恵によって生きていく生き方に、パウロは警鐘を鳴らすのです。 そして、「このことは、わたしたちの誇りです。」と言います。 「誇り」とは、その人が何を拠り所として生きているのかを示すものです。 キリスト者が避けなければならない「誇り」は、この世のこと、自分自身のことに対する「誇り」でしょう。 パウロは「誇る者は主を誇れ」と言います。 パウロ自身の「誇り」ではありません。 パウロが、コリントの教会の人たちの「誇り」、コリントの教会の人たちが、パウロの「誇り」だと言うのです。 自らの生きた足跡が実となり、「誇り」となるものが神さまから与えられる。 「終わりの日」には、完全に与えられることになる。 パウロはその照準をもって、この世の現実の今を生き、コリントの教会の人たちとの和解に向かったのです。 もし、この「誇り」を「喜び」と解するなら、パウロとコリントの教会の人たちとの関係の回復が果たされるなら、互いにその回復を導いてくださった神を喜ぶことが生まれ出てくる。 主を誇りとし、神のみ前に恥じない行動と思いをもって生きるキリスト者の誇りと喜びは、互いに反目し合っていたとしても持つことができるのではないでしょうか。
[fblikesend]「生きる望みさえ失った苦難から生まれるもの」 コリント二1章8~11節
コリントの教会の人々の深い悔い改めの後に、パウロは「和解の手紙」を記しています。 自分を裏切った人々も、自分を激しく罵った人々も赦し、同時に、和解へと導いてくださった神さまへの賛美と感謝の思いが「和解の手紙」には滲み出ています。 その手紙の一部分である今朝の聖書箇所に、パウロは「アジア州でわたしたちが被った苦難をぜひ知っていてほしい。 知らずにいてほしくない。」と言います。 使徒言行録19章に記されているエフェソでの騒動のことです。 アルテミス神殿の模型を銀で造り、利益を得ていた銀細工の職人たちが、偶像礼拝を否定するパウロたちの教えに対し激しく迫害したのです。 パウロは自身の実体験を美談として示すのではなく、むしろ、敗者としての実体験を赤裸々に語るのです。 しかし、この体験でこそ、神を頼りにすることになりました。 神がこれほど大きな死の危険からわたしたちを救ってくださったし、これからも救ってくださるにちがいないことが分かりましたと言うのです。 神のもと近くに留まるなら、測り知ることのできない神ご自身を知ることになります。 その神によって与えられる苦難や悲しみや喜びには意味があることを知らされるのです。 福音書では、「唯一のまことの神と、その神がお遣わしになったイエス・キリストを知ること、これが神によって与えられる賜物である。 永遠の命である。」と宣言されているのです。 今まで味わってきた恵みの実体験に支えられてきたパウロの、自身の使命について果たしてこれが神のみ心であるのかという信仰の根幹を揺るがす激しい葛藤であったのでしょう。 アブラハムがその息子イサクを焼き尽くす捧げものとして差し出すようにという神の命令に接したとき、また、すべてのものを奪い取られてしまったヨブが、それでも神さまへの信頼を失わず、友人や家族にまったく理解されなくとも、神のみ心だけを示してほしいと頑強に神に迫ったときのことを思い起こします。 パウロは、信仰者としての絶望を味わったのです。 問題の解決や具体的な助けを求めたのではなく、神のみ心が分からない、神から見放されてしまったのではないかという、信仰者の根本的な深刻な戦い、信仰があるがゆえの苦しみでしょう。 パウロは、これほどの苦しみを味わなければ分からないことがある、見えてこない景色、学べないことがあると分かって、「生きる望みを失った、死の宣告を受けた」と思わされるようなところからでも、「並み外れた偉大な力」によって救い出してくださるお方であることを改めて知って、このことを「知らずにいてほしくない」と赤裸々に語るのです。 私たちは苦難を求める必要はありません。 苦難そのものが問題なのではなく、苦難の中でこそ神から与えられることがあるのです。 私たちが経験したことのないパウロの経験から、パウロが「これほど大きな死の危険からわたしたちを救ってくださったし、これからも救ってくださるにちがいいないと、わたしたちは神に希望をかけています」という信仰を憶え、互いに執り成し合う祈りをささげることが赦されているのです。 私たちは苦難が臨む時、目や耳や心を目の前の苦しみに奪われてしまいます。 外的な変化ではなく、内的な変化、苦しみや悲しみそして喜びをどのように受け止めるのかによって、苦しみや悲しみそして喜びの内容が劇的に変わるのです。 「わたしたちが悩み苦しむとき、それはあなたがたの慰めと救いになります。 また、わたしたちが慰められるとき、それはあなたがたの慰めとなり、あなたがたがわたしたちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。 あなたがたについてわたしたちが抱いている希望は揺るぎません。 なぜなら、あなたがたが苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると、わたしたちは知っているからです。」(6,7)と語るパウロとコリント教会の人々の交わりの在り方のように私たちもかくありたいと願います。
[fblikesend]「表され、知らされ、全うされる愛」 ヨハネの手紙一4章7~21節
コリントの信徒への手紙一13章のパウロの「愛の賛歌」では、いずれ消えてなくなってしまうものではなく、いつまでも残るものとして、この「神の愛」を知ること、味わうことが「最高の道である」と断言しています。 これとは別に、ヨハネが語るもうひとつの「愛の賛歌」がここに記されています。 「愛は神から出るもので、愛する者は皆、神から生まれ、神を知っている。」(7)と言います。 神は愛を持っておられると言うのではなく、愛そのものであると言うのです。 神は愛そのものであるから、私たちもまた「互いに愛し合いましょう」とヨハネは呼びかけるのです。 神との交わりを「遮るもの、隔てるもの」がこの世にある。 聖書はこの「神のもとから離れてしまっている状態」を「罪」と言っていますが、これを取り除くことは神以外にはできないのです。 これを取り除くためには、神が決して相容れることのできない「罪」を正しく裁き、神の怒りをそこで終わらせなければならないと言う「宥めの側面」があります。 神は正しいお方であるがゆえに、この「罪」の状態を赦すことも、相容れることもできない怒りをもって対峙しなければならないお方なのです。 そこから私たちを救い出すためにはもうひとつ、神の赦しという側面、その一切合切を背負わせるために御子であるイエス・キリストを遣わされたという「贖いの側面」があるのです。 この神のご愛と神のご真実という二つの側面が折り重なって起こされた出来事、これがイエス・キリストの十字架の出来事なのです。 「神は、独り子を世にお遣わしになりました。 その方によって、わたしたちが生きるようになるためです。 ここに、神の愛がわたしたちの内に示されました。 わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪を償ういけにえとして、御子をお遣わしになりました。 ここに愛があります。」(9-10)と語っているとおりです。 このイエス・キリストの十字架の出来事から離れた「神の愛」をいくら宣べ伝えたとしても薄っぺらいものとなるでしょう。 神のご愛に裏打ちされた神の厳しい正しい裁きがあるのです。 この神の厳しい裁きに裏打ちされた、憐れみ、恵みとしか言いようのない「神のご愛」がここに示されているのです。 私たちはこの神との交わりが始まりますと、人が神に近づいて行けば行くほど、神をとことん味わうことになります。 なぜなら、神から注がれる聖霊という賜物による働きが、様々な知恵と力、そして出来事を起こしていくのです。 神は愛そのものだと言われる。 それが私たちの内にとどまるなら、神の愛が私たちの内にとどまることが分かるだけでなく、それが動き出し働き出すというのです。 互いに神の愛をもって愛し合う時、その交わりの中に目に見えない神が共におられることが見えてくる、気づくことになる。 「神の愛がわたしたちの内で全うされる」と言うのです。「全うされる」とは、成し遂げられるということです。 私たちを通して、神の愛が完成されると言っている。 これほどの尊い人生がこの世にあるでしょうか。 「神はわたしたちに、御自分の霊を分け与えてくださいました。 御父が御子を世の救い主として遣わされたことを見、またそのことを証ししています。」(13-14)と言います。 注がれた聖霊によって、私たちが神の内にあること、神が私たちと共にあることを確信させる。 目撃を完了した事実を証言すると言うのです。 私たちの信仰は、この目撃証言と復活されたイエスとの出会いの事実に基づいているのです。 この神の愛には流れがあります。 先ず神から私たちへと神の愛は流れてくる。 その愛が今度は、私たちの兄弟姉妹へと流れていく。 私たちが神の愛の内にとどまる限り、その神の愛の流れが全うされていくのを喜んでおられる神を、この地上においても見ることができるのです。 この神の愛の流れの一端を担う者として、この世に私たちは生かされているのです
[fblikesend]「今は見えると言う証し」 ヨハネによる福音書9章18~25節
9章には、「生まれつき目の見えない人の目をイエスが癒す」という出来事が記されています。 生まれつき目の見えない人、奇跡を起こしたイエス、奇跡を周りで目撃した人々、イエスを罪に定めようと企むファリサイ派の人々の姿が織り重ねられています。 イエスは「通りすがりに見かけられた」その人に目を留め、声をかけられた。 肉体的な不幸は罪の結果であるという、当時の因果応報の思想により苦難の原因にしか目が向かない弟子たちに向けて、「神の業が、遣わされたこのわたしを通して現れ出るためである。」と言われ、苦難の目的の方に焦点を当てようとされるのです。 言われただけでなく、「地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。」 そして「池に行って洗いなさい」とまで言われた。 イエスのとったこの行動はすべて、安息日にしてはならない行いです。 この律法に縛られた人々を前にして、救いの出来事をイエスは始められたのです。 ファリサイ派の人々は、「安息日を守らないから、イエスという人物は神のもとから来たものではない。」と、その戒めを破った確証を得るために、執拗に尋問を本人に繰り返すのです。 事実だけを答えるしかできない本人は、次第にイエスとは誰であるのかを考え始め、「あの方は預言者です」と奇跡を呼び起こす者として意識し始めたのです。 盲人の目が開かれることを信じることのできないファリサイ派の人々は、本人の両親を呼び出し「この者は生まれつき目が見えなかったのか」と尋問します。 この時、「イエスをメシアであると公に言い表す者がいれば、会堂から追放する」と既に定められていた。 この社会的な死を意味する恐ろしい規定が両親をして、真実を見ようとしない、目をそらそうとする、判断を避けようとする「見えない者」のようにするのです。 そこで、ファリサイ派の人々は、「安息日に戒めを守らないイエスは、罪ある人間だと知っている」と語りかけ、本人を追い込み迫るのです。 その時の本人の証言が、「あの方が罪人であるかどうか、わたしには分かりません。 ただ一つ知っているのは、目の見えなかったわたしが、今は見えるということです。」というものでした。 本人は社会的に追い込まれても、「今、ここで」自分に起こされた事実だけに立ち続け、「見える」という意味合いに新しい光が差し始め、「イエスとの出会いを味わった者」としての姿に変わりつつあるのです。 自分たちが望む回答を得るために質問を繰り返すファリサイ派の人々に、当の本人は「聞こうともしない、見ようともしない、受け止めようともしない」彼らに、「神は罪人の言うことはお聞きにならない。 神をあがめ、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。」とまで語ったものですから、制定されていた追放規定により会堂から追い出されたのです。 この会堂から追放された本人に、イエスは再び出会ってくださるのです。 「あなたが見ている、話しているのがメシアである」と宣言し、「見えない者は見えるようになり、見える者は見えないようになる」と言われて、全く無関心であったところから、預言者である、神のもとから来られた方である、あなたこそ救い主であると証言できるまでに変えられたのです。 肉体的な目が開かれてから救いの出来事が始まり、問い詰められるにつれてその事実をしっかり見つめ直し、その事実に立ち続けた本人の心の目、霊の目が開かれたのです。 そのイエスとの交わりから引き離そうとする力が働いたとしても、「今は見える」という立場に立ち続けることができた。 私たちが「見て、聞いて、触れることのできる」お方として、主イエスが父なる神を示してくださったのです。 病いが癒されたことが大切なことではなく、目に見える事実として神の働きに出会い、神のみ業が始まったことに気づくことが大切なのです。 主イエスは必ず自ら近寄って、出会ってくださるのです。 「目の見えなかったわたしが今は見える」という信仰へと導いてくださるのです。
[fblikesend]「神の子として生きる喜び」 ヨハネによる福音書10章22~42節
「神殿奉献記念祭」とは、シリアに侵略されエルサレム神殿の中に異教の神が持ち込まれたが、その後シリア軍を打ち破って、異教化されてしまったエルサレム神殿を取り戻したことを記念した国民的祭りで、「宮清めの祭り」とも訳されています。 ユダヤ人指導者たちとの対立が決定的になっていたイエスが、真の礼拝をささげる場となっていないエルサレム神殿を取り戻そうとされた、「宮清め」の働きを果たそうとされたとヨハネによる福音書は語りたかったのでしょう。 「神殿奉献記念祭」の時に、イエスは「神殿の境内でソロモンの回廊を歩いていた」と言います。 「ソロモンの回廊」とは、律法学者たちが常用していた場所であると言いますから、まるで「飛んで火にいる夏の虫」と言ったところでしょう。 エゼキエル書34章には彼らの行状は、「群れを養わず、自分自身を養っている。 弱いものを強めず、病めるものをいやさず、傷ついたものを包んでやらなかった。 追われたものを連れ戻さず、失われたものを探し求めず、かえって力ずくで、苛酷に群れを支配した。」と記されているのです。 彼らはイエスに、「もし、メシアなら、はっきりそう言いなさい。」と迫ります。 イエスは今まで、自分自身のことを「たとえ」を用いて語っていたので、彼らは「その話が何のことか分からなかった」のです。 イエスは、「わたしは言ったが、あなたたちは信じない。 わたしが父の名によって行う業が、わたしについて証ししている。 しかし、あなたたちは信じない。」と反論し、「あなたたちは、わたしの羊ではないからである。」と語るのです。 イエスはこのように決定的に反目する者に対しても、諦めず最後まで「良い羊飼い」のたとえを用いて繰り返し訴えるのです。 私たちはこのイエスの訴えを聞き取らねばなりません。 「わたしの羊」と言うように、イエスの羊として既に知られている。 その事実のうえに、イエスの呼びかけを聞き分ける、従うという事実が加わって、イエスと私たちのつながりが確かなものとなっていく。 このイエスの手の中にあるという事実から、だれもイエスの手から奪い去ることができないと言われるのです。 ついには、「わたしと父とは一つである」と、人間としての一線を越えて語ったものですから彼らの殺意を呼び起こすのです。 彼らは律法に書かれてある(レビ24:15)「神を冒瀆する者はだれでも、その罪を負う。 共同体全体が彼を石で打ち殺す」と定められていることを十分承知のうえで「メシアなのか」とイエスに迫るのです。 彼らの言う「神を冒瀆した」というその「神」とは、自分たちが築き上げてきた宗教的権威や体制のことでしょう。 イエスは詩編82編を引用し、神の言葉を受けた人たちは「神々」と言われているではないか。 神にたとえられるほどの存在が、「ふさわしい務めを果たしていない。」と言い、今何が起きているのか、その現実を注意深く見聞きするようにと言うのです。 イエスは私たちと同じ肉体を担ってくださり、託された神の様々な業を通して映し出された諸々の事実、恵みの世界にある神を目の当たりに見るようにと示し、律法の戒めの中でしか神を見ることのできなかった彼らに言われているのです。 ただ恵みにより、神とイエスとの関係に招き入れられていること、この恵みの先行によって私たちの信仰が歩み始めることを忘れてはなりません。 イエスはその後、エルサレム神殿に戻らず、ヨルダン川の向こう側、ヨハネがバプテスマを授けていたところに行って、そこに滞在されたと言います。 「ヨハネは何のしるしも行わなかったが、彼がこの方について話したことはすべて本当だった」という素朴な民衆の証しが述べられています。 エルサレム神殿の権威から解放されて、素朴に証しし、心からイエスを信じることができたという「救い」がエルサレム神殿の外にもあることを、指導者たちと素朴な民衆の姿を対比して示しています。
[fblikesend]「イエスの声を聞く体験」 ヨハネによる福音書16章25~33節
イエスがこの世を去るにあたり、愛する弟子たちに語られています。 イエスご自身が十字架に架けられる前日、最後の晩餐の席上でのことです。 この直後には、ユダに導かれてイエスを捕らえるために兵士たちがやってくる差し迫った場面です。 イエスは、「しばらくすると、あなたがたはもうわたしを見なくなるが、またしばらくすると、わたしを見るようになる。 あなたがたは悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。 あなたがたは悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。 その喜びをあなたがたから奪い去る者はいない。 あなたがたは喜びに満たされる。」と言われていた。 弟子たちは「これはいったい何のことだろう」と分からないでいた。 イエスと弟子たちとの思いの大きな隔たりには、50日間の産みの苦しみが必要でした。 この直後に訪れるイエスの処刑の出来事、自分たちを守り支えてくださるはずのイエスがこの世の支配に降り、余りに無力な敗北の姿を弟子たちは目の当たりにせざるを得なかったのです。 絶望のうちに家の戸に鍵をかけ閉じこもっていた弟子たちの前に、イエスは復活した事実を幾度となく表し、今までと変わりなく約束通り呼びかけてくださった。 そして、50日後に聖霊が弟子たちそれぞれに注がれて、恐れていたこの世の支配者たちに堂々と語る力を得て、「あなたがたが十字架につけて殺したナザレの人イエスこそ、神から遣わされた方です。 わたしたちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。」と語り始めたと言うのです。 イエスは最後の晩餐の席上で「わたしは父のもとから出て、世に来たが、今、世を去って、父のもとに行く。」と言われた。 父なる神を知るようになるその時、あなたがたはわたしを愛し、わたしが神のもとから出て来たことを信じることができるようになる。 父なる神の温かいご愛に触れることになると、イエスは弟子たちに約束されたのでした。 この約束に弟子たちは、「これによって、あなたが神のもとから来られたと、わたしたちは信じます。」と答えたと言う。 この弟子たちの精いっぱいの信仰告白にイエスは、「今ようやく、信じるようになったのか。」 あなたがたの神の理解には限界があると言う。 私たちの「分かった」と言う理解が、私たちの信仰を生み出していくのではない。 まだ起きていない出来事を前にして、「あなたがたが散らされて自分の家に帰ってしまい、わたしをひとりきりにする時がくる。 いや既に来ている。」と言われる。 愛する弟子たちさえも、イエスを見捨ててイエスのもとを離れてしまう。 これが、私たちの現実、歴史的事実です。 イエス御自身も、私たちと同じ肉体を背負ってくださって、この限界と弱さを担ってくださったのです。 「しかし、わたしはひとりではない。 父が、共にいてくださるからだ。」 この父なる神との交わりなくして、この世の歩みを果たすことができないと言われるのです。 イエスは愛する弟子たちに対し、その信仰の不徹底を叱責されてはおられない。 むしろ、「あなたがたには世で苦難がある」と心配しておられる。 今、私が父なる神と共にあるという確かさによってしか、その限界と弱さを克服することができないように、あなたがたもまたこの私を通して父なる神との交わりに招かれている。 「勇気を出しなさい。 わたしは既に世に勝っている。」と愛する弟子たちに呼びかけておられるのです。 イエスがこの世を去るにあたって、この世の有限や弱さと、神の国の無限や真の強さの間にある、決して混じり合うことのない峻厳なる事実が、私たちに恐れと絶望を引き起こすのかもしれない。 「しかし、勇気を出しなさい。 神ご自身が自ら、神の世界のものとこの世のものが混じり合うことのないことをはっきりと知らせる時が来た。 恐れることはない。 一緒に神ならぬものから解放されて、父なる神のもとに戻って行こうと招いてくださる呼びかけを聴く体験が与えられているのです。
[fblikesend]「赦されている私たち」 ヨハネの手紙一2章1~11節
「徴税人の頭であり金持ちであった」ザアカイはなぜイエスに呼びかけられたのでしょうか。 「徴税人」とは、人々からお金を搾取し私腹を肥やしていた人物で、その元締めですから「罪人の代名詞」でした。 「金持ちが神の国に入るよりも、らくだが針の穴を通る方がまだ易しい」とイエスが言われたように、神から最も遠い存在であったのです。 ザアカイにとってみれば、単なる好奇心からであったかもしれない。 「イエスを見るために走って先回りをして、木に登って待っていた。」 そこにイエスが差しかかると、「木の上を見上げて、ザアカイ、急いで降りて来なさい。 今日はぜひあなたの家に泊まりたい。」と呼びかけられた。 この「泊まりたい」とは、「泊まらなければならない、泊まることになっている」という意味合いです。 知られる筈のない自分の名前を聞いて呼びかけられたことを知り、「急いで木から降りて来て、喜んでイエスを迎えた」と言う。 イエスを通して、父なる神との交わりの回復が「今、ここで」始まった。 このイエスの呼びかけに動き出したザアカイの振る舞いは、単なる好奇心を越えた心の奥底に潜む「求め、願い」であった。 ザアカイの一連の動きはイエスご自身によって起こされ、ザアカイ自身に止まらずザアカイの家にまで及ぶ「福音の到来」です。 ザアカイはこの招きにふさわしい何かを成し遂げたわけでも、招きにふさわしい姿になったからでもない。 ただイエスに言われたとおり、近づいて行ってそのみ言葉を受け入れたのです。 自分の家に招き入れたザアカイは、「主よ、わたしは財産の半分を貧しい人々に施します。」と唐突に話し始めます。 軽いお詫び程度で、なぜ徴税人の職を辞するとまで言えないのだろうかと思わされますが、明らかにザアカイの心に変化がもたらされ、精いっぱいのイエスに対する告白が起こされたのです。 イエスはこの姿を見て、「今日、救いがこの家に訪れた。 わたしは失われたものを探して救うために来たのである。」と言われた。 イエスはザアカイをすでに、「徴税人の頭であること」も、「私腹を肥やしていたこと」も受け入れておられる。 自分の姿を見つめようとしないザアカイを呼び寄せて、ご自身との交わりに招いておられる。 聖書の言う「罪」とは、神の呼びかけに背を向けみ前に進み出ようとしない状態を言うのでしょう。 ヨハネの手紙は、「あなたがたが罪を犯さないようになるため」にこの手紙を書いていると言います。 せっかくイエスを通して結ばれた神との交わりから離れないようにと勧め、「たとえ罪を犯しても、神のもとを離れてしまっても、御父のもとに弁護者、イエス・キリストがおられます。 この方こそ、全世界の罪を贖ういけにえです。」と言うのです。 天の裁きの場で私たち人間の罪の姿が浮き彫りになっても、「いけにえ」として差し出された御子イエスが弁護者として、今もってとりなしの祈りをささげ続けてくださっていると言うのです。 私たちの信仰の出発点は、先ず、自分自身の本当の姿を見つめること、神のもとから離れてしまっていることに気づくことです。 そのために、イエスは呼びかけ出会ってくださるのです。 ザアカイがそうであったように、そのことに気づいたのなら、御子イエスの十字架によってすでに「赦されている、贖われている」ことに気づくことになるのです。 私たちはそれに応えて踏み出し、導かれるままに身を委ねていく。 すると刻々と新しい変化が起こされ、いつしか神のもとにたどり着くまで、恵みの上に更に恵みを受け取っていく。 「神の掟を守るなら、神を知っていることが分かります。 神のみ言葉を守るなら、その人の内に神の愛が実現しています。」と言います。 「神を知る、神の愛が実現する」とは、神との人格的な信頼関係、血の通った温かい交わりで結ばれているということです。 その時こそ、「闇が去って、既にまことの光が輝いている」ことを賛美することになるのです。
[fblikesend]「互いに愛し合う神の子たち」 ヨハネの手紙一3章11~18節
「御子の内にいつもとどまりなさい。 だれにも惑わされないようにしなさい。」と勧告し、依然として「この世」で「罪のうちを歩む者」と、そうしたものに取り囲まれながらも御子なるイエスと共に生きていこうとする「神から生まれた者」を対比し、私たちを縛りづける「この世の罪と死」という力から解放されるようにと、この手紙が強力に勧める言葉が「互いに愛し合うこと」だと言うのです。 「カインのようになってはいけません。」とありますが、これは最初の人間アダムとエバの間に生まれた兄カインと弟アベルの間に起こされた殺人事件です。 土を耕す者となった兄カインは、「土の実りを献げ物として持って来た。」 羊を飼う者となった弟アベルは、「羊の群れの中から肥えた初子をもって来た。」と言います。 二人は神の祝福に対し、祭壇を築き礼拝しようとしたのですが、神は二人のささげる「信仰」を見ておられたのです。 神は弟アベルとその献げ物に目を留められたが、兄カインとその献げ物に目を留められなかったと言う。 少なくとも、神の恵みに対する感謝と賛美の思いは二人にはあったでしょう。 しかし、自分の献げ物が神に目を留められなかった兄カインは、「激しく怒って顔を伏せた」と言います。 神は、「どうして怒るのか。 どうして顔を伏せるのか。 お前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。 お前が怒りを抑えることができないのなら、戸口で待っているこの世の力である罪に支配されるようになる。」と言われたのです。 神は献げ物ではなく、カインの心の中に隠されていた「怒りの根源」を見抜いておられたのです。 兄カインは怒りと嫉妬にかられて、弟アベルに向け襲ってしまったのです。 この世に生きる限り、互いにぶつかり合うこともしばしばあるでしょう。 イエスは、「あなたが祭壇に供え物を献げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰って来て、供え物を献げなさい。」(マタイ5:23-24)と言われて、目に見える兄弟との交わりが壊れてしまっている状態で、目に見えない神との交わりを果たして持てるのだろうかと迫ります。 神はご自身の愛を、御子であるイエス・キリストを通して注いでくださって、私たちの状態如何に関わらず先ず神の子として受け入れてくださったのです。 その救いの恵み、注がれたご愛に満たされて、その神からの賜物をもって与えられた「隣り人、兄弟姉妹」に注ぎなさいと招いておられるのです。 この手紙は、今や、「わたしたちは、自分が死から命へ移ったことを知っています。」 この新しい命は、イエスが語られたこと、果たされたことを、この私のためであると信じ、教えられた福音を受け入れた瞬間から始まり、芽生えている。 「イエスは、わたしたちのために、命を捨ててくださいました。 そのことによって、わたしたちは愛を知りました。」と告白するのです。 私たちは、御子なるイエス・キリストを通して、神との出会いと交わりを体験しなければ、神のご愛を深く味わうことができないのです。 神のもとからしか注がれない驚くべきご愛に、その出会いと交わりにより気づかされるのです。 注がれた恵みとご愛は、私たちが受け取るだけでなく身近な「隣り人、兄弟姉妹」に分かち合うためのものです。 「この世」は様々なものを駆使して、私たちを自分のことしか考えられないように縛ります。 神はそのような私たちを裁くためではなく、救い出すために神のご愛の前に立たせてくださるのです。 神のご愛に満たされた神の子たちは、その「隣り人」をも愛する生き方が備えられ、やがて整えられ、神の子どもにふさわしく成長させてくださるのです。 「この世」とは、かつて私たちが住んでいたところ、今や、つくり変えられて「死から命へと移ったことを知った者」として遣わされているところなのです。
[fblikesend]『囲いの内と外』 ヨハネによる福音書10章7~18節
イエスは、「わたしは羊の門である。」と言い、この前段落では「羊の囲いに入るのに、門を通らないでほかの所を乗り越えて来る者は、盗人であり、強盗である。 門から入る者が羊飼いである。」と言います。 エゼキエル書34章には、「牧者たちは、群れを養わず、自分自身を養っている。 見よ、わたしは自ら自分の群れを捜し出し、彼らの世話をする。 すべての場所から救い出す。 連れ出し、集めて、導く。 養い、憩わせる。 追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。 わたしは彼らのために一人の牧者を起こし、彼らを牧させる。」と言われ、ダビデのような羊飼い、メシアが現れると預言されていたのです。 イエスがここで「羊の囲い」、「羊飼い」、「羊の門」のたとえを用いて、ユダヤ教の支配者たちに向けて、「神の民を養い、育む務めを主なる神から託されているのに、自分たちを養うことだけに専念し、むしろ神の民を支配し苦しめている。」と語られているのに、彼らは自分たちのことが語られているとは気づかなかったのです。 イエスは、ユダヤ人たちが語る「良い羊飼い」と「悪い羊飼い」という次元を超えて、これから起こされる十字架の出来事をたとえを用いて権威をもって語り進めます。 「わたしが来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。 わたしは良い羊飼いである。 良い羊飼いは羊のために命を捨てる。 わたしは自分の羊を知っており、羊もわたしを知っている。 それは、父がわたしを知っておられ、わたしが父を知っているのと同じである。」とまで言われたのでした。 「父がわたしを知っておられ、わたしが父を知っているのと同じである。」と言う意味は、「人格的な結びつきがある、交わりがある」ということです。 父なる神と御子なるイエスとの関係、ご自身と神の民との関係を、羊飼いと羊の関係にたとえておられるのです。 ご自身を「見失った一匹の羊を探し回る真の羊飼い」だと言うのです。 そして、羊飼いのいないイスラエルの民をご覧になって、「飼い主のいない羊のような有様」であると深く憐れまれたのです。 イエスはご自身の大切な務め、父なる神によって託された務め、十字架の苦難と死、そこから解放されて新しい命へとつくり変えられる道、「復活の道」を切り開くことになる、果たすことになる。 「わたしは命を、再び受けるために、捨てる。 それゆえ、父はわたしを愛してくださる。 だれもわたしから命を奪い取ることはできない。 わたしは自分でそれを捨てる。 わたしは命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。 これは、わたしが父から受けた掟である。」と「羊の囲い、羊飼い、羊の門」のたとえを用いて語られたのでした。 イエスは、「わたしには、この囲いに入っていない他の羊もいる。 その羊をも導かなければならない。 その羊もわたしの声を聞き分ける。」と付け加えるのです。 イエスはこの世においては様々な囲いがあることを承知のうえで、「こうして、羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。」と断言されるのです。 イエスを通して注がれる神のご愛は、私たちが勝手に定める「囲い」などによって限定することなどできないでしょう。 当時ですら、すでにローマ兵士の中にも、ファリサイ派の人々の中にも、「囲い」を越えてイエスのみ言葉を聞き分ける者がいたのです。 私たちはこの世において、異質なものに囲まれながら、それでも「神の民」として生きていくのです。 教会の群れは、神によって呼びかけられ集められた者の群れです。 私たちはその「囲い」の外に身を置いて、生活と人生を共に味わいながら、それでも神の国に籍をもつ者として証ししていく務めが恵みとして与えられているのです。 「終わりの日」には、イエスに似たものとなると約束されています。 小さな存在ですが、そこが神の民の群れの源となる、何もなかったところに湧く祝福の源になるのです。
[fblikesend]「み言葉に従った旅立ち」 創世記12章1~4節
神さまは、『あなたは生まれ故郷 父の家を離れて わたしが示す地に行きなさい。 わたしはあなたを大いなる国民にし あなたを祝福し、あなたの名を高める 祝福の源となるように。』と言い、アブラハムは「この主の言葉に従って旅立った。」と言います。 神さまの命令は、アブラハムの思いのままではなく、神が遣わされるところに行けということでした。 この世のものに執着せず故郷を捨て、ただ神に従って歩むということでした。 神さまの約束だけを頼りに神と共に旅立ち、新しい一歩を踏み出したのでした。 アブラハムは、神のみ心が告げられる喜びを知った。 それに応えていこうとする信仰が起こされる恵みを受け取った。 そのために捨てる苦しみや失われる悲しみも、新しく変えられる喜びとして受け取ったのです。 この旅立ちによって、アブラハムはやっとの思いで手にすることのできた約束の息子イサクを神さまにささげるまでに信仰が与えられた。 自身の心の確かさに依り頼む信仰から、神さまの約束の確かさに依り頼む信仰に変えられていったのでした。 自分の力や考えで進めていくのではなく、父なる神に聴き、祈り、神に与えられたものを受け止めていく新しい道に踏み出したのです。 しかし、途中で信仰に挫折もし、食糧を目指してエジプトにまで足を延ばしてしまい、人を恐れ、人間の知恵をもって動き失敗もしています。 そうであるにもかかわらず、神さまの約束は果たされていくのです。 アブラハムは妻のサライと甥のロト、蓄えた財産すべて携えて、途中で加わった人々と共に約束の地に入りました。 このアブラハムと共に出発した民によって、信仰の民がつくり出され、祝福の源となっていったのです。 それは、神さまの選びという働きから始まり、備えられていったものでした。 互いに分かち合い、神さまの民としてひとつとされ、恵みにあずかった者が祝福の源となり、新しい神の民がつくり上げられたのです。 イエスもまた、神さまに祈り思いを受け止め、愛する弟子たちを選び、送り出し、信仰の民をつくり出されたのでした。 イエスは使徒を選ぶために、山に行き、徹夜の祈りをされています。 神さまの子どもであるにもかかわらず、私たちと同じように祈らなければ父なる神のみ心を知ることができない存在となってくださったのです。 このイエスの祈りによって選ばれた使徒たちもまた、神さまの呼びかけによって選ばれ、新たな信仰の旅が始まったのです。 選ばれた使徒たちがイエスのみ言葉によって遣わされていくところに、神さまの民が起こされていく。 祝福の源がつくり上げられる。 その土台は、神のみ言葉とみ心そのものであるイエス・キリストです。 それに応える礼拝が起こされるところに、信仰の民がつくり上げられていったのです。 私たちはいろいろな出来事に出会い、右往左往しながらおのれの弱さや傲慢さや喜びや悲しみを通して神さまに生かされていることを知るのです。 旧約聖書の冒頭に、「初めに天地を創造された。」 そして、第七の日に神さまは創造の働きを終えて「極めてよかった」と、その完成を喜ばれ安息なさいました。 その安息の中に私たちが憩うことが赦され約束されているのです。 私たちはこの神さまの安息日に身を委ねるようにと招かれているのです。 私たちの生活は、この神さまの安息の礼拝から始ります。 神さまの選びによって、神さまの祝福に招いてくださっているのです。 礼拝への出席は、この世に縛られることなく神さまのみ前に進み出ることです。 そこから遣わされて生活の中で神さまに用いられていく、そのための旅なのではないでしょうか。 神さまが遣わされたところに行きたい。 アブラハムが旅に出発したのも、人となったイエスの祈りによって呼びかけられた使徒たちが遣わされたのも、神さまの呼びかけに応えることから始まっています。 神さまによって与えられる信仰の旅を、今ここから始めたいと願っています。
[fblikesend]« Older Entries Newer Entries »