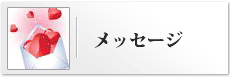「ダビデの賛歌」 詩編23編1~6節
人一倍激しくその生涯を濃厚に生きたダビデは、多くの詩を書いて自分の生涯を振り返って主を賛美しています。 この詩篇23編でもその前半部分で、「主はわたしの本当の羊飼いであった。」と振り返ります。 「不安と戸惑いの中にあったこのわたしを、主は青草の原に休ませてくれた。」 「憩いの水のほとりにまで導いてくださって、わたしの魂を生き返らせてくださった。 だから、これから死を迎えようとしているこのわたしには、何も欠けることがなかった。 何も困ることはなかった。」と賛美します。 ひとりの羊飼いに過ぎなかったダビデは、イスラエルの王にまで駆け上がった人物です。 その地位にまで上り詰めるにあたっては、自分の才能、体力、経験、知恵をフルに用いてきたことでしょう。 あるいは、人からの名声や賞賛や地位もまた活用したことでしょう。 長い間そのようなものを振り回し、あるいは振り回されてきた。 しかし、その生涯を終えるにあたってはそうではなかった。 最後にダビデは「主がわたしの羊飼いであった。 最後までわたしを見届け、導いてくださった。 たとえ、死の陰の谷を通されるような災いのときにも、わたしは不思議と恐れることはなかった。 それは、主がこのわたしと共にいてくださったからだ。 主の羊飼いとしての鞭と杖がわたしを力づけてくださった。」と、その生涯を振り返って賛美しているのです。 ダビデにとって、主の鞭や主の杖とは果たして何であったのでしょうか。 羊飼いとして自分の生涯をコントロールしていこうとしたダビデこそが、様々な災いとも思われる出来事を通されて思い悩み、うろたえるこの自分こそが迷える羊であった。 歩むべき道を取り間違えた時も、このわたしを取り戻してくださった。 自ら踏み込んでしまって「死の陰の谷」を歩んだときでさえ、災いを恐れとは感じさせず、あなたの鞭と杖によってむしろその道を潜り抜けるまでわたしは力づけられた。 「わたしを苦しめる者を前にしても、あなたはわたしに食卓を整えてくださった。 わたしに油を注いでくださった。 わたしの杯に、恵みを溢れさせてくださった。」と、感謝のうちにその生涯を振り返っているのです。 そして、「その導きに身を委ね、歩み通したその後には、わたしは主の家にたどり着く。 そこにとこしえに留まることが赦されている。」と、最後まで主に望みをおいて希望をもって賛美しているのです。
自分がどのようにその生涯を歩んだのかではなく、主がわたしの生涯にどのようになされ、わたしとともに歩んでくださったのか、また歩もうとしてくださったのかに目を注いでいるのです。 そして、その主の働きにこそ、心から期待し、希望を抱いていると思わされるのです。 「死の陰の谷を通ったときも あなたはわたしと共にいてくださり、わたしを力づけてくださった。」と叫んでいます。 他の詩篇の箇所にも、「あなたは多くの災いと苦しみを、わたしに思い知らせましたが、再び命を得させてくれるでしょう。 地の深い淵から 再び引き上げてくださるでしょう。」(詩編71:20)という叫びもあります。 また、「深い淵の底から 主よ、あなたを呼びます。 わたしは主に望みをおき、わたしの魂は望みをおき、みことばを待ち望みます。 わたしの魂は主を待ち望みます。」(詩編130:1,5,6)と叫びます。 自分を支えるものが何もない、一切頼るべきものがない。 主の前に立ちようがない、立つ資格もない。 主のみ言葉に耳を傾けることも、悟ることも、それにふさわしい行いすらもできない。 立ち向かう信仰すらもっていない。 そのようなところからでも、「わたしは、あなたを呼び求めます。 再び命を得させて、再び引き上げてくださるでしょう。 わたしは主に望みをおきます。 わたしを追いかけてくださる恵みと慈しみにすがります。」と叫んでいるのです。