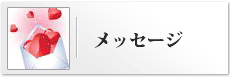「神の畑、神の建物」 コリントの信徒への手紙一3章1~9節
「神に用いられる器」とは、神に必要とされている人ということでしょう。 私たちは、主イエスに出会って、主イエスに結ばせていただいた者です。 「キリストのからだ」であるからこそ、果たすべき役割は大なり小なりそれぞれにふさわしくあるはずです。 与えられた役割が果たされなければ「キリストのからだ」全体、キリストを通しての神のみ心が果たし得ないことになるのです。 「神に用いられる」とは、自らが「キリストのからだ」の一部であることに気づかされ、自分に備えられた恵みを受け取って従順に用いて、感謝してその御心に委ねて従っていくということではないでしょうか。 パウロがコリントの教会の人々に、「兄弟たち、キリストとの関係においては乳飲み子である人々」と呼びかけています。 パウロは2年足らずでコリントの教会を立ち上げ、その後を弟子のアポロに託して、エフェソに移ったのです。 アポロは雄弁で、聖書に精通し、説教で多くの人々を魅了し、外見も立派であったと言います。 一方、パウロは朴訥で、説教は分かりづらく、「手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で、話もつまらない」と表現されています。 アポロに惹きつけられた人々は、アポロを指導者として新しい歩みを望んだ。 一方、創設者であるパウロから直々に教えを受け導かれた人々は、新しいアポロの動きに反発をしたと言います。 これが、コリントの教会内部の争いです。 パウロは、「お互いの間にねたみや争いが絶えない以上、あなたがたは肉の人であり、ただの人として歩んでいる。」と言います。 パウロの言う「肉の人、ただの人」とは、キリストの十字架の贖いのみ業に立つことなく、いつまで経っても自分という存在に囚われている人のことです。 一方、「霊の人」とは、キリストの十字架に贖われ、自分という存在が神のものとなっている人、自らの拠り所をキリストの十字架の贖いに置いて、その恵みに生かされている人のことです。 パウロは終始、「十字架に架けられたキリスト」(2:2)だけを宣べ伝えてきたと言います。 神のみ言葉の方に違いがあるのではなく、聴く側の状態によって「乳を飲むようなもの」になったり、「固い食物を噛み砕くようなもの」になる。 この十字架の救いを受け止めるには、どうしても霊の働きが必要になるのです。 「わたしたちはキリストのからだであり、アポロも、パウロも、あなたがたを信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えた者です。 パウロは植え、アポロは水を注いだ。 しかし、成長してくださったのは、神なのです。」 パウロは、私たちは「神の畑」であると言います。 蒔かれる種はみ言葉です。 それが実り、育っていく畑が私たちだと言うのです。 実を結んでいくのは、蒔かれた神のみ言葉です。 あくまでも大切なものは神の働きです。 私たちが用いられて、神の恵みの業が映し出されることなのです。 もうひとつパウロは、私たちが「神の建物」だと言います。 私たちは「キリストのからだ」の一部分です。 一人一人が立派になり、建物全体が成長するのではない。 一つ一つの結びつき、交わりを壊してはならないのです。 主によって集められた群れ全体の益を目指しているのです。 この全体を築き上げるのは、神ご自身です。 私たちは神が蒔いてくださる畑、神が築いてくださっている建物に組み込まれた部分です。 十字架を背負ってくださったキリストを指し示すこと、蒔かれた福音の種を受け止め聴き続けること、自分を顧みるのではなく十字架の上で罪を贖ってくださっているキリストを仰ぎ見ることです。 これらのことを邪魔するのが「自我」、「肉の思い」です。 自分自身から解放されること、神のみ前に進み出て砕いていただくことです。 神は用いられるのは、この「砕かれた魂」(詩編51:19)なのです。 「わたしの神」から「神のためのわたし」へと変えて頂きましょう。
[fblikesend]「置かれたところで常に励みなさい」 コリントの信徒への手紙一15章50~58節
パウロは、「肉と血は神の国を受け継ぐことはできません。 朽ちる者が朽ちないものを受け継ぐことはできません。」と言います。 「肉と血」とは、私たちの「からだ」のことを言うのでしょう。 これをもってしては、神の国を受け継ぐことができないとパウロは言い、そこで「わたしはあなたがたに神秘を告げます。」と語るのです。 この「神秘」と訳されているギリシャ語は「ミステリオン」という言葉で「奥義」とも訳され、旧約聖書の時代には明らかにされなかった事柄、神の御心が、今ここに明らかにされ成し遂げられてきた。 そして十字架に死んで、よみがえらされ、天に上られたイエスが再び現れ出る時、世の終わりがある。 コリントの信徒の人々が心の底では疑問に思っていた「死者はどんなふうに復活するのか、どんなからだになるのか。」ということに、パウロは真正面から応えていこうとするのです。 パウロは、「蒔かれるときは朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、蒔かれるときは卑しいものでも、輝かしいものに復活し、蒔かれるときには弱いものでも、力強いものに復活するのです。 つまり、自然の命の体が蒔かれて、霊の体が復活するのです。」(15:42-44)と言い、これが「神秘」だと言うのです。 「もし、イエスを死者の中から復活させた方の霊が、あなたがたの内に宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなたがたの内に宿っているその霊によって、あなたがたの死ぬはずの体をも活かしてくださるだろう。」(ローマ8:11)とパウロが語っているとおりです。 この世にあっても霊を与えられることによって、「よみがえり、復活」はすでに始まっている。 この私たちの「肉と血」がそのまま蘇生することが復活することではない。 そのような人間が、神の国を受け継ぐこと自体が「神秘」だと言うのです。 しかし、この起こされた「よみがえり、復活」は、「終わりの日」において完成されると言います。 パウロは、「からだ」を取り替えるのではなく、「古いからだの上から新しいからだを着る」と表現します。 神が良きものとして創造したものがいつしか罪の狡猾な働きに縛られ、本来意図されたものとは程遠いものとなった。 それを主イエスの十字架と復活によって取り戻すということ、主イエスという贖いによって買い戻すということ、「古いからだの上から新しいからだを着る」ということです。 これは「神の国を受け継ぐため」なのです。 今、倒されるべきは、「死」そのものです。 人間が「死」に脅かされているのは、「死」のとげである「罪」に縛られているからです。 「死」が滅ぼされれば、朽ちる「からだ」から劇的に変化することになる。 それは神の国を引き継ぐため、いつまでも主イエスと共にいるためなのです。 朽ちるべきものの上に朽ちないものを着せられない限り、今とは異なる新しいからだにはなれない。 しかし、神の恵みの業がすでに起こされている。 私たちはこの復活の約束を受けて、希望が果たされることを待ち望んでいるのです。 58節に、「わたしの愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい。 主イエス・キリストに結ばれているならば自分たちの苦労が決して無駄になることはありません。」と断言するのです。 イエスは、聖霊が下されたことで、この苦しむことのできる「からだ」を担ってくださったのです。 敵意を向ける人たちの救いのため、その「からだ」をもって生きてくださったのです。 「肉と血」は苦しみを避けようとし、死を恐れて見ないよう、考えないようとします。 「からだ」は、聖霊という神の約束の賜物が注がれることによって苦しみを背負ってでも、悲しみを引き受けてでも、生きることができるようになるのです。 私たちの今味わっている苦しみや悲しみや喜び、思い煩いや期待こそ、私たちの中に聖霊が宿っている証しなのではないでしょうか。
[fblikesend]「神の前と人の前」 コリントの信徒への手紙二5章11~17節
パウロは、「内面ではなく、外面を誇っている人々に応じられるように、わたしたちのことを誇る機会をあなたがたに提供している。」と言います。 「外面を誇っている人々」に対して、「内面を誇っているわたしたち」のもとに呼び戻そうとパウロはするのです。 「神の並外れて偉大な力、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光、このような宝物を土の器に納めている。」(4:6-7)と言います。 その「宝」の中味を説明や教えや解釈によってではなく、コリントの教会の人々に対するパウロ自身の在り方、生き方によって、もっと突き詰めれば、そのパウロを突き動かしているキリストのご愛について語るのです。 最初に、「主に対する畏れに生きること」だと言います。 この「畏れ」とは、恐れおののくことではありません。 旧約聖書の時代では、「神を畏れる」ことは信仰の中心、知恵の初めでした。 パウロは、「わたしたちは、神にはありのままに知られています。」と言い、私たちを熟知しておられる神のみ前に立つこと。 その神が遣わした主イエスがすべて引き受け、背負ってくださった神の裁き、主イエスの十字架の前に立つこと。 そこまでしてくださった神の恵みのみ前に立ち味わうこと。 この「キリストに対する畏れをもって、互いに仕え合いなさい。」(エフェソ:21) パウロはかつての自分自身の姿を思い浮かべながら、この神への畏れを失った者が、罪と死に縛られている存在であると言うのです。 更に、「外面を誇っている人々に応じられるように」と「内面に生きる」ことを求めます。 私たちはどうしても外面的なものに左右されます。 主イエスは、「ファリサイ派の人の祈り」と「徴税人の祈り」を示して、神の目に留まったのは「徴税人の祈り」だと言います。 「ファリサイ派の人」とは、社会的に申し分のない立派な人、自分は正しいと豪語し他人を見下している人のことでしょう。 「徴税人」とは、内面までもありのまま曝け出して、「神の前に立つ人」のことでしょう。 真の誇りを偽りの誇りに替えて、心の中に宿すように。 「土の器」を誇るのではなく、土の器に納められた「宝」を誇るように。 その「宝」を自分のためではなく、「土の器」を通して神の民をつくり上げるため、キリストのからだを築くために用いるようにと言うのです。 人々も、愛する弟子たちも、「肉に従ってキリストを知ろう」とし、目に見える結果に失望し離散したのです。 パウロも同じでしたが、「サウル、サウル、なぜ、わたしを迫害するのか」という、目に見えるところによれば処刑されたはずのイエスが復活して生きて呼びかけている。 この声を聴いたパウロは地面に倒れ、目が見えなくなって、キリスト教徒のアナニアに助けられるのです。 コリントの教会の人々に対し説明することのできないこのパウロの体験を、「キリストの愛がわたしたちを駆り立てているから」だと言い、「わたしはありのままに知られたいと思います。」と、自分自身の生き方、在り方によって、復活の主イエスと共に知られたい、この「キリストの愛から、だれがわたしたちを引き離すことができましょう。」と、キリストのために生きる、愛する人のために生きる、もっと多くの人のために生きる、そして神から「宝」を授けられた自分自身のためにも生かされるよう、この一筋の道を歩み通す為にも人と神とに仕えていくことを勧めるのです。 「キリストと結ばれる人はだれでも、新しく創造された者」、キリストを通して注がれてくる「新しい命」を受け取って味わっている人である。 滅びに向かっていた人が滅びに向かっている人に呼びかけ、それぞれの人に合わせて復活の主と共に神のもとへ帰るようにと促す人に変えられていくのです。 「古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。」のです。 神とキリストとの関係がまったく変えられる時、この地上の生活を共に送っていく人との関係もまた、必ず根底から変えられていくのです。
[fblikesend]「主のもとへ帰るという礼拝の姿」 フィリピの信徒への手紙3章17節~4章1節
「兄弟たち、皆一緒にわたしに倣う者となりなさい。」とパウロは言います。 なぜそのようなことを語らなければならないかと言いますと、「キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多い」からだと言うのです。 本来フィリピの教会の人たちに向けての手紙であるはずです。 主イエスの十字架を信じていない人たちに対してではなく、実際の信仰の生活において、主イエスの十字架に支えられて生かされているかどうか。 主イエスを通して表された神の恵みと赦しを受け取ることなく、自分たちにはかかわりのないこととする者が多いと涙ながらにパウロは語るのです。 このパウロの言葉は、自分自身を誇っているのではありません。 主イエスによって与えられた自分の中にある恵みを、同じように宿すことを願うパウロの祈りです。 パウロが指し示しているのは、パウロ自身のことでも、人間の模範の姿でもない。 「わたしがキリストに倣う者であるように、あなたがたもこのわたしに倣う者となりなさい」と、パウロの中に宿っている主イエスご自身を指し示すのです。 十字架によって生かされる、神の恵みのみによって生かされるという恵みから離れてしまって、自分の力や努力、自分の理解や行いを少しでも混ぜて十字架の救いの恵みを薄めていく。 神の力や知恵は、人間の力や知恵をはるかに凌ぐ。 「万物を支配下に置くことさえできる力によって、わたしたちの卑しい体を、御自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださる。」と言うのです。 私たちは自分を誇っている限り、どうしても十字架がその人の躓きとなり、必要としなくなる。 しかし、十字架に示された真の神の恵みとご愛を受け入れるためには、この十字架を受け入れる必要があるのです。 十字架には、神の裁きと共に、神のご愛が凝縮されているのです。 「神によってあなたがたはキリスト・イエスに結ばれ、このキリストは、わたしたちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。」(コリント一1:31)と語っているとおりです。 パウロは「彼らの行き着くところは滅びです。」とまで言います。 十字架による救いがないとするなら、他に救いの道はない。 「人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリスト・イエスによる贖いの業を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。」と言うのです。 私たちは残念ながら、最後の詰まるところのことではなく、今どうなるのかということだけに終始してしまう。 パウロはその「行き着くところ」に、フィリピの教会の人たちの目を向けさせるのです。 「彼らは人間の欲望とでも言うべき腹を神とし、恥ずべきもの、神ならぬものを誇りとし、この世のことしか考えていません。」 だから、神との正しい関係を取り戻すこと、神のみ前での生活を最後まで続け通すことを勧めるのです。 「わたしたちの本国は天にあります。」と、「あなたがたはキリストと共に復活させられた」という違いがあると語るのです。 自分を、あるいは自分の造り上げたものを愛してしまっていては、神を知ることはいつまで経ってもできない。 主イエスとの交わりを回復していただき、主イエスと共にある人々との交わりに加えていただかなければ分からないのです。 実際の信仰生活において、パウロは「主イエスが救い主として来られるのを待っています。」 主ご自身が救いの完成として神の恵みに満たされて生活を送れるよう自ら来られる。 その結果、「わたしたちの卑しい体を、御自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださる。」と言います。 やがて朽ち行く人間に、朽ちない生活ができる道を与えてくださった。 このことを、「わたしが愛し、慕っている兄弟たち、わたしの喜びであり、冠である愛する人たち」と呼びかけ、「主によってしっかりと立ちなさい。」と、キリストと共に、キリストによって生かされなさいとパウロは、この世と一線を画した「礼拝の姿」を求めているのではないでしょうか。
[fblikesend]「満たされた油の壺」 列王記下4章1~7節
聖書箇所の預言者エリシャが行った奇跡は、マタイ福音書25章に記されている主イエスの語られた「10人のおとめのたとえ」の中に示された「油」と「壺」を思い起こします。 エリシャの行った奇跡の数々は、主イエスがなされた奇跡によって更に鮮明に、神のみ心を鋭く私たちに語りかけてくるのです。 預言者エリシャは、主なる神のみ言葉でなすべきことを知り、み言葉どおりに働いたがゆえにこの世で奇跡と思われるような神のみ業が示されたのです。 その奇跡が、何百年後にこの世に遣わされてきた主イエスによって、更に神のみ心が深められていった。 神の霊なるみ言葉と賜物を働かせるならば、今まで気づきもしなかった神のみ業を共に味わうことができると語りかけてくるように感じるのです。 主イエスの光によって、神のみ言葉とみ業を私たちははっきりと受け取ることができるようになるのです。 「預言者仲間の妻の一人」が、エリシャに助けを求めて叫んでいます。 「わたしの夫は、死んでしまいました。 あなたの僕でした。 主なる神を畏れ敬う人でした。」と言います。 その夫は、借金を残して死んだのでしょう。 預言者として仕えた夫の死による家族の窮乏の切実な訴えです。 しかし、妻は社会に向けて訴えるのではなく、預言者エリシャのもとにきて、神の憐れみと恵みに期待して神のみ言葉に聴こうとするのです。 彼女に対しエリシャは、「何をしてあげられるだろうか。 あなたの家に何があるのか言いなさい。」と尋ねるのです。 「油の壺一つのほか、家には何もありません。」という彼女の答えは諦めが漂っています。 エリシャは、今すでに神が彼女に与えておられる恵みの賜物に目を向けさせるのです。 そして、「外に行って近所の人々皆から器を借りて来なさい。 空の器をできるだけたくさん借りて来なさい。」と、 彼女と交わりのある者、その手元にあるものにも目を向けさせるのです。 そして、「家に帰ったら、戸を閉めて子供たちと一緒に閉じこもり、その器のすべてに油を注ぎなさい。 いっぱいになったものは脇に置くのです。」という不思議な命令を彼女に告げるのでした。 マタイによる福音書25章に出てくる主イエスの「10人のおとめのたとえ」では、「油」とは主なる神から注がれる賜物、神によって注がれるみ言葉と恵みでした。 「壺」とは、それらを受け入れ、蓄えるための器、私たちの祈りであり、信仰であり、礼拝する姿でした。 このたとえは、主イエスの十字架の直前に語られた「たとえ」です。 「その日、その時」は突然訪れる。 「目を覚ましていなさい。 油を受け取る用意をして待ちなさい、 油を入れる壺の中を空っぽにして、注がれるものを受け取る準備をして待ちなさい。」と言われているのです。 この世の煩いや、自分の築き上げたもの、自分が誇りとするものがあれば、主なる神からその時に必要な新しい賜物が入ってこないでしょう。 自分に都合のよいものにしか耳に入らないでしょう。 「戸の閉められた家」だけに「油」は注がれたのです。 一つずつの「壺」に今与えられている油を注ぎ始め、いっぱいになればすぐ脇に置いて目もくれず注ぎ続けた。 どれもこれも不思議といっぱいになった。 驚いた彼女は「もっと器を、持っておいで」と子どもに言ったけれども、「器はもうない」と子どもが答えたとたん、「油は止まった」と言うのです。 他の家の話ではない、彼女の家の中に今、その時に必要な油が注がれる恵みが訪れたのです。 信仰と祈りの応答のあるところに、集中的に行われた場所と働きのもとに救いと恵みが起こされたのです。 主なる神が注がれる「油」は無尽蔵です。 どれだけ自らの「壺」を空っぽにして受け取る備えができているのかどうかです。 小さな存在を用いて、大きな憐れみと恵みの業を果たしてくださる主なる神に期待することです。 神さまからの恵みは互いに分かち合うもので、そのための「油」、「壺」です。
[fblikesend]「生ける神の神殿、わたしの軛」 コリントの信徒への手紙二6章11~16節
パウロはキリストの福音を宣べ伝える務めを書き綴り、その締めくくりとして「神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。」と語るのです。 パウロほど、福音を宣べ伝える恵みを味わった人はいないし、福音を宣べ伝えるがゆえに苦痛極まりない惨めさを味わった人はいないのではないでしょうか。 その体験を、「苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓」といった言葉で表現しています。 パウロも、自身の愛と労苦によって生まれたコリントの教会の人々から言われなき非難、中傷を浴び、傷つきもしていたのです。 筆舌に尽くしがたい出来事を経て、その関係の修復にあたり「神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。」と呼びかけるのです。 パウロは、自分自身の生き様を通して注がれた神さまの恵みを最終ゴールとしていません。 その結果が重要ではなく、その過程において味わった主イエスとの出会いと交わり、主イエスご自身が心の内に宿り引き起こされた変化こそ、神さまの恵み、祝福だと言うのです。 私たちに起こる出来事が、その受け取り方によって「幸い」にもなるし、「災い」にもなるということです。 栄誉を受けるときも、辱めを受けるときも、悪評を浴びるときも、好評を博するときにも、真理の言葉と神の力によって、義の武器を左右の手にもって、自身の大いなる忍耐をもって主イエスによって与えられた務めを果たしてきたと、ありのままの姿でその弱さも含めてさらけ出して主イエスの恵みを証しするのです。 パウロ自身も攻撃を受け、傷つけられ、自己の弁明もしたくなるでしょう。 しかし、パウロは「コリントの人たち」となおも諦めずに呼びかけ、「あなたがたに率直に語り、心を広く開きました。」と言うのです。 かつての自分と同じコリントの教会の人々の姿を受け入れ、自分に注がれた同じものが芽生え、呼び起こされるようにと祈るのです。 自分自身と同じように、コリントの教会の人たちの贖いのためにも主イエスは死んでくださったはずであると、願いを込めて「子供たちに語るように、率直に語り、心を開く」のでした。 二つ目の勧告としてパウロは、「信仰のない人々と一緒に不釣り合いな軛につながれてはなりません。」と言います。 「軛」とは、牛やろばなどの首につける横木のことです。 性質の異なる動物を一緒に組み合わせて「軛」に付けると、うまく耕すことができません。 当時の「コリント人」とは、「みだらな人」というレッテルまで張られていた道徳的にも、宗教的にも退廃していた町にパウロは足を踏み入れ、キリストの福音を宣べ伝え、ヨーロッパの有力な教会の礎を築いたのです。 この勧告は、この世との関係を一切断ち切って、この世との分離を促しているのではありません。 キリスト者とは、イエス・キリストを救い主と受け入れ、信じて生かされていく者でしょう。 イエス・キリストを知らず、受け入れず、神のもとから離れてしまっているこの世において、その証し人となる務めを与えられた者です。 むしろ、誤りだらけの、闇の真っ只中と言わざるを得ないこの世においてこそ、しっかりと証し人として生きるべきです。 神によって用いられる存在として生かされるべきです。 主イエスは「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。 休ませてあげよう。 わたしの軛を負い、わたしに学びなさい。 そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。 わたしの軛は負いやすく、わたしの荷は軽いからである。」(マタイ11:28)と言われているのです。 「正義と不法、光と闇、信仰と不信仰とは、何のつながりがありますか。」と迫ります。 最後に「神の神殿と偶像」を対比して、信仰と不信仰に直結する「礼拝」の姿を迫っているのです。 キリスト者こそ、主なる神が住まう神殿である。 神と出会って、神と共に歩む、この世と一線を画した生活、それが私たちのささげる「礼拝の姿」なのではないでしょうか。
[fblikesend]「高い天から注がれる神の霊」 イザヤ書32章15~20節
イザヤ書の28章から35章までに「災いだ」という言葉で語られている「六つの災いの宣告」が語られています。 六つもの災いがあるがゆえに、「ついに」、今までの裁きを終えた後に起こされる主なる神の「救い」と「変革」をイザヤは語り始めるのです。 第32章の冒頭の1節から8節に少し目を留めます。 「一人の王が正義によって統治する。」 「高官たちは公平をもって支配する。」と言います。 ここで言う「一人の王」とは、正義の裁きと憐れみと恵みを兼ね備えたメシア、イエス・キリストでしょう。 旧約聖書によって延々と書き記し、伝え続けられてきたみ言葉が、イエス・キリストによって成し遂げられ、「神のものとなった民、イエス・キリストのからだとなった民」、新しい神の民が生まれると信仰告白をするのです。 ひとりのメシアが統治する。 そのメシアの贖いを受けた者たちが統治するようになる。 「ついに、今や、そのとき」が訪れたと賛美し、礼拝をささげているのです。 「風を遮り、雨を避ける所のように」、「水のない地を流れる水路のように」、「乾ききった地の大きな岩陰のように」なるという外的な変化に留まらず、内面的、霊的な変化が人間の心の中に訪れる。 「見る者の目は曇らされず 聞く者の耳は良く聞き分ける。 軽率な心も知ることを学び どもる舌も速やかに語る。」ようになる。 愚かな者が愚かなことを語っていても、神を無視して、主について迷わすことを語っていても、ならず者が謀り事をめぐらし災いをもたらしても、見極めることができなかった。 それらを見事に見極めることができるようになる。 この世における評価がまったく覆される。 そのメシアによる変革と逆転は、救いの実現に向かっているときではなく、むしろ破滅へと裁きの実現へと向かっている厳しい現実の中にこそ訪れると語るのです。 15節に「ついに、我々の上に霊が注がれる。」と言います。 「恵みを与えようと待っていた主なる神が、ついに憐れみを与えようと立ち上がられる。」 神の霊によって、神ご自身の意図をもってご自身のみ心を果たすために事を起こされる。 そのことを、「高い天から注がれる」と言うのです。 その変革は、私たちがうごめく世界の中からではなく、この世の私たちの思惑や計画によって起こされるものではない。 神の側から私たちのところへ下ってくる神の霊による力、意志によって果たされることである。 今、イスラエルの民が味わっている荒廃と滅亡の惨憺たる現実、自己解決の道が全く閉ざされてしまっている状態。 そこに救いと恵みの時が訪れる。 これは、私たち神の民の群れの中から、神の民の決意と決断によってもたらされるものではなく、神ご自身がご自身の民を用いて、天からの裁きとして、また、憐れみと恵みとしてご自身の民に与えてくださるものであると言うのです。 「高い天から神の霊が注がれるなら、すべてが変わる。」と言います。 「荒れ野は園となり 園は森となる。」という外的な変化、「荒れ野に公平が宿り、園に正義が住まう。」霊的な変化が起こされる。 聖書の言う「義」とは、神との関係、交わりの事です。 「正義」とは、神との正しい関係、交わりということです。 神とのあるべき関係、神に対する信頼を取り戻すということです。 この世のものさしに縛られ、見失っていた神のものさしを取り戻すことです。 神の言う「災いだ」と言われる姿を直視しなければ、真の神の憐れみと恵みを味わい知ることが 残念ながらできないのです。 その「正義が造り出すものは平和であり、正義が生み出すものはとこしえに安らかな信頼である。」と、主イエスが遣わされる何百年も前に主なる神が約束されているのです。 「安らかな信頼」とは、厳しい体験を通して味わった神への信頼と確信です。 そこで、主イエスは「平和の住みか」、「安らかな宿」、「憂いなき休息の場所」を読み取って、エルサレムの十字架の場所に自ら進んで行かれたのです。
[fblikesend]「主がいない間に預けられたもの」 ルカによる福音書19章11~27節
「ある立派な家柄の人のたとえ」と「ムナのたとえ」のふたつの「たとえ」が語られています。 「たとえ」が語られた理由をルカは、イエスたちのガリラヤからの長い旅がついに終わりの段階となり、「エルサレムに近づいておられるからである。」 そして、「人々が神の国はすぐに現れるものと思っていたからである。」と言うのです。 延々とイエスたちの長旅が綴られ、最後のエルサレムでのイエスの十字架の出来事を迎えようとしている緊迫した中に語られた「たとえ」であるとルカは言うのです。 マルコは、「時は満ち、神の国は近づいた。」と神の国の接近を告げます。 しかしルカは、「神の国は見える形では来ない。」と言い、使徒言行録において「父がご自分の権威をもってお定めになった時や時期は、あなたがたの知るところではない。 あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。」と言います。 神の国の時期の近さではなく、神の国そのものを語り、むしろその神の国の現れる時までの間の備えを訴えるのです。 「ある立派な家柄の人」のたとえには、ユダヤの人々の心に刻まれた一つの出来事が背景にあります。 ヨセフとマリアと幼子イエスは、ユダヤのヘロデ王の殺意を避けてエジプトに非難していた。 そのヘロデ王の死後、ユダヤに戻ろうとしたが、ヘロデ王の息子アルケラオがユダヤを支配していることを知って、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレの町に行って住んだとマタイによる福音書に記されています。 このヘロデ王の息子アルケラオは、ローマ皇帝より父ヘロデ王から引き継いでユダヤを治める王位を認めてもらうためにローマに旅立った。 これに反旗を翻し立ち上がったユダヤ人代表者50名がローマを訪れ、アルケラオの王位の継承と任命を妨げようとローマに陳情に行った。 ところが、ローマより王位の継承を勝ち取ったアルケラオはユダヤに帰り、自分に敵意を抱いたその50人を殺害したと言うのです。 このユダヤの人々の心の傷として刻まれた出来事を用いてこの「たとえ」に、その激しい表現を用いたのではないでしょうか。 主イエスもまた、遠いところに旅立っていく。 十字架の死をエルサレムにおいて成し遂げ、その三日後によみがえり天の父なる神のもとへ戻られる。 私たち人間が唯一神のもとへ辿り着く道を切り開いて、そこで一度失われた神の王位を再び受ける、取り戻す。 そのために主イエスは愛する弟子たちのもとを一旦離れるが、再び帰って来られる時がある。 その日まで、愛する弟子たちにはその間の時が与えられている。 神の賜物を求める者には聖霊が与えられると約束されたのです。 「ムナのたとえ」では、「あなたの一ムナで十ムナをもうけました。 五ムナを稼ぎました。」と、預けられた一ムナが新しいムナを生み出したと僕たちは喜んでいるのです。 ルカの言う賜物はすべて「一ムナ」ずつです。 「一ムナ」とは100デナリオン、1デナリオンは一日の賃金であったと言いますから、小さな単位を等しく僕たちに預けられたとルカは言います。 イエスが「神の国はからし種に似ている。 パン種に似ている。」 神のみ言葉、聖霊の働きは、この世では目にもとまらない小さな存在であるかもしれないが、「やがて成長する、膨れてくる」と言うのです。 人によって違いのあるこの世のものではない、本来持ち得ないものでしょう。 託されていること自体が喜びです。 用いることの恵みも与えられているはずです。 そこに神の恵みだけが支配する町が起こされると言うのです。 自分のためだけに自分を固く守っている人は、この世の死と共にその生涯が終わります。 しかし、主イエスが切り開いてくださった神のもとへ辿り着く道を歩む者は肉体の死をもって終わらない。 託されている賜物を、わずかな生涯のうちに用いる時、無上の喜びに囲まれるのです。 生きることは呼吸することではありません。 神に委ねてみて、神に用いられて与えられた生涯を味わうことです。
[fblikesend]「憐れみと裁きの神」 イザヤ書30章18~26節
主なる神が預言者イザヤに託されたイスラエルの民に対する言葉は、辛辣なものでした。 イザヤはこれにたじろぐことなく託された務めに歩み始めると、主なる神はその荒廃した中から、「それでも切株が残る。 聖なる種子が残る。 ひとつの芽が萌えいで その根からひとつの若枝が育ち その上に主の霊が留まる。」と、「神が我らと共におられる」というインマヌエルの預言、十字架の福音の恵みの種を蒔かれたのでした。 そして、「わたしが計ることは必ずなり、わたしが定めることは必ず実現する。」(14:24)と約束されたのでした。 イザヤによって語られたみ言葉に耳を貸そうとせず、自分たちにとって耳に心地よいことだけを聞こうとするイスラエルの民の姿に語る主なる神の辛辣な預言の真の目的は、ご自身の民が立ち帰ること、そのためにイザヤが遣わされること、人々の不信仰、頑なな心は、神の憐れみだけによってしか変えられないこと、この救われていく事実を示すために、壮絶な出来事を起こされたのです。 主イエスご自身もこのイザヤの語った言葉、「あなたたちは神の掟を捨てて、人間の言い伝えを固く守っている。」(マルコ7:8)と「ファリサイ派の人々と律法学者たち」に向けて引用し、主なる神のみ心を私たちに伝えておられるのです。 私たちは、聖書のみ言葉を自分自身に語られた言葉として聞かなければなりません。 決して、「ファリサイ派の人々と律法学者たち」を非難する立場に立ってはならないのです。 主イエスと主なる神のみ言葉は、私たちを神ご自身のみ前に立たせてくださるためです。 このつらい経験を、「わが主はあなたたちに、災いのパンと苦しみの水を与えられた」とイザヤは語ります。 「立ち帰って、静かにしているならば救われる。 安らかに信頼していることにこそ力がある。」と言われているのに、それを望まず自らの判断でその現実を解決しようと動いてしまっている。 結果はその逆になっているではないかとイザヤは語るのです。 主なる神は、「ご自身のもとに立ち帰ること、ご自身の計らいを信じて静かに待ち、願うこと」を求めています。 そして、「それゆえ、主は恵みを与えようとしてあなたたちを待っている。 主は憐れみを与えようとして立ち上がられる。」 それが、「正義の神」であると語られるのです。 「正義の神」とは、裁きの神、公平な神に留まらず、「恵みと憐れみを与えようと待って、立ち上がる神である」と言うのです。 そのための「災いのパンと苦しみの水」であった。 その道を歩んでいる私たちを導き 待っておられるお方は 隠れることなく、目に見るお方となる。 その語られる言葉を耳に聞くことになる。 言い換えれば、既に目の前におられて、共に働いてくださっているお姿を私たちはやっと目の当たりに見るようになる。 今まで決して聞こうともしなかった「これが行くべき道だ。 ここを歩け、右に行け、左に行け」と背後から語られるみ言葉に気づくようになると言うのです。 イザヤは、語るべき相手方である南ユダの人々の姿に、自らの姿を見て取って、つらい体験として味わった「災いのパンと苦しみの水」を通して、主なる神の生きたみ言葉が自らの生きる力によって、叫び求めるご自身の民を支え、助け、救い出し、教え、気づかせ、導かれる。 そのみ言葉の命の力、その確かさが立ち帰ってくる神の民に対し恵みを与える。 それは、今考えつくようなものではなく、とてつもない考えようもないほどの神の恵みであることが、いずれ成し遂げられる。 そのための一連の神の働きであることを、今は実現していないけれども、はっきりと知らされていたのでしょう。 「主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。 主はこの地を圧倒される。 地の果てまで、戦いを断ち 弓を砕きあがめられる。」(詩編46:9-11)と歌う確信にイザヤは至っていたのでしょう。
[fblikesend]「祈りによる交わりの回復」 フィリピの信徒への手紙1章3~11節
フィリピの信徒への手紙は、パウロが牢獄の中から直に書いた書簡だと言います。 自由が奪われ命の危険がある、そのような状況の中で、パウロからフィリピの人たちへ送られた手紙です。 フィリピでのパウロの滞在は、わずか数日間であったと言います。 教会という立派な建物があったわけでもなく、川岸にある「祈り場」にパウロたちが赴き福音を語ったのでしょう。 紫布を商う神を崇めるリディアという婦人が心を開き、パウロの語る話を注意深く聞いた。 そこから、彼女もその家族もバプテスマを受けたと言います。 とある出来事から牢獄の中に捕えられたパウロたちが、そこでも賛美の歌を歌い神に祈る姿が、フィリピの人たちに大きな影響を与えたのでした。 そこからヨーロッパで最初の教会が誕生し、今に至るまでパウロとフィリピの人たちとの「交わり」が脈々と続いているのです。 「わたしは、あなたがたのことを思い起こす度に、わたしの神に感謝している。」 「あなたがた一同のために祈る度に、いつも喜びをもって祈っています。」とパウロは言います。 今朝の聖書箇所の「パウロの祈り」は、牢獄の中で祈る「たったひとりの祈り」です。 フィリピの人たちが、「最初の日から今日まで、福音にあずかっていること」への「感謝の祈り」です。 「フィリピの人たちの中で善い業を始められた方」が、今もってそこにおられる。 今日に至るまで、変わらず守り導いてくださっている。 その神の働き、神の恵みに対する「感謝の祈り」です。 ほんのわずかな「交わり」に端を発し、今日に至るまで、その信仰を保ち、支え導いてくださっていることへの「神への賛美」です。 その「善い業を始められた方が、キリスト・イエスの日までに、その業を成し遂げてくださる」という確信を表明している「祈り」です。 キリストが再びおいでになるその日まで、フィリピの地において神の業が続けられる。 その日を目指して、フィリピの人たちとの「交わり」は続けられる。 パウロたちも、フィリピの人たちも、「キリスト・イエス」に結ばれている。 監禁されているときも、自由を奪われているときも、社会から断絶されているときも、命の危険さえあるときもです。 「福音を弁明し、立証するときも」と付け加えられているのもまた、広く他の人たちに伝えるときもと積極的な意味です。 み心のままに「終わりの日」には、必ず成し遂げられるとパウロは断言しているのです。 「共に恵みにあずかる」という意味は、自分一人ではなく共に恵みに触れて、共に交わるということです。 「キリストの福音に与る」とは、キリストにそれぞれがふさわしく結ばれ、それぞれ異なる恵みを味わい、それを持ち寄って交わるということなのです。 ご一緒にそれぞれにふさわしい福音の恵みを味わい、それらが一つとなって大きな神の働きへと結び合わされていく。 それが成し遂げられるまで、終わることなく続けられるということです。 パウロはこのことを願い求める「とりなしの祈り」を、たった一人で牢獄の中から喜びと感謝とともにささげているのです。 祈ることは、たったひとりでもできます。 神のみ前に自ら進み出てそこで初めて、神と交わることができる。 むしろ、ありのままの姿が、神によって引き出されていくのです。 私たちはどうしても、自分に依り頼もうするのです。 自分が無力であることを、どうしても認めたくないのです。 パウロはありとあらゆる苦難を体験したと、自己表現しています。 それは、パウロに対する神のご愛に裏打ちされた厳しい神の裁きであったのかもしれない。 しかし、それはパウロが「祈り人」へと変えられる神の「招き」ではなかったでしょうか。 自分たちもフィリピの人たちも、神ご自身の恵みによって守られ、支えられてきた。 これからも神の計らいに導かれていく「確信と事実」を、今まで味わってきた「キリスト・イエスの愛の心で」賛美とともに、「とりなしの祈り」をささげているのです。
[fblikesend]« Older Entries Newer Entries »