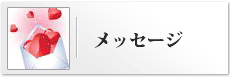「聖霊を受けなさい」 ヨハネによる福音書20章19~23節
イエスが十字架に架けられて処刑されて死んだ三日目の早朝です。 安息日が明けた週の初めの日曜日の朝です。 マグダラのマリアがひとり、イエスの遺体が置かれていた墓の外に立って泣いていました。 墓の中をのぞいたマリアが、イエスの遺体がないことを知って驚いています。 そこに死んだはずのイエスが現れて、「マリア」と呼びかけられました。 最初は、それがイエスだと分からず、その墓を守る園丁だと思っていたマリアに、イエスは、「わたしは、父なる神のところに上ると、弟子たちに告げなさい。」と語られたのです。 驚いたマリアは、急いで弟子たちのところに行って、「わたしはイエスを見た。 そのイエスは父なる神のもとへ上ると言われた。」と弟子たちに証言したのです。 告げられた弟子たちは、「ユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけて閉じこもっていた」とあります。 自分たちが慕って、生涯をささげて従ってきたそのイエスが、処刑されるという予想外の事態に直面した直後のことです。 焦燥感と諦めと、悲しみと苦しみに縛られているなかでも、弟子たちは集まって祈っていたというのです。 そこにイエスが現れて、「あなたがたに平和があるように」と言われました。 弟子たちは「主を見て喜んだ」とあります。 弟子たちはイエスが言われていた、「しばらくすると、あなたがたはもうわたしを見なくなるが、またしばらくすると、わたしを見るようになる。 あなたがたは悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。 わたしは再びあなたがたと会い、あなたがたは心から喜ぶことになる。 その喜びをあなたがたから奪い去る者はいない。」(16:22)というみ言葉を思い起こして喜びにあふれたのです。 弟子たちは、このみ言葉通りであったと証言する者でなければならなかったのです。 ですから、イエスは手とわき腹をお見せになって、十字架の傷跡をお見せになったのです。 悲しみと絶望に縛られていた弟子たちが解放されて、喜びに変えられた体験、これこそ「復活」の知らせ、「福音」です。 絶望と恐れと悲しみの向こうに現れる「神の平安」、「神の赦し」です。
縛られていた不安と恐れからの解放に満たされた弟子たちに、イエスは、「父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」と言われたのです。 復活したイエスに出会うという体験は、そのイエスから遣わされるという体験であったと言うのです。 弟子たちが遣わされるためには、先ず、イエスが復活したと証言する人でなければならなかったのです。 そして、もうひとつ、イエスの息が吹きつけられなければならなかったのです。 イエスと同じように父なる神のもとへ帰る、復活の命に生きるために、イエスは「聖霊を受けなさい」と言われたのです。 「わたしが注いでいるその聖霊をしっかり受け止めなさい。 その力によって出て行きなさい。」と言われたのです。 その力は、「だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される」、罪を赦す権能であると言われるのです。 息を注ぎ続けてくださっているイエスとともに弟子たちが歩むなら、そこは罪を赦す「神の平和」に包まれると言っておられるのです。 「十字架の死を経てよみがえられたというイエスの復活」が、「絶望と恐怖から解放されて、悲しみが喜びに変えられた弟子たちの復活」を支えているのです。 神との間に取り戻した「赦しと和解」が、私たち人と人との間にも「赦しと和解」をもたらし、「神の平和」を取り戻すというのです。 今日でもなお、弟子たちに授けられたこの復活の福音を、私たちは語り続けることができます。 聖霊によって働き続けてくださっている復活されたイエスに、私たちもまた出会うことができ、一人一人にふさわしいところに遣わされていくのです。
「立て、行こう」 マタイによる福音書26章36~46節
イエスは最後の晩餐の中で、すでに「弟子たちのうちの一人がわたしを裏切ろうとしている」ことを見抜いておられました。 いよいよ、その者が身近に迫ってくる、その緊迫した時です。 イエスはいつものように、いつものところで、父なる神との交わり、祈りの時をもっておられたのです。 イエスは弟子たちに言います。 「わたしが向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさい。」 これから十人の弟子のうちの一人ユダに率いられた人びとに捕らえられ、裁かれ、十字架に架けられ、死に及びます。 父なる神のみ心である十字架の死という出来事によって引き起こされる、弟子たちとの「別れ」がここに示されています。 この地上に愛する弟子たちを残して、ひとり孤独の中に去って行かれたイエスの姿が象徴されています。 その時のイエスの言葉です。 「ここを離れず、わたしと共に目を覚ましていなさい。 誘惑に陥らぬように、目を覚まして祈っていなさい。」 イエスが弟子たちに最後に教えられたこと、それが「祈ること」でした。 今からイエスご自身の無残な十字架の姿に直面しなければならない弟子たち、ここに留まり、離れないでじっと座っていることさえもできなくなってしまうであろう弟子たちに、「ここを離れてはならない。 ここに留まっていなさい。 目を覚まして起きて、祈り続けなさい。」と、その緊迫したなかで弟子たちにイエスは告げられたのでした。
同時に、イエスはご自身の「悲しみもだえる姿」、「わたしは死ぬばかりに悲しいと訴える姿」「うつ伏せになって、万策尽きたかのような姿」を、弟子たちにお見せになるのです。 「父よ、できることなら、この杯を、わたしから過ぎ去らせてください。」と訴える姿を、わざわざお見せになるのです。 イエスはそのような弱さをもった人の姿をとったうえで、「しかし、わたしの願いどおりではなく、み心のままに。 あなたのみ心が行われますように。」と祈っておられるのです。 それも三度も同じ言葉で祈られたと言うのです。 そのような切実な祈りを続けておられるイエスの傍らにいる弟子たちの姿が、「眠っていた」姿、「ひどく眠かった」姿でした。 弟子たちはイエスの言葉に従うことができませんでした。 イエスと共に祈るこができませんでした。 弟子たちだけではありません。 父なる神からも何の応答もなく、神の沈黙のなかにありました。 弟子たちからも、父なる神からも見捨てられ、孤独の中にありながらも、なぜイエスは「あなたのみ心が行われますように」と確信をもって十字架の道に歩むことができたのでしょうか。
この神の沈黙は、罪人の滅びを代って担う捨てられる苦しみをイエスに味わせることになる父なる神の悲しみです。 イエスの願いを聞き入れることのできない、共に苦しんでおられる父なる神の痛みです。 ルカによる福音書は、「天使が天から現れて、イエスを力づけた」と記しています。 父なる神は、この「杯」を乗り越えることができるようにと、神のもとから力を与えられたのです。 神の沈黙は、イエスが神に従うための備えの時でした。 神は、「わたしの思いは、あなたたちの思いとは異なる。 わたしの思いは、あなたたちの思いを、高く超えている。」(イザヤ55:8-9)と言われます。 この確信に至ったイエスは、立ち上がって十字架の道を歩み進められたのです。 眠り込んでいる弟子たちに、父なる神の答えのないまま天からの力を受けて、確信をもって「時が近づいた。 罪人たちの手に、わたしは引き渡される。 立て、行こう。」と裏切り続けた弟子たちに呼びかけ、眠り込んでいる弟子たちを呼び起こしておられるのです。 弟子たちの弱さを十分ご存じのうえで、すべてを赦したうえで、「時が来た。 起きなさい。 立ち上がりなさい。 一緒に立って、歩んで行こう。」と言われたのです。神の沈黙が与えたもの、それが「イエスの復活」です。
「ともし火と油」 マタイによる福音書25章1~13節
「天の国は次のようにたとえられる」と言われるこの「たとえ」は、ご自分の命を捨てる十字架を前にしたイエスが、死んで再び戻ってくるという終わりの日の厳粛さのなかに語られている「たとえ」です。
ユダヤの結婚式は、夜から始まります。 花婿が花嫁を迎えに行き、花嫁を連れて自分の家に行き、婚宴が始まるというのが一般的なユダヤの結婚式であったようです。 この「たとえ」によりますと、十人のおとめが手に「ともし火」を持って、花婿を迎えに出て行った。 ところが、花婿が来るのが遅れてしまった。 十人のおとめ全員が待ちくたびれて、眠気がさして眠り込んでしまったと言います。 そこに、「花婿だ。 迎えに出なさい。」という叫び声が届いた。 その声を聞いて、全員が起きてそれぞれの「ともし火」を整えた。 ところが、花婿が到着して一緒に婚宴の席につくことができたのは五人だけであった。 その他の五人は間に合わず、家の戸が閉められて入ることができなかった。 時が限られていて、大事な時に喜びの婚宴に加わることができなかったという「たとえ」です。 この「十人のおとめ」とは、花婿を「ともし火」を持って出迎える人たちです。 花婿の到着が遅れたため、眠り込んでしまった人たちです。 花婿が到着したという知らせを聞いて、急いで「ともし火」を整えた人たちです。 その違いは何らありません。 ところが、「賢いおとめ」と「愚かなおとめ」に分かれたと言うのです。 その違いは、油を用意していたかどうかという違いでした。 「ともし火」は、芯に油を染み込ませて明かりをつけるものであったでしょう。 その「ともし火」を灯し続けるために、「油」を入れる「壺」に注ぎ足す「油」を準備していたかどうか。 これが、この「たとえ」の言うおとめたちの違いです。
問題は、この「花婿を迎える」という意味です。 イエスはこれからご自分の命をささげようとしておられるのです。 イエスは、「命を捨てなければならない」という、神のもとから捨てられるということの恐ろしさのゆえに、この身からこの杯を去らせてくださいとまで祈られています。 神から裁かれ、捨てられるという人間の「死」を味わい尽くしてくださったのです。 恐ろしい「死」の現実を目の前にしながら、その「死」の力を越えるものがあることを指し示そうとなさったのです。 私たちが裁かれなければならない「滅び」を代って体験し、苦悩と悲しみの中に降ってきてくださったのです。 そのイエスを、私たちが信じることができない「よみがえり」という方法で、父なる神がイエスを「死」の中から引き上げられたのです。 「花婿を迎える」ということは、このよみがえられたイエスを迎え入れために待つことです。 すべての人の前に再び現れ出るイエスを迎え入れるということは、婚宴の日、喜びの日だと語っているのです。 だから、明るく照らす「ともし火」、イエスの光を受けて輝く「信仰」と一緒に、「ともし火」に注ぎ足す「聖霊の油」を備えなさい。 その油の「壺」である「祈り」によって、注ぎ足されて蓄えなさいと語っているのではないでしょうか。 「油」とは、求める者には必ず神が与えてくださる聖霊です。 この賜物は、人に依存して与えられるものではありません。 自ら、花婿であるイエスを出迎えて、向かい合って初めて与えられるものです。 人情や感情によって、助け合いによって融通してもらうものではありません。 自分の人生を他の人に代わってもらうことのできない厳粛さを憶えて、「あなたがたは、その日その時を知らないのだから、目を覚ましていなさい。」と、これから十字架に向かい、「死」を味わい尽くすところに向かわれるイエスによって、弟子たちに問われたのではないでしょうか。
「もう見ている復活の主」 ヨハネによる福音書9章35~41節
「外に追い出された彼」と「ファリサイ派の人々」と「イエス」がいます。 「彼」とは、生まれつき目の見えなかった人です。 通り沿いに座って物乞いをしていた人です。 弟子たちが、「この人が生まれつき目が見えないのは、だれが罪を犯したのですか。 本人ですか。 それとも両親ですか。」と尋ねるぐらい、だれも気にもかけていなかった存在です。 そんな「彼」にイエスは、「土をこねて彼の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさい」と言われた。 イエスの言う通りにした「彼」の目が見えるようになった。 不思議がる近所の人々が「お前の目はどのようにして開いたのか」といくら尋ねても、「彼」は目が見えるようになった事実しか答えることができない。 治してくれたイエスが、いったいだれなのかさえ分からない。 その出来事を聞きつけたファリサイ派の人々が、イエスを裁く格好の出来事としてイエスが行った安息日に禁じられている行いを公に挙げつらうために尋問するのです。 ファリサイ派の人々は、「彼」だけでなく、その両親までも呼び出すのです。 両親は、イエスを「救い主である、メシアである」と証言すれば、社会から追放する権力をファリサイ派の人々がもっていることを知っている。 問い詰められても両親は答えず、本人から聴くようにと逃げる。 近所の人々にも、両親にも追い出され孤独となった「彼」は、それでも「あの方は罪人かどうか、わたしには分かりません。 ただひとつ知っていることは、目の見えなかったこのわたしが、今見えるということです。 神は罪人の言うことはお聞きにならない。 しかし、神をあがめ、そのみ心を行う人の言うことは、お聞きになると承知しています。 もし、あの方が神のもとから来られたのでなければ、このようなわたしの目が見えるようにしてくださることはできなかったはずです。」と証言したのです。 その時の「彼」の身に起こった出来事が、この聖書箇所です。
目が見えず、通り沿いに物乞いをしていた「彼」の姿に目を留められたイエスが、再び、外に追い出された「彼」を求めて出会ってくださった。 そして、「人の子を信じるか」と尋ねられたと言うのです。 「人の子」とは、終わりの日に神のもとから遣わされる「救い主」と信じられていた人です。 そう尋ねられた「彼」は、「その方を信じたいのです。」と思わず答えている。 自分の身に起こされた事実は、神のもとから来た者でなければ引き起こすことができないと、「彼」は信じることができた。 そのお方こそ、「人の子」ではないかと思うまでになっていた。 自分では理解することも、説明することもできないが、そのお方を「わたしは信じたい。 そのお方にもう一度、お会いしたい。」 これが「彼」の願いでした。 その「彼」にイエスに言われたのです。 「あなたはもう出会っている。 もうすでに見ている。 新しい目でみえるようになったものは、あなたと話しているこのわたしである。」 その言葉に圧倒されて答えた「彼」の言葉が、「主よ、信じます。」でした。 その「彼」を、最初に目を留め、ずっと見守っていたのはイエスです。 そして、ひとり外に追い出された「彼」に最初に近づいてきてくださったのもイエスです。 ご自身を見えるようにして、ひざまずいて礼拝するまでに「彼」を変えられたのです。 私たちにとって「復活」の出来事こそ、自分の新しい目が開かれる。 その目で、よみがえられて霊なる姿になって働いてくださっているイエスを仰ぐことができる。 昔のままの目で見ている自分が壊されて、視点を変えられて、方向を転換されて、見えなかったイエスの姿を取り戻すことができる。 もうすでに起こされている恵みに、視点を変えられて気づくこと、これが私たちにとっての「復活」の出来事であると、「彼」の身に起こされた事実によってイエスは語っておられるのです。
「福音を告げ知らせる」 コリントの信徒への手紙一1章10~17節
イエス・キリストによって呼び出された者たちの群れを、聖書は「エクレシア、教会」と言っています。 神の働き、目に見えない霊の働きによって形づくられた共同体を指します。 この「エクレシア、教会」がこの地上で存在する理由は果たして何でしょうか。 また、いったいどのような務めが与えられているのでしょうか。 「教会」には、ふたつの力が働いているように思います。 ひとつは、教会の中にあって働く、霊なるイエスとの交わりです。 二千年前に十字架に架かってくださったイエスは今や、父なる神によってよみがえらされ、この地上における霊なる働きそのものとなって私たちに伴なってくださっています。 この交わりによって、人と人との交わりが神の愛による交わりへと変えられていくのです。 もうひとつの力は、この群れから外に向かって働き出す力、宣教、伝道です。 問題は外に向かって働き出す力の方角です。 この地上での存在として、「教会」がその存在理由を示そうとすればするほど、立派な存在にしていこう。 世の中の人に認められ、むしろ羨まれるぐらいの存在になろう。 教会がますます発展し、人が増え、建物も立派にしていこう。 霊なるイエスの働きを脇に置いて、人間のものさしによって「教会」をつくり上げようとするのです。 「教会」に働く力は、神の霊なる力です。 風のように自由奔放に働く霊なる大胆な働きです。 私たちの理解不可能な力です。 それをこの世の経験や知恵によって、コントロールしていこう。 このような力がもう一方で働く、この葛藤とせめぎあいが教会の歴史なのではないでしょうか。
パウロが設立したコリントの教会がまさに、そのような状態にあったのです。 「あなたがたの間に争いがあると、知らされました」と、手紙の冒頭でパウロは書き始めています。 コリントの教会のめいめいが、「わたしはパウロにつく、アポロにつく、ケファにつく、キリストにつく」と言っている分派争いが起こっています。 パウロこそコリントの教会の創始者です。 パウロを慕っても不思議はありません。 その後に教会に来たアポロは、聖書に精通していただけでなく、弁舌さわやかな説教者であったと言います。 アポロに養われた人々もたくさんいたでしょう。 ケファとは、エルサレム教会の指導者ペトロのことです。 イエスとともに生活した紛れもない使徒の代表者でしたから、心酔していた人も多かったのでしょう。 内紛に嫌気を刺した人々が、人間を離れキリストにつくと新しいグループをつくったのかもしれない。 パウロは、「あなたがたは、キリストに呼び集められた群れではなかったのですか。 キリストはどこに行ったのですか。 教会の中にはキリストはおられないのですか。」と訴えるのです。 人間のことに思いを寄せて、神の思い、キリストの存在を忘れてしまっているコリントの教会の人々に、「皆勝手なことを言わず、仲たがいをせず、心を一つにし、思いを一つにして、キリストにあって固く結び合いなさい。」と言うのです。 目に見える人間の思いを捨てさせ、「十字架に架かってくださったのは、いったいだれですか」と、キリストを思い起こし、十字架を思い起こすためでした。 そしてパウロは、「キリストがわたしを遣わされたのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであった」と言うのです。 バプテスマを受けるという行いによって、私たちは救われるのではありません。 イエス・キリストの死と復活に固く結ばれることによって救われるのです。 そのために、十字架の福音、イエス・キリストの福音を告げ知らせることが、私たちの務めなのです。 「教会」はこの世にありながら、この世とは一線を画します。 「時は満ち、神の国は近づいた。 悔い改めて福音を信じなさい。」という、福音を語る務めが私たちに与えられているのです。
「不正にまみれた富」 ルカによる福音書16章1~13節
イエスが語られた「たとえ」です。 「自分の財産が無駄遣いされている」と知った主人は、管理人を呼びつけて言います。 「会計の報告を出しなさい。 もう管理を任せておくわけにはいかない。」 そう言われた管理人は、「主人はわたしから管理の仕事を取り上げようとしている。 でも辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。」と考えた管理人は、次々と、主人に借りのある人々を呼んで、それぞれの借りを軽くしてあげるのです。 不正を働いた管理人が自分の将来のために、更に不正を重ねて主人の財産に新たな損失を加えようとしているのです。 だれしも主人が烈火のごとく怒り、管理人を取り詰めると思うでしょう。 ところが、その主人は「この不正を働いた管理人の抜け目のないやり方をほめた。」と言うのです。 なぜイエスは、このような「たとえ」を語られたのでしょうか。
この「主人」とは、ご自身のものを管理人に託した「父なる神」のことをイエスが語っておられるのでしょう。 「管理人」とは、「主人」に託されたものを自分のために用いた、あるいは用いようとしたこの世にある私たちのことでしょう。 この「たとえ」をイエスが語っておられる相手は、愛する弟子たち、そして私たちです。 私たちは「父なる神」によってつくられ、命を与えられ、からだも時間も財産も知恵も力もそれぞれにふさわしく与えられています。 イエスは管理人が働いた「不正」をほめているのではありません。 この「不正」は、道義的に赦されることではありません。 また、ずるがしこく立ち回りなさいと教えているのでもありません。 だれがどのようにして手に入れたにしろ、それらの富すべては神のものである。 神から委ねられ、託されたものである。 その富の用い方を、イエスは弟子たち、私たちに問われたのではないでしょうか。 いくら正当に手に入れたものであったとしても、自分が勝ち取って自分のものであるかのように用いるならば、それもまた「不正にまみれた富」になると言われているのです。 いずれは「父なる神」に返さなければならない厳粛な時がくる。 もし、そのことを忘れてしまっているなら、「父なる神」が「会計報告を出しなさい。 もう管理を任せておくわけにはいかない。」と言われる時がくるでしょう。 その時こそ、神の前に出る時です。 神と私だけの時です。 申し開きの時です。 この世にある限り、託されたものをどのように用いるのか、どのように生きるのかは、私たちの自由に委ねられ、しばしの間は隠されているでしょう。 しかし、その管理すべき時が終る時がいずれくる。 主人に報告をもって立たなければならない時がくるのです。
私たちの神に対する借りは、膨大な赤字でしょう。 埋め尽くすことのできない量の赤字でしょう。 その膨大な量の赤字をイエスが引き受けてくださっている。 父なる神が、私たちのあがきのようなふるまいをも、赦してくださっている。 神ご自身の前に立つためにすばやく備えた管理人のふるまいを、赦してくださっていると、イエスがあとわずかしかないこの世の別れを忍んで弟子たち、私たちに憐れんで語りかけてくださっているのではないでしょうか。
イエスはその「不正にまみれた富」をもって、「友達をつくりなさい」と言われます。 そうしておけば、「金がなくなったとき、弟子たちあなたたちは永遠の住まいに迎え入れてもらえる」と言われるのです。 「金がなくなったとき」とは、この世を去るときでしょう。 一切のものを手放さなければならない時でしょう。 イエスは、「わたしの兄弟であるこの最も小さい者のひとりにしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」(マタイ25:40)と言われています。 私の友となるように、この限られた地上の生涯を送るようにとイエスは励ましてくださっているのです。 だから、あなたがたは神のために、富を用いなさいと言われているのです。
「神の武具」 エフェソの信徒への手紙6章10~18節
パウロはこの手紙で、「今は悪い時代であるから、愚かな者としてではなく、賢い者として、細かく気を配って歩みなさい。 時をよく用いなさい。 無分別な者とならず、主のみ心が何であるかを悟りなさい。 酒に酔いしれてはならない。 むしろ、霊に満たされ、霊的な歌によって主に向かってほめ歌いなさい。 いつも、あらゆることにイエスの名によって神に感謝しなさい。」と語っています。 このような思いをパウロはもちながら、この手紙の最後に語っているのが今日の聖書箇所です。 「最後に言う。 主に依り頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。」と言うのです。 この時のパウロは獄中にあります。 もう、そう多くは語りえないだろう。 だから、最後に、この悪い時代に生きる新しい生き方の根幹は、「神に依り頼み、神の偉大な力によって強くされることだ。」とパウロは言うのです。
パウロの言う「悪い時代」とは、特別にこの時代が悪いと言っているのではないでしょう。 どの時代でも、神のもとを離れてしまっているところからくる過ちを私たちは繰り返しています。 来るべき新しい時、神の国が訪れるその時に対して、今は神に背を向けている時代です。そうは言っても私たちは過去に生きることはできないし、今の現実に立って生きていかなければなりません。 ですから、私たちには今を生きる痛みがあります。 この痛みを忘れてもならないでしょう。 この神のもとから離れさせようとするこの世の力との戦いは、「血肉を相手にするものではない。 支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものだ。」 私たちの戦いは人間を相手とする戦いではない。 その人間を動かして、意のままに支配し、操作して、動かしているすべての力との戦いであるとパウロは言います。 私たちは自分に直接向かってくる相手を見てしまいます。 しかし、パウロはそうではないと言います。 その相手を動かしている、私たちの目には見えない力を恐れているのです。 神の力を小さく見せて、目に見える力を大きく見せて、不安や絶望に私たちを落とし込んで、その恐れに私たちを縛り付けて、巧みに支配し、操作し、動かそうとする力を相手とする戦いである。 そのようなものから守るための武具を身に着けなさいとパウロは言うのです。
パウロの言う「神の武具」とは何でしょうか。 「帯として締めなさい。 胸当てを着けなさい。 履物を備えなさい。 盾を取りなさい。兜をかぶりなさい。」と言っている身に着けるものとは、「真理」です。 イエス・キリストそのものです。 神の正しさです。 神の平和の福音です。 信仰です。 神による救いです。 それもこれも、神によってしか与えられないものばかりです。 この武具を着けて、人を支配し、操作するこの世の霊と戦うために、「主に依り頼み、主の偉大な力によって強くなって」、「霊の剣」を取りなさい。 神の言葉を受け取りなさいと言うのです。 人間がつくるようなもの、考えるようなものではなく、神によって与えられる霊的なもので身を固めなさい。 これは神の霊による戦いである。 神のみ言葉による戦いである。 そのうえで、「どのような時にも、霊に助けられて祈り、願い求め、絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。」と言うのです。 「どのような時にも」です。 「絶えず目を覚まして」です。 「根気よく」です。「祈り続けなさい」です。 これが、この世の霊と戦う、神の戦いに備えている私たちキリスト者の生きる姿です。 イエス・キリストの生き方を真似て、自分の力を磨いて生きる生き方ではないのです。 神の力によって、神によって授けられるものによって強くされる姿です。 そして、自分のためだけでなく、同じようにこの世の霊に取り囲まれ、さらされているすべての人のために祈る姿です。
「宣べ伝えなさい」 マタイによる福音書10章1~12節
イエスが十二人の弟子を呼び寄せられました。 父なる神に授けられているイエスご自身の権能を十二人の弟子にお授けになったと言います。 この有様には、イエスの弟子の原型があります。 このイエスによる弟子の選びと派遣は、イエスの深い憐れみを原動力としています。 迫ってきている神の国に、「弱り果て、打ちひしがれている人々」を招くためのイエスの業でした。 イエスが行われている通りの業を引き継ぐための備えでした。 そのために弟子たちは集められ、イエスから賜物を授けられ、人々のところに派遣されていくのでした。 その「授けられた権能」とは、「汚れた霊」を追い出す権能、神のもとから離れさせようとするこの世の力、あらゆる病気や患いを通して人々に与える不安や絶望から救い出す権能でした。
イエスはこの十二人の弟子たちを派遣するにあたり、「異邦人の道に行ってはならない。 また、サマリア人の町に入ってはならない。 むしろ、イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。 行って、天の国は近づいたと宣べ伝えなさい。」と命じられたのです。 なぜイエスは、イエスをまったく知らない異邦人のところではなく、イスラエルの人々のところに先ず行きなさいと言われたのでしょうか。 イスラエルの民は、神の民として選ばれた民のはずです。 その民が、選んだそのお方を頼らず、神のみ心を思わず、自分勝手に歩み出してしまっている。 そのご自分の民が「飼い主のいない羊のようだ」とイエスは憐れんでおられるのです。 この失われたイスラエルを取り戻すこと、これが宣教の始めであると、十二人の弟子たちにイエスは語ったのではないでしょうか。 イエスの神の国の福音宣教は、「悔い改めよ。 天の国は近づいた。」という短いみ言葉でした。 選ばれたイスラエルの民の悔い改め、方向転換を呼びかけること、イスラエルの民の回復がすべてに優先されていたということでしょう。 マルコによる福音書では、「十二人は出かけて行って、悔い改めさせるために宣教した」とはっきりと書いてあるのです。 そして、イエスご自身が今まで行ってきたように、病人をいやす、死者を生き返らせる、重い皮膚病を追い払うようなことが弟子たちにもできるようにと、ご自身が授っている権能を与えられたのです。 そして、あなたがたはその権能を、「ただで受けたのであるから、ただで人々に与えなさい」と言われたのです。 「ただで」とは、価なしにということです。 何の資格もない、ただ神の恵みによって与えられたということです。 十二人の弟子たちの信仰歴は、わずか1~2年であったでしょう。 何の資格もなければ、何の力も、何の経験もありません。 また、事前の訓練も備えもありません。 突然呼び出されて、突然その力が授けられたのです。 すべて、イエスの方から呼びかけてくださって、「ただで」その力が与えられ、選ばれたのです。 すぐ近くにいるイスラエルの人々、新しいイスラエルに、ただ自分が神に赦されたこと、愛されてきたことをそのまま証しするだけであったのです。 ですから、「帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れて行ってはならない。 袋も二枚の下着も、履物も杖も持って行ってはならない。」と、神の支配の中に包まれて神のみ心に従って働く者には、神ご自身が必要なものをすべて用意してくださるし、神の国の支配が現実に私たちの中にあることを神ご自身が証ししてくださるとイエスは言うのです。 私たちはイエスから授けられた精いっぱいの賜物で、神の国の福音を告げることが私たちの務めです。 しかし、そこから先は、私たちが決めることではありません。 神のわざ、神の戦いです。 私たちはするべきこと、する必要のないことを神に教えていただかなければなりません。 すべきことの虜になってもならないし、すべきことに気づいてもいなければならないのです。
「わたしが愛したように」 ヨハネによる福音書13章34~35節
イエスは十字架に架けられる前の晩、弟子たちの足をひとりずつ洗い終え、その足を洗った弟子たちのうちのひとりユダが出て行った後に、「あなたがたに新しい掟を与える。 互いに愛し合いなさい。」と語られました。 奴隷である僕が行うような「人の足を洗う」というイエスが取られた振る舞いの意味を、弟子たちは理解することができなかったでしょう。 事実、ペトロは、「主よ、あなたがわたしの足を洗ってくださるのですか」と不思議がっています。 そのイエスに向かって、「わたしの足など、決して洗わないでください。」とまで、真剣に断っています。 そのペトロにイエスは、「わたしのしていることは、今あなたには分かるまいが、もし、わたしがあなたを洗わないなら、あなたはわたしと何のかかわりもないことになる。」と答えておられるのです。 そして、弟子たちすべての足を洗い終えたイエスは、「わたしがあなたがたの足を洗ったのだから、あなたがたも互いに洗い合わなければならない。」と、十字架に架けられるその前の晩に弟子たちに語られたのでした。
一人一人の汚れた足を見つめながら、腰を静めて丁寧に洗い流す。 私たち人間の汚れている部分をご自身が引き受けられて、その過ちを贖ってくださる。 そのイエスを通して注がれた「神の愛」、「救いの招き」を、ひとりユダだけは受け取ることなく、その場から出て行った。 その直後にイエスが、「あなたがたに新しい掟を与える。 互いに愛し合いなさい。」と語られたと言うのです。 「自分を愛するように隣人を愛しなさい。」という律法の戒めがすでにあるのに、イエスはなぜ「新しい掟を与える」と言われたのでしょうか。 それは、「わたしがあなたがたを愛したように」です。 「昔の人の言い伝え」とされている戒めに、「イエスがわたしたちを愛したように」愛することを加えたということです。 イエスは、「父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛してきた。 わたしの愛にとどまりなさい。」と言っておられます。 イエスご自身が体験されておられる神の愛です。 同じように、ご自身を十字架にささげるまでに私たちを愛してくださっているイエスの愛です。 そのように示された神の愛にとどまることによって、互いに愛し合いなさいと、イエスは新しい掟として語っておられるのです。 イエスに足を洗われて初めて、私たちもまたその隣人の足を洗うことができるようになる。 過ちをイエスの十字架によって赦されて、贖われた者だけが、互いに神の赦しによって愛し合えるようになる。 そこには、その過ちに気づいた人の涙がある。 砕かれた時の痛みがある。 イエスの十字架によって砕かれ、つくり直され、赦された人の喜びがあるのです。 イエスはそうした者たちだけが、互いに愛し合えるようになると言っておられるのです。
イエスになぜ、多くの人々が群がってきたのだろうと思わされます。 貧しい人たち、悲しむ人たち、社会から見捨てられた人たちでした。彼らがイエスの驚くばかりの教えをそのまま理解し、受け入れたとは到底思えない。 しかし、同じ肉体をもった人としてのイエスの深い憐れみが、人々の心を捕らえたのでしょう。 イエスの分け隔てのない言葉と振る舞いに、彼らが本当に求めていたものを感じ取ったのでしょう。 イエスの示す憐れみに、この世にない「神の愛」を感じ取ったのでしょう。 ユダヤ人も異邦人もない。 自由人も奴隷もない。 男も女もない。 かけがえのない人として愛しておられるイエスのまなざしに彼らは魅かれて、この世にない「愛」を感じ取ったのではないでしょうか。 人が神に赦される、愛されるということが、人を根本的に生き返らせるのであるということを、彼らはイエスの姿と語る言葉の中に感じ取った。 神を見ることができたのではないでしょうか。
「わたしの時」 詩編90編1~12節
詩編90編は、「神の人モーセの詩、祈り」と書かれています。 モーセと言えば、エジプトの地からその奴隷として虐げられていた同胞のイスラエルの人々を救い出した「偉大な指導者」と私たちは表現するでしょう。 しかし、モーセの生涯を考えてみてください。 生まれてすぐイスラエル民族への迫害のゆえにエジプトのナイル川に流されるという、悲しい出来事からその生涯が始まっています。 しかし、神はその赤ちゃんをよりによってエジプトの王女に拾わせ、エジプトの王宮の中でモーセを育て必要な教育を受けさせたのです。 成長したモーセは、同胞であるイスラエルの人々の苦しい奴隷の姿に憤り、迫害するエジプト人を殺してしまう。 苦役に縛られているイスラエル民族の解放のために立ち上がるが失敗し、失意のうちに荒れ野で羊を飼う生活に入り込んでしまうのです。 ここでも、神はご自身が選んだモーセを再び立ち上がらせ、エジプトに向かわせるのです。 神のイスラエル民族の救いのご計画の担い手として立たせ、同胞の人々の不信仰に何度も悩まされながらも、エジプトの反撃に遭いながらも、自然の脅威に襲われながらも、40年もの間、エジプトから連れ出してきた人々とともに荒野をさまよい、ついに約束の地カナンを目の前にするまでに至ったのです。 そこでモーセは体力、気力とも満ち溢れていたにも拘わらず、その生涯を終えたのです。 モーセだけは約束の地に一歩も入ることが赦されなかったのです。
このモーセが神に向かって、「大地が、人の世が生み出される前から、世々とこしえにあなたはわたしたちの宿るところ」と歌い始めるのです。 そのように私たちは創られたはずなのに、私たちはその神のもとを離れて、漂う者、移ろう者、しおれる者、枯れゆく者、消え去る者、飛び去る者となってしまった。 あなたはとこしえに変わりなくおられるお方。 しかし、私たちの人生はたかだか70~80年、本来宿るべきところを忘れてしまった私たちは、このようにはかない者となって、はかない人生を送るようになってしまっていると言う。 その理由を、神が「隠れた罪」を光の中に置いて、明るみにされたと言い、神の憤りが私たちに迫っても不思議なことではないと言う。 神はこのような罪深さに気づかず、驕りの中に沈み込んでいるこの私たちを、土の塵に返すお方です。 そのように扱われても仕方のない私たちです。 これだけエジプトから救い出されても、不平や不満を言い、もとに戻ろうとする。 同じことを繰り返してしまう人々の自分勝手な姿を通して、モーセは気づいたのです。 また、やりきれない自らの思いから、神の約束を受け取ることができなくなる自分自身の姿を通して、私たちはすべて死ぬべき存在であると分かったのです。 自分たちがいかにはかない存在であるのか。 神を恐れないで自分勝手に動いてしまう存在であるのか。 その本当の姿をはっきりと自覚したその時です。 「人の子よ、帰れ」 「あなたを塵に返す。 あなたは、わたしのもとへ帰れ。」という神の声がこだましたのです。 モーセは神の命令によって、体力も気力も十分にあったにも拘わらず、自分の死を受け入れて人々の罪深さを背負って、ひとり神のみ心によってそこに留まったのです。 モーセは、神の厳粛さを知り尽くすと同時に、「選ばれて、用いられて、ここまでみ心を果たし終えたモーセよ、わたしは人を塵に返す者である。 そのわたしのもとへ帰れ。」という神の招きに癒されたのです。 彼の願いは約束の地に入ることではなく、神に用いられることでした。 自らの人生はこの神のみ手の中にあったのだと確信して、その喜びに同胞のイスラエルの人々が与るようにと、「生涯の日を正しく数えることができるように教えてください。 塵に帰る私たちの肉体の死が、神のもとに赦されて帰る喜びの日となるように。」と、モーセは祈るのです。
« Older Entries Newer Entries »