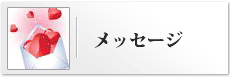「託された必要なもの」 マタイによる福音書25章14~30節
イエスがこれから迎えるご自身の十字架での死を直前にして、愛する弟子たちとのお別れにこの「譬え」を語っています。 イエスはひと度、しばしの間、弟子たちの前から姿を消すことになる。 しかし、必ず戻ってくると語っています。 「主人は、これから旅に出かける。」と僕たちに言います。 「主人」とはイエスのことです。 「僕たち」とは愛する弟子たちのことです。 この「譬え」は、イエスと僕たちの関係について譬えているのです。 決して、人間どおしの「道徳」を譬えているのではありません。 主人がしばしの間の旅に出かける前に、「自分の財産を、僕たちに預けた。」と言います。 その財産を、「タラントン」という通貨単位をもって表現しています。 1タラントンとは、6000デナリオン。 1デナリオンは一日の賃金相当であったと言いますから、1タラントンと言えども相当な額の財産ということになるでしょう。 それを、「それぞれの力に応じて預けて、主人は出かけた。 しかし、かなりの日がたってから、主人が帰ってきてから精算を始めた。」と言います。 この「タラントン」とは何でしょうか。 「それぞれの力に応じて預けられる。 預けられたものを倍にして返す。 預けられたものをそのまま地の中に隠しておく。」とはどういうことでしょうか。 主人は、いったい僕たちの姿の何を見つめておられたのでしょうか。
「タラントン」とは、主人のものです。 しばしの間だけ、僕たちに預けられたものです。 僕たちの所有物でも、予め備わっているものでもありません。 1タラントンだけでも豊かなものです。 主人は僕たちを信頼して、その「タラントン」と「時」をその務めに応じて託したということでしょう。 ところが、「忠実な僕だ。 よくやった。 もっと多くのものを預けよう。 わたしと一緒に喜んでくれ。」と言われた僕と、「怠け者の悪い僕だ。 預けられていたものを取り上げられる。」と言われた僕とに分かれました。 主人は預けたものの成果をご覧になって喜ばれたり、悲しまれたのではありません。 それぞれの務めに預けられたことを喜んで用いた僕の姿を喜んでおられるのです。 主人は、その喜びをともに分かち合いたいのです。 そうではなく、自分がなくしてしまったら主人に咎められる、責められることを恐れて、主人のみ心に応えることができなかった僕の姿に、主人は悲しみを覚えたのでしょう。 一緒になって喜びを分かち合いたいと願う主人のみ心を知ろうとしないで、自分の身に迫ることだけに目を向けた僕の姿、むしろ、預けたものを減らすことのなかったことを褒めてもらおうとした僕の姿を、主人は悲しんだのです。 イエスのこの厳しい言葉は、神の御心を忘れ、自分の身を守るために神の言葉の形だけを守ることに専念した当時のファリサイ派の人々の姿に向けた悲しみの言葉でしょう。
「主人が帰ってくる時がやがてくる。 精算を始める時がくる。」のです。 その時こそ、イエスとともに喜びを分かち合う時です。 神の国が訪れる「その時がやってくる」と、イエスは愛する弟子たちにしばしの別れをこの「譬え」で告げておられるのです。 ご自身が大切にしておられるものを託して預ける。 再び出会うとき、預けられたものを用いた恵みを持ち寄って互いに喜びを分かち合おうと、呼びかけておられるのです。 預けられるものは、イエスを通して注がれる一方的な恵みです。 私たちの身に備えられる資質や才能といったものではありません。 私たちの忠実さや努力によって勝ち取られるものでもありません。 神の持ち物です。 神のご用のために用いられるものです。 ですから、この預けられたものは自ら必ず、預けられた人を用いて神のみ業を成し遂げるのです。 そのための「しばしの間」と「タラントン」と「恵みの喜び」なのです。
「ペトロの恵み」 使徒言行録10章1~16節
場面は、カイサリアという町にいるコルネリウスとヤッファという町にいたペトロとの出会いです。 カイサリアもヤッファもともに、地中海に面するパレスチナ地方の代表的な港町です。 ヤッファは、エルサレムと密接につながる保守的なユダヤ主義の町です。 カイサリアは、ヘロデがローマ皇帝のために年数をかけて築いたローマによるユダヤ支配の象徴的なギリシャ文化の色濃い町です。 コルネリウスは、そのカイサリアに常駐する「イタリア隊」と呼ばれる部隊の百人隊長でした。 ギリシャ文化に包まれたカイサリアに住む純粋なローマ人です。 「信仰厚く、一家そろって神を畏れ、民には多くの施しをし、絶えず祈っていた。」と、理想的な信仰者の姿であったと言います。 一方、ペトロは、かつてガリラヤの漁師であったユダヤ人でした。 イエスと出会い、聖霊が降り、別人のように変えられた人です。 方々を巡り歩き、イエスの語った福音を宣べ伝え、病を癒し、不思議な業を行い、ユダヤ主義の色濃いヤッファに滞在していたのです。 そのようなローマ人とユダヤ人であった二人を、神は出会わせようとするのです。 神の福音自らが場所と文化と人種を超えて、二人を用いてその壁を突き破っていこうとするのです。
最初に、カイサリアにいるコルネリウスに神は呼びかけます。 「ヤッファにいるペトロをカイサリアに招きなさい。」という分かりやすく、具体的な呼びかけでした。 一方、ヤッファにいるペトロにも神は呼びかけます。 しかし、その呼びかけは難しく、理解不能なものでした。 「大きな布のような入れ物に入っているものを屠って食べなさい。」という呼びかけでした。 その入れ物の中には、「律法に戒められていた清くない物、汚れた物が含まれていた。」とペトロは拒みます。 それでも、「わたしが清めたものを、清くないなどと言ってはならない」と神はペトロを戒めます。 これが三度繰り返されたと言います。 ペトロは、この神の呼びかけを食べ物のことであると決めつけて、思い込みで三度も拒んだのです。 そこで、コルネリウスにも神の呼びかけがあったことをペトロは初めて知らされて、この神の呼びかけは食べ物のことではなく、人間に対する福音を宣べ伝えることであることを知らされたのです。 ペトロはコルネリウスに出会って、「神はわたしに、どんな人をも清くない者とか、汚れている者とか言ってはならないとお示しになりました。 神は人を分け隔てなさらないことが、よく分かりました。」と語っています。
一方、ペトロを迎えるコルネリウスは、最大限の敬意をペトロに払います。 親類や親しい友人を呼び集めてペトロを待っていました。 ペトロの姿を見るや、足元にひれ伏して、「今わたしたちは皆、主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして、神の前にいるのです。」とまで言います。 コルネリウスはペトロを迎えたというより、神を迎え入れて、そのみ前に進み出ていると言っているのです。 ペトロも同じでした。 「あなたがたもご存じのとおり、ユダヤ人であるわたしは外国人と交際したり、訪問したりすることは律法で禁じられています。 けれども、神はわたしに、どんな人をも清くない者とか、汚れている者とか言ってはならないとお示しになりました。 それで、すぐにここに来たのです。」と、先立って行われた分け隔てなさらない神の働きだけを見つめているのです。 この三度も繰り返し神に砕かれたペトロが、コルネリウスのもとに遣わされたのです。 そこで、神の前に進み出てペトロが語る福音を聞き逃さないようにと多くの人々が待っていた恵みに、ペトロは与ることができたのです。 福音を伝えられたコルネリウスたちも、福音を伝えたペトロも、ペトロについてきた人たちもそこで、神の働きに与ることができたのです。 パウロは言っています。 「福音のためなら、わたしはどんなことでもします。 わたしが福音に与る者となるためです。」(コリント一9:23)
「立ち上がるサウロ」 使徒言行録9章1~19A節
生まれたばかりのキリストの教会は、ひとりの人物の大きな変化によって新しい世界が拡がっていったと聖書は語っています。 その人物はヘブライ語読みで「サウロ」、ギリシャ語読みで「パウロ」です。 ユダヤ教の中から飛び出したキリスト者たちが、「十字架に架けられたナザレ人イエスが神の子であった。 すべての人々の救い主となった。 今もなお、死を乗り越えて生きて、自分たちに出会ってくださった。」と証言し始めたので、エルサレムでは神を冒涜する者であると激しい迫害が起こっていたのです。 その最前線で指揮を取っていたのがサウロです。 「十字架に架けられた者」は神に呪われた者であると学んできた律法からも、自分の信念からも断じて許すことができないと、「脅迫し、殺そうと意気込んで、見つけ出したら、男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行しようとした」のです。 そのサウロが、エルサレムから200キロ以上も離れたシリアのダマスコで、天からの光に照らし出され、自分の名を呼びかける声を聴いて地に倒れたと言います。 あまりの輝きに、サウロは驚いたのです。 「呼びかけるあなたはどなたですか」のサウロの問いに返ってきた「あなたが迫害しているイエスである」という答えに、サウロは混乱したのです。 迫害していたのは、イエスを神の子と仰ぐキリスト者たちでした。 サウロは今、迫害されたキリスト者たちの痛みを自分の痛みとするイエスの呼びかけに出会ったのです。 イエスは、神に呪われて十字架に架けられて殺された、それだけの人物である。 自分を神と一体としたために、神を冒涜する者として処刑された人物であるとばかりサウロは思っていたのです。 死んだはずのそのようなイエスが、今、生きてこの迫害する自分に呼びかけている。 サウロは、キリスト者たちの「イエスは復活した」という証言を思い起こしたに違いない。 イエスを十字架に架けて殺した人々と同じように、自分もまたひとりひとりのキリスト者たちを捕らえ、処刑して、イエスを痛めつけている者であることを知らされたのです。 サウロは自分の本当の姿を知らされて、三日間、目が見えなくなって、何も飲み食いができなくなったと言います。 この三日間は、サウロにとって必要な時、神の恵みの時でした。 このイエスは律法によって裁かれたのでも、処刑によって裁かれたのでもない。 神の愛によって、神の痛みによって、私たち人間の過ちを背負って、神の前に立って裁かれてくださった。 私たちの代わりに神に見捨てられてくださった。 神に見捨てられるという本当の恐ろしさを味わってくださった。 そのイエスが今、ここに生きて自分に呼びかけてくださった。 そのことを、サウロは聖霊によってやっと知らされたのでした。
そのような状態のサウロのもとに、アナニアという人物が遣わされます。 イエスはアナニアにも、「サウロのもとに行け。 サウロは、あなたが手を置いて、元通りに目が見えるようにしてくれるのを祈り待ちわびている。」と呼びかけます。 アナニアは、「サウロは、エルサレムでどれほどの迫害を、わたしたちに行ったのかを聞いて知っています。 ここダマスコでも、祭司長たちからイエスの名を呼び求める人たちを片っ端に捕らえる権限を受けてやってきています。」としり込みします。 イエスはそれでも、「サウロは、わたしが選んだ器である。 わたしの名による福音を、異邦人に、すべての神の民に告げ知らせるために、わたしが準備して、選んだ人物である。」と迫ったのです。 サウロの生い立ちも、学んできたことも無駄にされることなく、また誤った熱心さから起こした過ちもまた赦されて、相応しい援助者も与えられて、まったく方向の異なる方へ神のみ業のために用いられるよう整えられていったのです。 これはサウロだけの特別なことでしょうか。 ひとりの回心が、イエスの輝きでその周りを照らし出すのです。
「イエスとの出会い」 ルカによる福音書2章8~20節
ルカによる福音書が記す最初のクリスマスは、ローマ皇帝が命じる住民登録の命令によって、大騒ぎとなっているその最中に訪れたと言います。 だれも注目していないユダヤのベツレヘムというダビデの町で、泊まるところなく「飼い葉桶に布にくるまれて寝かされていた」ひとりの乳飲み子の誕生として訪れたとあります。 私たちが「救い主」として賛美するそのお方の誕生は、皇帝の命令に翻弄され、その騒々しさのなかで、粗末に置かれたひとりの赤ん坊として起こされたのです。 きらびやかなところでも、誰が見ても圧倒されるような荘厳な厳粛なところでもなければ、ひとかけらのこの世の威厳もないところで、イエスはこの世に遣わされたのです。 そのありふれた乳飲み子であるイエスの誕生を、神は「野宿しながら、夜通し羊の群れの番をしていた羊飼いたち」を目に留められ、知らせたとあります。 羊飼いの仕事は、昼夜を分かたず羊の世話をする過酷なものでした。 人々からは卑しい仕事であると思われていたのでしょう。 そのような軽んじられていた、小さな存在であった羊飼いたちに、「恐れるな。 今日、大きな喜びを告げる。 ダビデの町で主メシアが生まれた。 『布にくるまれて飼い葉桶に寝かされている乳飲み子』がそれである。 これが、あなたがたへのしるしである。」と告げられたのです。 9節に、「この知らせを聞いた羊飼いたちは、主の栄光が周りを照らしたので非常に恐れた。」 13節には、「羊飼いたちに語り終えた神の使いに、天の大軍が加わって、『いと高きところには栄光、神にあれ。』と賛美したとあります。 聖書は、このクリスマスの出来事を神の栄光が現れ出るためであった。 神の栄光のためであったと、神の側のことを中心に語っているように思います。 神の側から見れば、その創り主を忘れて自分勝手な道を歩んでいる。 創り主を必要としないで自分が神のようにふるまっている。 力もない、知恵もない、小さな存在であるにもかかわらず、自分たちが造った権威に酔いしれて生きている。 このような私たちの姿こそ、「神の悲しみ」でしょう。 そのことに未だに気づいていない。 自分の本当の姿を見ようともしない。 逃げ隠れする私たちがいることが、「神の痛み」でしょう。 しかし、この神の前に失われたものと思われていた私たちが、方向転換し、ひと度、神のもとへ戻ってくるなら、神にとってこれ以上の「神の喜び」はないのではないでしょうか。 ですから、私たちが神を求める以上に、私たちを神が捜し求めてくださっている。 戻ってくるようにと、私たちを招いておられるのです。 神はご自身を離れてしまっている本当の恐ろしさを知っておられるから、放っておくことができないお方です。 私たちひとりひとりの過ちを赦して元に戻すために、イエスをこの世に遣わしたのです。 ルカは、このイエスの誕生の出来事を、初めに「神の栄光が周りを照らした。」 その終わりに、「栄光、神にあれ」という賛美が響いたと証言しているのです。 神がそこに顕れ出て、その神の力が溢れ出て、だれの目にも神の権威が明らかとなるそのところには、神を賛美する声が響く。 そのことを、ルカは、「神の栄光が周りを照らす。 それを仰いだ者が賛美している。」と書き記したのでしょう。 イエスの誕生という神の栄光が顕れ、羊飼いたちがいつものように夜通し羊の群れの番をしているそのところを照らした。 羊飼いたちが、神の起こされた業を見ようではないかと立ち上がった。 神の栄光を仰いだ者たちが声を挙げて賛美したと書き記しているのです。 イエスの誕生は、放っておくことのできない神の栄光のためです。 それと同時に、私たちが救い出されるためになされた神の業です。 私たちの救いは、私たちの側の熱心さや努力ではなく、神の栄光、神の必要のために、神ご自身が働いてくださっているも神の業です。
[fblikesend]「クリスマスという騒動」 マタイによる福音書2章13~18節
ヘロデ王の時代に、イエスはユダヤのベツレヘムにお生まれになりました。 東の方から「占星術の学者たち」が星に導かれ、エルサレムにやって来たと言います。 天体の異変に気づき、世界を救う「救い主」を礼拝するために、遠い彼方から「黄金、乳香、没薬」を携えてエルサレムを訪れたのです。 この知らせに、ヘロデは「不安を抱いた」とあります。 国中の祭司長、律法学者たちを集めて、その学者たちが言っているメシアはどこで生まれることになっているのかを調べさせたのです。 「ユダヤのベツレヘムに生まれる」と聞かされたヘロデは、「占星術の学者たち」をひそかに呼び寄せ、「行って、生まれたメシアと思われる子を詳しく調べ、知らせるように」と、言葉巧みに学者たちを送り出したのです。 その場所こそ、だれも注目していない馬小屋、そこには母マリアと父ヨセフしかいないような寂しいものでした。 とても世界を救うメシアが生まれたと信じることができないような有様であったにもかかわらず、その生まれた場所をつきとめた学者たちは喜びにあふれたと言います。 ひれ伏して、その赤ちゃんを拝んだ後、「ヘロデのもとへ帰るな」という神の言葉をかけられて、別の道を通って自分たちの国へ再び戻って行ったと言うのです。
この学者たちが帰った後です。 神はヨセフに言います。 「その子どもと妻マリアを連れて、エジプトに逃げなさい。 わたしが告げるまで、そこにとどまっていなさい。 ヘロデがその子を探し出して、殺そうとしている。」という恐ろしい知らせを聞いたのです。 ただでさえ、これから自分たちの身に何が起ころうとしているのか不安であったヨセフに、今度は、ユダヤの王ヘロデによってその子が殺されようとしている。 その難を避けて、遠く離れた、何も分からないエジプトの地に行かなければならない。 それも、いつまでかも分からないと言うのです。 先を見通せないまま、エジプトに向けて流浪の旅に出なければならない。 そこで神の呼びかけを待ちながら、じっとそこに留まらなければならないという知らせを神に突き付けられたのです。 イエスの誕生が人を分岐点に立たせます。 ヘロデも、ヨセフもともに「不安を抱いた」のです。 しかし、ヘロデは、自分に取って替わる新しいメシアの出現を感じ取った「不安」でした。 その不安を取り除こうとして、自分だけが平安のうちに過ごすために、今までの経験やあらゆる知恵と、自分が今まで勝ち取ってきた力によって、不安に陥れるものを取り去ろうとしたのです。 それがベツレヘムとその周辺一帯の二歳以下の男の子の殺害であったのです。 一方、ヨセフはその不安の中にあっても、神の言葉に聴き、分からないままでも従って行こうとしたのです。 神に呼びかけられるまで、希望をもって待とうとしたのです。 ヘロデも、ヨセフも、学者たちもすべて、神に用いられているのでしょう。 私たちは、自分のわずかしか見えていない目で、また、自分の経験でしか受けとめることのできない常識で、イエスの誕生を見ようとします。 神はイエスを十字架に献げて裁くまで、生まれたばかりのイエスの命をヘロデから守ったのでしょう。 イスラエルの民が、エジプトやバビロンに囚われた体験を追体験させているのでしょう。 流浪の旅を強いられたヨセフの家族の痛みは、イエスの十字架の死のためでした。 ベツレヘムの二歳以下の幼子が殺されるという出来事に、ヘロデを陥れたこの世の霊の働きを憶えます。 些細なことから陥ってしまう私たちの弱さ、醜さの悲しみを憶えます。 イエスの誕生の出来事は、私たちを根底から覆す「騒動」とも言うべき驚くべき出来事です。 この世の霊の働きに縛られている私たちに一石を投じる出来事です。 マリアが宿したように、私たちもまたこのお方をうちに宿して、このお方とともに歩んで参りたいと願います。
「神の子として迎えるクリスマス」 ルカによる福音書1章26~38節
神はマリアに、「あなたは身ごもって男の子を産む。 その子の名をイエスと名付けなさい。」と言われました。 結婚前のマリアにとって子どもができるとは、父親のいない子を産むということです。 当時のユダヤの社会では、訴えられれば厳しい律法によって姦淫の罪として石打ちの刑に処せられるのです。 そのような突然の、自分の人生を大きく揺さぶる知らせがマリアのもとに舞い込んだのです。 いくら、「その子は偉大な人になる。 神の子と言われるようになる。」と言われても、マリアにとってはそれどころの話ではありませんでした。 ただただ困惑するだけです。 「どうして、そのようなことがありえましょうか。 わたしは男の人を知りませんのに。」と応えるのが精いっぱいであったのでしょう。 マリアにとって、このクリスマスの出来事は常識を超えた、信じることのできなかった驚きの出来事でした。 私生児を産むという世間からの誹謗、中傷があったとしても不思議ではない出来事でした。 これから一生涯、この重荷を背負っていかなければならい窮地に陥った知らせでした。
常識と理性によって、不安のうちに応えるマリアに神は挑みます。 「聖霊があなたに宿り、神の力があなたを包む。 だから、生まれるその子も、この世から取り分けられた聖なる子となる。 神の子と呼ばれるようになる。」と言われたのです。 マリアは決して、神の前に素晴らしい決断をしたわけではありません。 告げられた知らせに思い巡らし、悩んだのです。 将来に不安を覚え、悩み、踏ん切りがつかなかったのです。 これは誕生の時だけではありませんでした。 イエスが成長し、その人間には理解できない振る舞いに戸惑い、そのたびに人間の常識によって親としての心配をし、イエスをたしなめようとまでしたのです。 それでもマリアには、他に頼るべきものはありませんでした。神の約束の言葉しか、頼るべきものは残されていなかったのです。 ですから、思い巡らし、何も分からないまま、ただ語られた「聖霊が宿る。 神の力に満たされる。 その子は育まれ、神の子となる。 このことは、何千年も前から預言されてきたことである。」という神の約束の言葉に、自らを委ねていくしかなかったのです。 それが、「わたしは主のはしためです。 お言葉どおり、この身になりますように。」という言葉になったのでしょう。 イエスの目には、この母マリアの姿はどのように映っていたのでしょうか。 ある女性がイエスを賞賛して、「あなたを宿した胎、あなたが吸った乳房は、なんと幸いなことでしょう。」と言われたイエスは、「むしろ、幸いなことは、神の言葉を聞き、それを守る人である。」(ルカ1:28)とだけ答えられました。 イエスは、産んだ母親としてマリアは幸いであったと言っておられるのではないのです。 思い巡らし、不安の中にたたずんで、それでもなお、「お言葉どおり、この身になりますように」とみ言葉に聴いて従った母マリアを幸いであると言われたのです。 神のみ言葉を聞いてその約束に従い、その約束のうえに立って生涯を生きること、これほど幸いなことはないと言われたのです。
このイエスの誕生物語を詳細に書き記したキリスト者たちは、歴史の中に胎児として現れ、人間の代わりに裁かれ、私たちの過ち、醜さ、弱さを死んで贖ってくださったイエス、よみがえられて、神のもとに戻る道を切り開いてくださった「霊なるキリスト」を賛美しているのです。それが神の約束であった、神のご計画であった、そこに神のご愛とご真実があったと証言しているのです。 マリアと同じように、信じることができない、説明することができないような出来事に遭遇して、それでもなお神のみ言葉に立って生きる生涯を賛美しているのです。 母マリアが宿した胎児こそ、このよみがえって霊なるキリストとして私たちの中に宿ってくださるイエス・キリストです。 このお方との交わりに生きる生涯に、私たちは招かれたのです。
「クリスマスの驚き」 イザヤ書53章1~5節
預言者イザヤは、救い主メシアは「乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように主の前に育つ」と預言しています。 ユダヤ教の中から起こされてきた最初の頃のキリスト者は、「十字架に架けられて処刑されて死んだはずのナザレの人イエスが、墓の中にない。 よみがえったとしか言わざるを得ないように、自分たちの前に姿を現してみ言葉をかけられ、一緒に食事し、交わり、共に生きてくださった。」と証言し始めたのです。 イエスというひとりの人間が死から復活した。 それは神の起こされた出来事であった。 このお方こそ、神ご自身のもとに立ち帰る人間の歩む「道」となってくださった。 見ることも、聞くこともできなかった暗闇の世界を照らす「光」となってくださった。 肉体の死に縛られている世界から解放されて、神のもとに憩う新しい霊の世界に生きる「命」となってくださった。 そのことに最初に気づかされたキリスト者たちにとって、現在の私たちと同じようにイエスの「復活」は驚きの出来事であったのです。 いったいどのような力が働いて、どのように成し遂げられたのか、説明することのできないことであったのです。 この驚くべき「復活」という神の救いの出来事を見つけ出したキリスト者が、このメシアの誕生、イエスの誕生について福音書にこう証言しています。 イエスの誕生は、名も知られていないヨセフとマリアというありふれた二人に赤ん坊として与えられた。 生まれる場所さえ用意されていなかった、粗末な扱いであった。 しかし、ありふれた大工の息子として育てられたその子どもが、霊の導きによって人とはまったく異なる成長をした。 親でさえその振る舞いを理解することができなかった。 苦しみ、悲しみの中にある人、虐げられている人の側に立って、その不思議な力から病いを癒し、心の平安を与えた。 人々からは、このお方こそ自分たちの国を再び復興させるお方として期待され、担ぎ上げられるようになった。 しかし、自分たちが望むものではないと分かった人々は、今度は手のひらを反すように見捨て、軽蔑し、十字架という惨い処刑によって殺害した。 まさにイザヤが預言したように、「見るべき面影も、輝かしい風貌も、好ましい容姿もない、軽蔑され、見捨てられた」存在でとなったのです。 「神の手にかかり、神の罰によって打たれたから、苦しんでいる」姿に見えたのです。 それは、隠された神のみ心でありました。 「わたしたちが人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。」(コリント一2:5) 十字架に架けられたイエスの姿こそ、神がこの世に遣わしたご計画であったのです。 私たちは、この神のみ心に従ってみようとしないから、自分たちの望みだけに頼ってみようとするから、イエスの振る舞い、イエスがなされる姿を受け取ることができないのです。 受け取ることが難しいのは、イエスの十字架を受け入れることが難しいのではないように思います。 イエスの十字架の姿は、私たちのすべての弱さ、醜さ、過ちを担ってくださった姿です。 自分の醜い姿こそ、その姿であることを認めることが私たちには難しいのです。 自分の弱さ、醜さを見つめざるを得なくなる恐れを感じるからです。 イエスの十字架の前に私たちが立つなら、その姿を突きつけられるからです。 暗闇は、光に照らされることを恐れます。 自分が暗闇であることを認めたくないのです。 罪は、神の正しさの前に出ることを避けます。 自分の醜さを晒したくないのです。 イエスは私たちに替わって、神に砕かれるため、懲らしめを受けるために十字架に架けられたのです。 私たちに神との交わりを回復させるためです。 それが神のみ心であるからです。 イエスの誕生の出来事は、この隠されていた神の救いの業を、驚きをもって「十字架に架けられた」醜いイエスの姿とともに見つめなければなりません。
[fblikesend]「どこまでも離れない神」 創世記45章1~13節
ヨセフは、族長ヤコブの息子12人の11番目です。 この異母兄弟の息子たちによって、12部族のイスラエルの民が形づくられました。 兄たちは、父ヤコブにもっとも愛されていたヨセフを妬み、憎んでいました。 兄たちの様子を見てくるようにと父に言われたヨセフが、父の羊の群れを飼っている兄たちのところに近づいてきたのを好機に、兄たちは「ヨセフを殺して、穴に投げ込もう。 あとは、野獣に食われたと言えばよい。」などと相談までしていたと言います。 兄たちはヨセフの着ていた晴れ着をはぎ取り、捕らえて穴に投げ込んで、イシュマエル人に売ろうとしたのです。 そして、ヨセフの着物を殺した雄山羊の血に浸して、野獣に食われたのだと見せかけ父ヤコブを悲しませたのです。 ところが、エジプトに売られてしまったヨセフが、今や、そのエジプトで国を治める者とまでになっていたのです。 聖書は、「主がヨセフと共におられたので」という言葉を再三用いて、ヨセフの行ったことはすべてうまく事が運んだと言います。 エジプトでは、ヨセフがエジプトの王が見た夢を説き明かして、7年の豊作と7年の飢饉が神によって起こされることに気づいて、豊作の時に食糧をできる限り蓄え、飢饉に備えるようにしていたのです。 その食糧の監督を一手に行っていたのがヨセフだったのです。 飢饉に見舞われた所から食糧を求めてやってくる人々が、ヨセフのもとに押し寄せていたのです。 なんとそこに、イスラエルから、自分を売ってしまったその兄たちが食糧を求めてやってきたと言うのです。
一目で、自分の兄たちであること知ったヨセフは、気づかれないように兄たちを試します。 「この国を探りに来たに違いない。 もし本当に正直な人間だと言うのなら、兄弟のうち一人を牢獄に監禁しなさい。 他の者は皆、飢えている家族のために穀物を持って帰り、末の弟をここに連れて来なさい。」と、ヨセフはすべてを知ったうえで兄たちに命じたのです。 末の弟とは、ヨセフと同じ母をもつ唯一の弟、愛すべきベニアミンです。 ヨセフはなぜ、兄弟の一人シメオンを縛り上げ、父のもとにひとり残していた末の弟ベニアミンを連れてくるようにと難題を強要したのでしょうか。 父ヤコブがもっとも悲しむことを、兄たちに強要したのでしょうか。 ヨセフには悲しい過去の体験があります。 兄たちに見捨てられ、互いに家族がひとつにまとまることのできない苦しみ、父を同じように愛することのできない家族間の愛の貧しさを知っています。 ひとり残されるシメオンを本当に兄たちは愛しているのか。 連れて来られたベニアミンを父のもとに連れ帰る覚悟は本当にあるのか。 そのベニアミン、そして兄たち皆が戻ってくるのを心待ちにしている父ヤコブを本当に愛しているのか。 そして、この自分を売った罪深さを兄たちは認め、今では悔い改めているのか。 そのことに、兄たちの姿をじっとヨセフは見つめていたのでしょう。 そのような難題を突き付けられた兄たちを代表して、ユダがヨセフに語った弁明です。 「父ヤコブに、ヨセフが語った厳しい言葉を伝えました。 しかし、ベニアミンを連れてくることこそ、もっとも愛していた息子ヨセフを亡くして悲しむ父ヤコブの最大の痛みです。 もし連れ帰ることができなければ、この自分を代わりに監禁してください。」とヨセフに嘆願したのです。 今までとは違う兄たちの砕かれた姿を、そのユダの弁明する姿にヨセフは見たのでしょう。 父ヤコブを心から愛する兄たちを、その姿によって見極めたのでしょう。 互いに愛し合う兄たちの姿を見て取ったヨセフは、ついに平静を保つことができなくなり、自分の身を明かしたのです。 ヨセフは喜びにあふれ、涙が噴き出たと言います。 ベニアミンと兄たちを抱いて泣いたと記されています。 神はご自身の民、12部族をつくるために、ヨセフを異国の地に前もって遣わし、兄たちをイスラエルから異国の地に遣わし、それぞれに心を砕いて互いに引き合わせてくだる。 どのような境遇にあったとしても、それぞれから離れることなく神は共にいてくださり、それぞれを救うために養ってくださっていたのです。
「神の備えに生きる」 創世記22章1~14節
神の約束の言葉だけを信じて従ってきたアブラハムは、神から愛され、常に神とともにある存在でした。 不可能と思われる子どもさえも晩年には与えられ、その祝福のしるしとも言える恵みに神を賛美することを忘れず、礼拝を怠らなかったアブラハムでした。 神に「アブラハムよ」と呼びかけられ、「はい、ここにいます」と応えることのできる、神との親しい交わりの中にあったアブラハムでした。 そのような祝福に満たされ、信仰に大きな欠けがあるとは思えないアブラハムを神が試したと言われるのです。 試したというよりは、命じられたとあります。 その命令の中味が、「あなたがもっとも大切にしている、あなたが愛してやまない息子、独り子イサクを一緒に連れて行きなさい。 わたしが命じるところ、モリヤの地、わたしが命じる山の一つに登りなさい。 そして、そのイサクを焼き尽くす献げ物としてささげなさい。」というものであったのです。 神は何ゆえに、生々しい残酷さを秘めているこの試みをアブラハムにかけなければならなかったのかと問いただしくなります。
ところがアブラハムは、この神のご命令にためらったり、思い悩んだり、動揺することなく、直ちに翌朝早く、黙々と自ら「ろばに鞍を置いた。 献げ物に用いる薪を割った。 神の命じられるところに向かった。」のです。 そして、三日目にその命じられたところに到着したと言います。 この惨い内容を秘めている神のご命令を内に抱いて、父と息子がともに向かう三日間の姿を思い浮かべてみてください。 親子ふたりの心の中にある思いを想像してみてください。 何とも言えない重苦しさを感じます。 神が命じた場所に到着した父アブラハムはついてきた若者たちに、「わたしと息子はあそこへ行って、礼拝をして、また戻ってくる。」と、これから起こるであろう残酷さを秘める出来事を、まるで息子と一緒に礼拝をする出来事であるかのように思っています。 息子イサクは、「わたしのお父さん」と父アブラハムに呼びかける。 父アブラハムは、すぐさま、「わたしの子よ」と応える。 父と息子の間に緊張感が漂っています。 「お父さん、火と薪はここにありますが、焼き尽くす献げ物にする小羊はどこにいるのですか。」と問う。 薄々、息子はこれから起こるであろう出来事を感じ取っていたのかもしれない。 どう答えてよいのか分からない父には沈黙があったのかもしれない。 「わたしの子よ、きっと神が備えてくださる。」に違いないと答えるしかない。 この答えに息子は納得したのでしょうか。 父は、息子の疑問に十分答えたと思ったでしょうか。 この短い対話の後、神が命じられた場所に、神が命じたことを成し遂げるために、それ以上何も語らず、二人は一緒に歩いて行って、祭壇を築き、息子をささげるという神への礼拝をささげようとしたのです。
神が命じられた場所は、父アブラハムと息子イサクの二人だけでしか行くことのできなかった場所です。 互いに「わたしのお父さん、わたしの子よ」と言うだけで、何も語らず神にささげる二人だけの礼拝のために赴く親子の姿です。 父アブラハムは、この三日間の沈黙の重苦しい歩みの中で知らされたのでしょう。 神によって与えられたものを神にお返しする。 これから神ご自身から与えられるものを、愛する息子と一緒に受け入れようとする。 神が求めて奪い取っていかれるものを、息子と一緒にお返ししようとする。 25年間、待ち続けて不可能と思われた息子の命をさえ叶えて与えてくださった神を信じることができた。 その神にはご計画があることを信じることができた。 神はすべてをご存じで、神ご自身が説明してくださると委ねることができた。 息子をささげただけでなく、アブラハム自身もまた、神にささげることができたのです。 そこで神が、備えに気づかせてくださったのではないしょうか。
「見えるみ業と見えないみ業」 使徒言行録5章17~26節
使徒たちが捕らえられ、投獄されたのはここで二度目です。 最初の時は、ペトロとヨハネが生まれながら足の不自由な男を癒すという出来事を起こした時です。 イエスが死者の中から復活したという事実を、民衆の前で堂々と宣べ伝えていた時です。 その二人の姿を見ていていた祭司長たちが「いらだって」投獄したのです。 そして、「決してイエスの名によって話したり、教えたりしないように」と脅して二人を釈放したのです。 二度目となる今度は、「ねたみに燃えて、使徒たちを捕らえて公の牢に入れた」と書いてあります。 こうして囚われた使徒たちに、目に見えて不思議なことが起こったのです。 何の抵抗もできない使徒たちでした。 牢にはしっかりと鍵がかけられていました。 念には念を入れて、その牢の扉の前には番兵までもが立っていたと言います。 そうであるにもかかわらず、使徒たちは牢の外に連れ出されました。 解放されただけでなく、「行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさい」という神の言葉に呼びかけられました。 「神殿の境内」とは、使徒たちが捕らえられた現場です。 またしても同じように、もう一度そこに立ってみ言葉を告げなさいという神の命令であったのです。 使徒たちは凝りもせず、再び出かけて行って神の呼びかけ通りに「命のみ言葉」を民衆に向けて語りかけたのです。 この尋常ではない不思議な出来事に驚き、思い惑いながらも祭司長たちは、三度目の逮捕と投獄をここで行ったのです。 なすがままに身を委ねるしかできない小さな存在の使徒たちを、それがたとえ公の牢の中であったとしてもお構いなく、神は用いようとされるのです。 神の選びの器がたとえふさわしいと思えなくても、神はその選びにふさわしく働く場に立つまでどこまでも追い求めて、連れ出して、その務めの場に立たせてくださるのです。 私たちの状態がどうであれ関わりなく、神のご計画に沿って小さな存在である私たちでさえも用いてくださると言うのです。 いかなる妨げがそこにあろうとも、閉じ込める鍵をへし折って、その扉を開いて、妨げる番兵を差し置いて、そこから連れ出して神の働きの場に向かわせるのです。 この見えるみ業こそ、神の恵みのしるしです。
しかし、神の恵みのみ業はここで終わらないのです。 そのしるしを通して、私たちは神の呼びかけ、神のみ言葉を聴くことができるきっかけを頂くのです。 使徒たちを裁く側の中から人を起こして、神はご自身のみ心を成し遂げられるのです。 民衆全体から尊敬されている人物、使徒たちを外に出すようにと命じることのできる律法の権威者であるガマリエルでした。 「使徒たちの行動が人間から出たものなら、自滅するだろう。 しかし、神から出たものであれば、使徒たちを滅ぼすことはできない。」というガマリエルの意見によって、釈放されたのです。 使徒たちは自分たちが釈放されたことをそこで喜んだのではなく、「イエスの名のために辱めを受けるほどの者にされたことを喜んだ。 そして、言われた通り、毎日、神殿の境内や家々で絶えず教え、福音を告げ知らせた。」と言います。 神は事を起こす前に、もうすでに使徒たちを迫害する最高法院の中から律法学者の権威を用いて準備をなさったのです。 神はご自身の働きのために、私たちの思いに先立って事を起こしておられるのです。 私たちは神の助けを願うことに夢中になって、神の呼びかけるみ言葉に耳を傾けることに貧しい者です。 見えるみ業に満たされた際に、神はご自身の働きのための務めを私たちに語りかけてくださるのです。 私たちはその恵みの結果だけに目を奪われて、神の務めの呼びかけを聞き逃してしまうのです。 私たちが気づいていようがいまいが、この命の言葉を語るべくして、その命の言葉に生かされるべくして、神は準備して呼びかけてくださるのです。
« Older Entries Newer Entries »