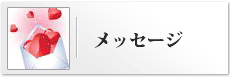「マルタとマリアの信仰」 ルカによる福音書10章38~42節
マルタとマリアの小さな家庭での出来事です。 「マルタという女が、イエスを家に迎え入れた。」と言います。 ユダヤの指導者たちが、盛んに教えを宣べているナザレの人イエスは、民衆を間違った教えに扇動していると言っている最中に、マルタは世間を恐れずこの家を代表して、イエスを喜んで迎え入れているのです。 この家の家族が家を開放して、世間の風潮に囚われず喜んでイエスを迎え入れているということです。 そのマルタは、「いろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていた」と言います。 料理上手で、手の込んだ最高の御馳走をふるまってもてなそうとしたのでしょう。 その一心で、あれもこれもとしなければならないことに、頭と心の中が詰まっていたのでしょう。 一方、マリアは、「主の足もとに座って、イエスの話に聞き入っていた」と言います。 当時は、教師から教えを乞うために、弟子たちは木陰で、教師の足もとに座って、その教えに耳を傾けて教師に親しく語りかけたと言います。 「主の足もとに座る」という姿は、教師と弟子との親しい関係を表現しているのです。
どちらの姉妹も、イエスを喜んで迎え入れているのです。 ところが、切羽詰まって思いつめていたマルタは、ついついマリアの姿に心が破れてしまいます。 「主よ、わたしの姉妹はわたしだけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。 手伝ってくれるようにおっしゃってください。」 とても、客人に対して語る言葉とは思えません。 マルタとイエスの関係の近さを感じさせます。 これに対するイエスの言葉です。 「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。 しかし、必要なことはただひとつだけである。」 「マルタ、マルタ」という二度の呼びかけに、親のようなイエスの思いやりを感じます。 イエスは、今日食べる物がない、明日着る物がない厳しい状態にある人たちに向けて、「命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。」と言われました。 究極の選択とも言える驚きの言葉です。 「思い悩む」とは、自分の力でどうしたらやっていけるのかと考えることでしょう。 自分の経験、知恵や知識、自分がもっているものを見つめて、どうしたらこの場を乗り越えていけるだろうかという行き詰まりの状態を言うのでしょう。 しかし、私たちには、自分の力だけではどうすることもできないことがあります。 思い悩んでも仕方のないことがあります。 ある意味、思い悩むことができるのは幸いなことであるかもしれません。 一羽の雀でさえ、神なしでは地に落ちることはない。 一本の髪の毛でさえも忘れ去られることはないとイエスはおっしゃっています。 「多くのこと」があるかもしれない。 しかし、必要なことは「ただ一つのこと」である。 「幸いなのは、神の言葉を聞き、それを守る人である」と、イエスは言います。 神のみ言葉を聴くためには、恥ずかしくとも醜くともありのままの姿をもって神の前に出て行かなければなりません。 「守る」とは、行いのことではなく、神のみ言葉を宿して、神のみ心の内に歩ませてくださいと祈ることでしょう。 ここまで導いてくださった主イエスに信頼し身を委ねて、共に生きていこうと小さな決断を繰り返していくことでしょう。 イエスは、「マリアは良い方を選んだ。 それを取り上げてはならない。」と言われました。 マルタの呼びかけに、この小さな家庭に入って行かれたのはイエスの方からです。 この家庭に、それぞれの家族に、ふさわしい恵みと祝福と救いを与えるためです。 イエスは喜んで、マルタのもてなしもマリアのもてなしも受け入れてくださったのです。 イエスはマルタに、「必要な一つだけのこと」とは、父なる神が選んで準備してくださったものを自ら決断して受け取ることだと喜んで招いておられるのです。
「恐るべき者は」 マタイによる福音書10章26~31節
聖書箇所に出てくる3回の「恐れるな」という言葉と、1回の「恐れなさい」というみ言葉から、イエスの励ましと力とご愛を頂きたいと願います。 イエスは、群衆が「飼い主のいない羊」のように弱り果て、打ちひしがれているのをご覧になって、深く憐れんでおられました。 そして、弟子たちに力をお授けになり、汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すために、12人の使徒を選んでこの世に送り出されました。 イエスは彼らに、「この世の人々を恐れてはならない。」 「体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。」と励まします。 イエスご自身が表現されたように、愛する弟子たちをこの世に送り出すのは、「狼の群れに羊を送り込むようなもの」でした。 恐れと不安の中にある弟子たちの状態を十分知り尽くしたうえで、恐れても仕方のない弟子たちに「恐れてはならない」と励ましておられるのです。 その理由は、「1アサリオンで売られている庭の雀の一羽さえ、あなたがたの父のお許しがなければ、地に落ちることはない」からだ。 「あなたがたの髪の毛までも一本残らず数えられている」からだと言われるのです。 小さな存在の一羽の雀、一本の髪の毛もまた、父なる神のお許しの中にあることだから、あなたがたは「恐れる」理由がないと言っておられるのです。 私たちは何かにつけ、恐れや不安を抱く者です。 人に頼り、神に頼り、支えられてやっとの思いで今ある存在であることを十分知っています。 自分の力で、自分の知恵で、自分の才覚で、今を生きているのではないことを知れば知るほど、神なしでは恐れや不安や心配が起こってくるでしょう。 なればこそ、この恐れと不安と心配を超えた、「わたしがともにいる。 恐れるな。」と言われるお方への祈りと信仰が益々起こされていくのではないでしょうか。 この「恐れるな」という呼びかけには、「この方がおられるのなら、一羽の雀でさえ地に落ちることはない。 一本の髪の毛でさえ忘れ去られることはない。」とイエスが言われるお方こそ、「本当に畏れるべきお方」、魂も体も滅ぼすことができるすべての権威と力をもっておられるお方なのではないでしょうか。 そのお方がこのような小さな存在である「私」のうえにも共にいてくださるという驚きにも似た「畏怖」に導かれるようにとイエスの熱情が込められています。
「恐れてはならないもの」と「信頼と感謝と驚きをもって畏れるべきもの」を示して、弟子たちを世に送り出すに際して憐れみと励ましをもって語っておられるのです。 神の業、神のご計画は、私たちにとって予測不能です。 ですから、神を信じることのできない人々には、神の起こされる出来事は「恐怖」でしょう。 しかし、神を信じることのできる人々には、とめどもないものに触れた「驚きと喜びの畏怖」となるでしょう。 イエスは、「あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。 わたしは世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。」と約束されています。 パウロがローマに向かって船出した時のことです。 暴風に襲われ、今にも船が難破しようかというその時です。 恐れと不安と心配が渦巻く船の中で、パウロに届いた神の言葉です。 「パウロ、恐れるな。 あなたにはしなければならないことがある。 わたしはそれをあなたに託している。 そのために、一緒に船による航海をしているすべての者をあなたに任せたのだ。」 この呼びかけを受けて、恐れと不安と心配に覆われた船の中の人々に対して語ったパウロの言葉です。 「わたしは神を信じます。 そのとおりになります。 わたしたちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。 船は失うが、誰一人として命を失う者はない。」 私たちの小さな群れに、おいでになってくださる神を仰いで、「驚きと喜びと感謝の畏怖」の声をご一緒に挙げたいと願います。
「この世で戻る場所」 使徒言行録4章23~31節
今までびくびくして片隅の部屋に閉じこもる小さな存在であった弟子たちは、様変わりの堂々とした姿を見せています。 エルサレム神殿の境内に運ばれてきた、生まれながら足の不自由な男をペトロとヨハネはじっと見て、「わたしたちを見なさい。 わたしには金や銀はないが、持っているものをあげよう。 ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。」と、彼の右手を取って立ち上がらせたのです。 「イエス・キリストの名によって」とは、イエス・キリストの力を呼び出すことによってということです。 当時のユダヤ社会では、名前こそその人の権威、力、人格の象徴でした。 その立ち直った男がペトロとヨハネに付きまとっている姿を示しながら、二人は「生まれながら足の不自由なこの人が歩き回ったり、踊ったりして神を賛美しているのは、イエス・キリストの名によって救われたのです。 これはその名を信じる信仰によるものです。」と大胆に語り出したのです。 これを知ったユダヤの指導者たちは束になって、この二人を捕らえて牢に入れます。 二人に尋問と警告を与えるためです。 人々の病いを癒す、神殿で教える、そして、ユダヤの指導者たちに問い詰められる。 この姿こそ、まさにイエスご自身の姿です。 その尋問に、「わたしたちが彼の病いを治したわけではない。 イエス・キリストご自身がなさったことである。 あなたがたが十字架で殺したイエス・キリストが、神によってよみがえらされて今も働いておられる。」と大胆に語ったのでした。 どう処罰してよいか分からなかったユダヤの指導者たちは、「決してイエスの名によって話したり、教えたりしないように」と命令し、脅して釈放したのです。
その釈放された二人が先ず赴いたところが、仲間のいるところでした。 一同がひとつとなって集まって祈っていたところ、一人一人の上に聖霊が降り語るべき言葉が与えられたところです。 釈放されたペトロとヨハネが先ず行ったことは、「厳しい尋問に晒された時にも、わたしたちは、見たことや聞いたことを話さないではおれないのですと答えた。」という「証し」でしょう。 「何の権威で、だれの名によってするのかと問われて、イエス・キリストの名によってと答えた。 イエスこそメシアである。 ほかのだれによっても救いは得られないと答えた」という「証し」でしょう。 自分たちが受けたこと、命令されたことの一部始終を「残らず」語り、その苦しみと喜びを分かち合ったことです。 その「証し」を聞いた仲間たちも、戻って来てよかったと釈放された二人を迎えたのではありません。 「仲間たちが心を一つにし、神に向かって声をあげた」と言います。 「あなたは全地の造り主です。 あなたが預言者たちを通して語られたみ言葉通り、御手と御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ってくださった」と、確信をもって神に信頼の喜びの声をあげたのです。 精いっぱいの信仰告白です。 これに神は応えて、「主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、わたしたちが思い切って大胆にみ言葉を語ることができるように。」という「祈り」を彼らに与えられたのです。 自分たちを危険から守ってくださいとか、どうしたらよいのでしょうかという「祈り」ではありません。 「大胆にみ言葉を語ることができるように。 イエス・キリストの名によって病気が癒され、しるしと不思議な業が行われるように」と期待して祈っているのです。 この「祈り」が終ると、「一同の集まっていた場所が揺り動いた。」と言います。 この喜びは、神のご計画がこの自分たちのうえにイエス・キリストの名によって刻まれようとしている喜びです。 そのために「信仰」と「祈り」が必ず与えられるのです。 戻って行く場所があるのです。 そのことに感謝して、「信仰」が与えられるよう、「祈り」が与えられるよう、神に向かって「信仰」と「祈り」の声を一緒にあげているのです。
「交わりの回復」 使徒言行録2章1~13節
聖霊が降ってきた時の情景が記されています。 よみがえられたイエスが再三弟子たちにご自身が生きておられることをお示しになった際に、「前にわたしから聞いた、神の約束されたものを待ちなさい。 あなたがたは間もなく聖霊によるバプテスマを授けられる。」と言われていました。 その弟子たち「一同が一つとなって集まって祈っていたところ」です。 その弟子たち一人一人の上に言葉では表現しようのないものがとどまり、約束されていた賜物、聖霊に満たされたと言うのです。 すると、今まで自分たちの部屋に鍵をかけて祈り合っていた弟子たちが、鍵を開けて、自ら扉を開けて、今まで恐れていたエルサレムの外に向かって動き出した。 その聖霊が語らせるままに、自分たちが使っていた言葉ではない新しい言葉を語り出したと言うのです。 自分の故郷の言葉しか話すことのできなかった弟子たちが、世界に散らされていた神の民に向けて、それぞれが聞き届けることができるほどの新しい言葉をもって語り出した。 ひとつとなって祈り集まっている弟子たち一同のもとに、神が約束された聖霊を降され、彼らを用いて、今までまったく遮断されていた部屋の外に向かって、授けられた新しい言葉によって神の業を伝える「交わり」を取り戻していく出来事が起こされたと言うのです。
言葉は、人と人との大事な「交わり」を支えるにしても、壊すにしても大きな役割を果たします。 創世記に出てくるわずか20行の短い「バベルの塔」の出来事を思い起こします。 その当時、「世界中は同じ言葉を使っていた」と言います。 「移動してきた人々が、そこに住み着いた。 様々なものを見つけ出し、それを用いる技術も手に入れた。 そこに定住し、町を皆で築き上げるまでになった。 神との交わりを象徴する高い塔を立て上げた。 文明も知識も仕組みも整えられた。 次第に人々は誇りをもつようになっていった。」 「もっと有名になろう。 全地に散らされることのないようにしよう。 天まで届く塔のある町にしよう。」と言うまでになった。 自分たちが胸を張って誇れるようになりたい。 これで安心だと頼れるものがほしい。 どのようなことになっても拠り所となるものがこの町にほしい。 これが「バベルの塔」の建設です。 神はこの有様をご覧になって、憐れに思われて、降って来てくださって彼らが語る言葉に混乱を与え、互いの言葉が聞き分けられないようにして、そこから彼らを全地に散らされたのでした。 時が経って、今朝の聖書箇所です。 十字架によってイエスを失い途方に暮れて、心がバラナラになって、エルサレムの片隅に閉じこもっていた弱い、力のない、小さな存在であった弟子たちが、神によって再び集められ、神の群れとされたのです。 各地に散らされていた神の民の群れが祭りを通してエルサレムに集められたのです。 弟子たちには、今までとは異なる新しい言葉が聖霊に導かれて与えられたのでした。 聞く側の人々もまた、弟子たちに授けられた神によって与えられた言葉を聞く力を与えられたのでした。 言葉を語る者にも、言葉を聞く者にも神が働かれたのです。 神との「交わり」を再び取り戻すために、弟子たちの「交わり」が回復されるために、散らされていたはずの人々と弟子たちとの「交わり」が回復されるために、この出来事が起こされたと聖書は語ります。 「天まで届く塔」とは、自分たちが神によって造られたことを忘れて、私たちに恵みとして与えられたものを自分たちの安心のために用いようとしたしるしです。 自分たちが神にとって替わる拠り所を自分たちがつくり上げようとしたものです。 神は、この「神なき交わり」を完全に破壊されたのです。 神との「交わり」こそが、人と人との「交わり」をつくり上げることを思い起こさせようとされたのです。 このイエスの働きが弟子たちに引き継がれたのが、ペンテコステの出来事です。
「創造される清い心」 詩編51編3~14節
このダビデの「嘆きの祈り」には、サムエル記下11章および12章に記されている背景があります。 王であるダビデがその家臣、全軍を戦いのために戦地に送り出した。 自身は、エルサレムに留まっていた。 家臣であったウリヤの妻バト・シェバの姿に、ダビデは目を染めて王宮に召し入れた。 その後、ダビデは王の権威をもって、「激しい戦いの最前線に家臣ウリヤを送り出し、彼をそこに残して、軍を退却させ、ウリヤを戦死させよ」という卑劣な命令を降すのです。 ダビデの思惑通り、家臣ウリヤを死なせたと言います。 そして、ダビデはウリヤの妻バト・シェバを王宮に引き取り、自分の妻とし思いを遂げるのです。 聖書はこのことをはっきりと、「ダビデのしたことは、主の御心に適わなかった。 主は、預言者ナタンをダビデのもとに遣わされた。 主はナタンを通して、ダビデを激しく叱責した。 なぜ、主の言葉を侮り、わたしの意を背くことをしたのか。 あなたは隠れてこのことを行ったが、わたしは白日のもとにさらす。」と単刀直入にダビデに指摘したのです。 ダビデはこれに、「わたしは主に罪を犯しました。」と深く悔いています。 なぜダビデがこのような「祈り」をささげるようになったのかとその原因を探るより、この「嘆きの祈り」にある主を仰いで祈る「祈り」に合わせて、私たち自身が祈る「祈り」が与えられることを願いたいと思います。
私たちは、自分の犯した過ちを何とか正当化しようとします。 少しでも責任を軽くしよう、免れようと努めます。 これでいいと、自分を納得させようとします。 ダビデはそうではありません。 自分自身が犯した過ちは、神の目だけには明白である。 責任を免れ得ない、時を遡ってもう一度やり直しをしたいといった願いではなく、取り返しのつかないものであると告白します。 そのうえで、「神よ、わたしを慈しみをもって憐れんでください。 背きの罪をぬぐってください。」と、神の赦しがあること、救いがあることに望みを抱いて、神の憐れみと慈しみにすがろうと懸命に祈っているのです。 「憐れんでください。 ぬぐってください。 清めてください。 払ってください。 洗ってください。」と、表現はまちまちですが繰り返しています。 自分が犯した過ちを口に出して、神の前に差し出して、赦しと救いを願い出るということは、だれにも見せたくない恥ずかしいことです。 自分ではぬぐうことのできないことであると認めて差し出す勇気のいることです。 人は人知れずきれいになって、何事もなかったかのように振る舞いたいのです。 自分で洗って、もう一度やり直しがしたいのです。 自分の恥ずかしいところを認めて、さらけ出して、自分でぬぐうことができないことを認めて、神に助けを求めている。 これがダビデの「嘆きの祈り」です。 神の求められるものは打ち砕かれた霊。 神は、打ち砕かれ悔いる心を侮られません。」と確信して祈る「祈り」です。 神はこの赤裸々なダビデの「祈り」をどれほど喜んでおられるでしょうか。 ダビデは、「神よ、わたしの内に清い心を創造してください。」と祈っています。 もとのきれいなものに戻してくださいとは祈っていないのです。 「神よ、新しく確かな霊を授けてください。」と、神にしかできないこと、神から与えられなければできないことを「創造してください」と祈っているのです。 ダビデの「祈り」は後悔や懺悔の「祈り」ではありません。 新しく造り変えられることを望む「祈り」です。 今まで見えていなかった、聞くことのできなかった方向に向きを変えて、新しく生きていこうとする「祈り」です。 悔い改めは反省や後悔ではありません。 神によって授けられる「祈り」です。 神のもとから遣わされた主イエスに結ばれて、よりすがって、造り変えられて生きていこうとする「祈り」の姿です。
「命の選択の決断」 ヨハネによる福音書15章1~5節 申命記30章15~20節
私たちが行う選択には、「判断」と「決断」があります。 私たちはできるだけ正しい「判断」をしようと、理解し納得することができるよう奔走します。 しかし、コロナに象徴されるように何がいったい正しい「判断」なのか分からない、100%信じ切るものさしなどない中で生きていかなければならない時があります。 「判断」できない中で、それでも踏み出すのか留まるのか、その「決断」を迫られる時があります。 「決断」すべき時に、正しい「判断」を求めて逡巡し「決断」できない時があります。 そこには、手っ取り早いマニュアルの答えなどないのです。 「隠されている事柄は、主のもとにある。 しかし、啓示されたことは、我々と我々の子孫のもとにとこしえに託されており、この律法の言葉をすべて行うことである。」(申命記29:28)とあるように、神を信じるという「決断」に委ねて生きることができる恵みが私たちに与えられているのです。
モーセはその人生の最後に、40年もの間、エジプトから奴隷の身であった大勢のイスラエルの人々を引き連れて、荒れ野の旅を終え、いよいよヨルダン川を渡り、その向こう側にある新しい約束の地に入って行こうとする時に、人々にこう語りかけるのです。 「見よ、わたしは今日、命と幸い、死と災いをあなたの前に置く。 あなたの神、主を愛し、その道に従って歩み、その戒めと掟と法を守るならば、命を得る。 あなたは祝福される。 あなたは命を選び、命を得るようにし、あなたの神、主を愛し、御声を聞き、主につき従いなさい。」と語ります。 私たちの前には、「生と死、祝福と呪い」と思われるものが置かれる。 どちらも選び取ることができるし、そのことが赦されている。 しかし、神は「命を選び取るように、命を得るように」と言われる。 私たちは、神が祝福し喜んでくださることを選び取るはずです。 しかし、「死や呪いや災い」は、見たくもない姿をとって現れ出てこない。 人目をひく魅力をもってすり寄ってくる。 もっともらしい正しさをとって近づいてくるのです。 一方、「生や祝福や幸い」もまた、私たちの目には喜ばしい姿をとって見えてこないのです。 私たちの覚つかない「判断」だけでは、神の望んでおられる道を誤って選び取ってしまうのです。 よく考えてみてください。 神は私たちの前に置くべきものを、もうすでに選んで置いてくださっているのです。 私たちが選択する前に、神が責任をもって、神の強い意志と願いによって神の選択が施されているのです。 置かれているものを、私たちがどう受け取っていくのかが私たちの選択です。 うまくいっている時には神に選ばれた民として誇り、いざうまくいかなくなった時にはこの世の力に頼ってしまうイスラエルの人々と同じように、私たちは愚かさをもっています。 それでも神はこのような私たちを憐れんで、私たちにふさわしいものを置いて、それに対する応答、信仰の「決断」を待っておられるのです。 様々な私たちの小さな「決断」の積み重ねが、神によって引き起こされているのです。 私たちの人生は、神が用意してくださっている道のりに、私たちが何らかの応えをもって選びとっている厳粛な道のりです。 「神の準備」と「神の呼びかけに対する私たちの応答」から織りなす道のりです。 そこには、神の深い憐れみと強い願いがある。 神が準備しておられる命の世界があるのです。 それがどのようなものであったとしても、信仰という「決断」をもって喜んで応えて扉を開けるのです。 この私たちの「決断」は一回だけのものではありません。 この世にある限り、日々の「決断」の繰り返しです。 イエスはそのことを、「わたしに留まりなさい。 わたしはまことのぶどうの木、あなたがたはその枝である。 わたしの父である神は農夫である。 わたしを離れては、あなたがたは何もできない。」と言われます。
「ガリラヤ湖畔の野原での祝福」 ヨハネによる福音書6章1~13節
有名な「五千人に食べ物を与える」という、すべての福音書に記されている聖書箇所です。 よほど、弟子たちの心に刻まれた出来事であったのでしょう。 その場所は、イエスがガリラヤ湖畔の山に登り、弟子たちとともにお座りになった、草がたくさん生えていた野原であったと言います。 のどかな風景が目に浮かびます。 イエスを仰いで、弟子たちが、群衆がそこで安らぎをもってイエスの言葉に耳を傾けていたのでしょう。 大勢の群衆が自分たちの方へ近づいてくるのをイエスはご覧になって、「この人たちに食べさせるには、どこでパンを買えばよいだろうか」と言われた。 イエスはこれからなさろうとしていることを分かっておられて、弟子のフィリポを試されたと言います。 その群衆の数は、男たちだけで五千人であったと言いますから、フィリポは常識通り、「めいめいが少しずつ食べるだけでも相当なパンが必要です。 この数の人を養うだけのパンはありません。」と答えるのが精いっぱいであったでしょう。 弟子のアンデレが思わず、「ここに大麦のパン五つと魚二匹とを持っている少年がいます。 けれども、こんなに大勢の人では、何の役にも立たないでしょう。」と叫びます。 大麦のパンとは、粗末な食べ物のしるしでしょう。 五つのパンと二匹の魚も、少ない数のしるしでしょう。 少年という姿もまた、小さな存在ということでしょう。 しかし、イエスはそのパンを座っている群衆に分け与え、魚も同じように欲しいだけ分け与えられた。 そして、「少しも無駄にならないように、残ったパンの屑を集めなさい」と言われたと言います。 そこで考えられないことが起きたのです。 群衆は満腹となった。 食べ残ったパンの屑を集めると、十二のかごがいっぱいになったと言います。 群衆は、イエスのなさったしるしを見て、「まさにこの人こそ、世に来られる預言者である」と言ったと記されています。
この出来事が記された中に、ふたつの文章が心に残ります。 ひとつは、「ユダヤ人の祭りである過越祭が近づいた」という文章と、「イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから」という文章です。 この出来事とエルサレムで国を挙げて執り行われる過越祭とどのような関係があるのだろうか。 また、私たちが主の晩餐の際に行われているようなイエスの振る舞いが、なぜここに記されているのでしょうか。 神はモーセに、エジプト全土にひとつの災いをくだし滅ぼすと言われました。 エジプトにあるものすべてを区別なく撃つと言われました。 そうならないように、神はモーセにイスラエルの人々の家の柱と鴨居に小羊の血を塗るようにと言われました。 イスラエルの家に塗られた血がしるしとなって、この災いがその家を過越し、及ばないと約束されたのです。 神がすべてのものを滅ぼそうとされたが、そうならないようにと柱と鴨居に小羊の血を塗って「辛うじて救い出された」喜びを記念して、エルサレムで人々が祝っているのが過越祭です。 群衆は、イエスのしるしを見たからこの野原に近づいてきたのです。 その群衆を前にして、今、エルサレムの立派な神殿、整備された儀式もないけれども、このガリラヤ湖畔ののどかな野原で大勢の群衆に囲まれて、イエスはこの過越の祭りをともに祝うことを喜びとされたのではないでしょうか。 本来滅ぼされても仕方のない私たちが、イエスの贖いの十字架の血によって神の災いがここにいる群衆の上にも通り過ごされていくことを、「感謝の祈りを唱え」喜びをともにされたのではないでしょうか。 何もない、エルサレムから遠く離れたこの「草がたくさん生えていた野原」で、何千年も前の出来事と同じように、今、ここに訪れようとしているこの喜びをイエスは噛みしめておられるのではないでしょうか。 私たちもまた、イエスに出会って、そのご愛に触れて、赦されることのない過ちが赦されて、そのご愛に満たされる神の国の一員であるのです。
「神の愛に気づきなさい」 ルカによる福音書10章25~37節
「律法の専門家」が立ち上がり、イエスを試そうとしたと言います。 「何をしたら、永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか」 イエスに挑んだ「律法の専門家」が逆に、「律法に何と書いてあるか」と問い返されます。 仕方なく答えざるを得なくなった「律法の専門家」は、「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。 また、隣人を自分のように愛しなさい。」と律法に書いてあると胸を張ります。 イエスは同時に、「あなたはそれをどう読んでいるか」と尋ねているのです。 「あなたはそれを読んで、どう分かって、その戒めに沿ってどのように生きているのか」とその生き方に目を向けさせます。 「律法の専門家」は、自分の生き方から目をそらし、解釈の問題として「では、わたしの隣人とはだれですか」と尋ね返すのです。 その時にイエスが、この「善いサマリア人」の譬えを語られたのです。
私たちは、だれかを愛そうと決意して愛していこうとしても難しい。 頑張ってみても長続きしないこともよく分かっています。 「愛」は、私たちの意志によってコントロールできるものではありません。 聖書には、私たちが持ち合わせている「愛」のほかに、相手本位としか言いようのない、無条件の「愛」が区別された言葉で用いられています。 それが、神によってしか与えられない「神の愛」です。 この愛に満たされるなら、私たちの愛の貧しさをとことん知らされます。 自分が決意して築き上げるようなものではないことを知らされます。 自分の中にないこの愛に触れるなら、私たちは驚きと喜びと感謝に満たされます。 マザーテレサがこの神の愛をこう語っています。 「神は愛であり、愛は神から来るのですから、愛には限界がありません。 ですから、神の愛のうちに本当に身を置きさえすれば、神の愛に尽きることはありません。 肝心なのは愛することです。 傷つくまで与え尽くすことです。 どれだけのことをしたかではなく、あなたの行いに神から与えられた愛を込めたかなのです。」と言っています。 「傷つくまで」とは、その相手の人の痛みや悲しみや苦しみを自分のものとするということでしょう。 この「譬え」に出てくるサマリア人は、「その人を憐れに思い」と記されています。 この言葉が、同情するとか、かわいそうだと思ったとかを遥かに超えて、「はらわたがちぎれるほどの痛み、苦しみ」を受け止めたということです。 イエスが私たちの痛みや苦しみや悲しみをご自分のものとされた時に用いられた言葉です。 当時はユダヤ人とサマリア人は犬猿の仲でした。 決して互いに交わることなどない関係でした。 だれしも、「道の向こう側を通り過ごしていく」のが、当たり前のところで、「追いはぎに襲われた人」が思いがけない人の助けを得た。 考えてもみなかった人から助けられた。 社会的な慣習には縛られない「憐れに思った」相手本位の無条件の憐れみが、そのサマリア人の原動力でした。 イエスは「善いサマリア人」の譬えで、無条件の、恵みとしか言いようのない父なる神の愛が、だれも見向きもしないところに働いたと言っているのです。 その神の愛に満たされたのなら、「行って、あなたも同じようにその愛を注ぎなさい」と送り出しておられるのです。 イエスを試そうとした「律法の専門家」に、戒めに記されている「愛しなさい」という定めを自分の愛によって満たそうとしている「律法の専門家」に、神の愛に触れてみなさい。 自分で築き上げる「愛」の貧しさに気づきなさい。 私たちの痛みや苦しみや悲しみを自分のものとして受け取ってくださる神の愛に触れるなら、自分もまた神の愛に触れるために、「隣人」の痛みや苦しみや悲しみもまた、神の愛が注がれるものしてと受け止められるはずである。 神の愛を祈り求めるよう、送り出してくださっているのです。
「イエスの復活を信じるトマス」 ヨハネによる福音書20章24~29節
トマスは、疑り深い弟子の代表として描かれています。 死んだはずのイエスがよみがえったなど、見ていないので信じることができなかったトマスは「イエスの手に釘の跡を見、この指をその釘跡に入れてみなければ、また、この手をそのわき腹に入れてみなければ、わたしは決して信じない。」と仲間の弟子たちに訴えた人物です。 最初のイースターの日の夕方のことです。 仲間の弟子たちがユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけて閉じこもっていたところへ、十字架に架けられて死んだはずのイエスが現れたと言います。 入り込む余地のない所に、死んだはずのイエスが現れた。 自分たちの目で墓の中に、イエスの遺体がないことを目の当たりにしても、またマリアの「わたしは主を見ました。」という証言を耳にしても、イエスが生きていると信じることのできなかった弟子たちの真ん中に、イエスは立たれた。 そして、「あなたがたに平和があるように」と言われ、傷跡の残る手とわき腹をお見せになったと言います。 「あなたがたに平和があるように」とは、争いがなくなるようにというようなことではありません。 父なる神との正しい関係が、交わりが取り戻されるようにということです。 忘れてしまっていた神との交わり、そのような交わりがあることさえ知らなかった者に神との交わりが回復されるようにということです。
これが最初のイースターの夕方の光景です。 トマスは、そこにはいなかったのです。 よみがえられたイエスを目の当たりにした仲間の弟子たちは「主を見て喜んだ」のです。 思いもかけない驚きと喜びに満たされて、興奮して、「わたしたちは主を見た。」と証ししたのです。 イエスが「わたしは必ず復活することになる」と言われていたことを思い起こして、元気と希望を取り戻したのです。 それらの様変わりした仲間の弟子たちの姿を見たトマスは、自分だけが出会っていない。 見ていない。 信じ切ることのできない自分の姿を見つめさせられていたのではないでしょうか。 その思いの凝縮したトマスの言葉が、「イエスの手に釘の跡を見、この指をその釘跡に入れてみなければ、また、この手をそのわき腹に入れてみなければ、わたしは決して信じない。」という叫びになったのではないか。 この言葉の響きには、なぜ自分だけが取り残されているのか。 その理由が分からない、群れの中に居場所がないというトマスの痛みと悲しみを憶えます。 その一週間後です。 イースターの日と同じように、トマスのために最初の時と同じようにイエスが現れ、「あなたの指をここに当てて、わたしの手を見なさい。 また、あなたの手を伸ばし、わたしのわき腹に入れなさい。」と呼びかけてくださったのです。 トマスは、イエスの手とわき腹に傷跡があることを確認したかったのではありません。 他の弟子たちと同じように、自分をお忘れになってはおられなかったことを確認したかったのです。 この群れの仲間と同じように、自分もまた愛されている、この群れの中にいることを赦されている、イエスに捉えられていることを確認することができたのです。 そこで発せられたトマスの「わたしの主、わたしの神」という告白が、トマスの口からほとばしり出たのです。 「あなたはわたしと同じ人間としての苦しみを味わってくださった主であった。 そして、霊なる命に生きる神なるお方となってくださった。 人間の肉体をもって味わってくださったイエスが、目の前におられる復活されたイエス・キリストとなってくださったという、精いっぱいのトマスの告白です。 イエスは「指を入れてみなければ、手を入れてみなければ信じない」と言っていたトマスのこの告白を聞いて、「見ないで信じる人は、幸いである」と、変えられたトマスを最大限祝福されたのではないでしょうか。
「わたしたちの救い主」 イザヤ書53章1~12節
イザヤ書53章は、「苦難の僕」という歌、詩です。 バビロンにイスラエルの人々が捕らえられていた時期に活動した無名の預言者、第二イザヤが記したものです。 バビロンに囚われている時期のイスラエルの民が味わっているこの苦難は、いったいどこからきているのか。 それは神の罰である、神の教えであると、イスラエルの人々は思っていた。 異国の王、ペルシャ王キュロスの手によってバビロンが崩壊して、自分たちが解放されることになったことにより、キュロス王こそ自分たちを解放してくれる救い主だと思った時期があった。 しかし、この政治的、軍事的なメシアが自分たちを救ってくれるという希望が、不毛な戦いとその悲惨な結果によって諦めと絶望に襲われていた時です。 なぜ神に愛され、選び出された自分たちが、このような苦難に遭わなければならないのかと苦しんでいた時です。 この苦難の意味が、第二イザヤによって示されたのです。 自分たちが味わっている苦難こそ、これから訪れようとする神の恵みの世界を現れ出すものである。 無力で、貧しく、虐げられている自分たちの無言の忍耐と犠牲によって、神の憐れみの世界、恵みの世界がつくり上げられていくという贖罪の苦難がここにはあると四回にもわたって繰り返し、「苦難の僕」という姿を通して預言したのです。
このみ言葉を鋭く目に留めて、地上での生き方を定めたお方が救い主イエス・キリストです。 イエスは、「わたしは、仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を献げるために来たのである。 異邦人の間では、支配者と見なされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。 しかし、あなたがたの間では、そうではない。 あなたがたの中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、いちばん上になりたい者は、すべての人の僕となりなさい。」(マルコ10:42-45)と言われました。 私たちは少しでも高く見られたい。 人の評価に振り回され、神経をすり減らす者です。 あくまでも自分が主人で、神でさえも自分の奴隷として利用しようとまでするのです。 しかし、イエスはこの「苦難の僕」のみ言葉に聴いて、父なる神のみ心を見て取ったのです。 私たちの病い、痛み、背き、咎のために、これからご自身が受ける傷、軽蔑、侮辱、見捨てられること、葬り去られることによって、人々に「平和が与えられる」 「人々が癒される」ことを読み取ったのです。 聖書の言う「平和」とは、争いが起きていないとか、平和宣言がなされているとか、武器がなくなるとかということではありません。 「平和が与えられる」とは、神との正しい関係、交わりが取り戻されるということです。 神との和解ということです。 忘れてしまっていた神との交わり、そのような交わりがあることさえ知らなかった者に神との交わりが回復されるということです。 「わたしは、すべての人の僕となるために、神とすべての人との和解のために遣わされた。 多くの人々が、神の赦しがあることを知るため、そして、赦されることによって命そのものが癒され、神のもとに取り戻されるために遣わされた。」と言われたのです。 最後の晩餐でご自身がパンを裂いて杯を配られたのも、五千人にパンと魚を配られたのも、ご自身のからだをささげてこの世に「イエス・キリストによって結ばれたひとつのからだ」をつくり上げるためであったのです。 私たちは、このお方を救い主として何の資格もなくいただいた者です。 このお方が私たちと一緒にいてくださる。 わたしたちの僕となって仕えて、とりなしてくださっている。 そのためにご自身の命をささげたと言われているのです。 イースターを迎え、ご自身の十字架を背負って歩まれ、「復活の道」を切り開いてくださった主イエスをしっかりと仰いで参りたいと思います。
« Older Entries Newer Entries »