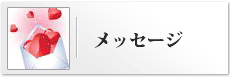「いつも父と一緒にいる息子」 ルカによる福音書15章25~32節
遠い国に旅立ち、放蕩の限りを尽くして困窮に至った「我に返った弟息子」こそ、「悔い改めるひとりの罪人」です。 元の父親のところに戻っていく「方向転換、悔い改め」です。 「もう息子と呼ばれる資格はありません」と、弟息子は今の「ありのままの自分」をさらけ出して、元々あった「自分」に立ち帰ろうとしたのです。 しかし、この場に及んで「雇い人の一人にしてください」と、条件をつけて父親との関係を取り戻そうとする。 せっかく見つめた「ありのままの自分」を、「雇い人のひとり」という「自分」を造り上げ覆い隠して、条件をつけて父親の憐れみを受け取ろうとするのです。 しかし、父親の姿は元の姿のままで、弟息子が条件付きの「自分」を差し出す前に、何ら条件もつけず赦し、自分と同じ家の者として装わせ、その喜びを全面に出して祝宴までも始めるのです。 弟息子はありのままの罪深さを覆い隠すために、もうひとつの「つくりものの自分」を作り直して「安心」を求めるのです。 「安心」とは自分のコントロール下にある一時的な心のゆとりでしょう。 聖書が語る「平安」は、すべてのことやものが神の支配のもとにあるという信頼、その父なる神と結ばれているという霊的なつながりの確信でしょう。 「ありのままの自分」をもって神の前に恐れず進み出るなら、思いもよらない無条件の愛に圧倒され、喜びの涙をもって一瞬のうちに心は砕けるのです。 主イエスは、弟息子の姿を通して「徴税人や罪人たち」に、父なる神から離れることがないようにと、見つけ出され元へ取り戻された失われた存在こそ、父なる神の大きな喜びであると語りかける。 この弟息子とは全く対照的な兄息子の姿を通して、「ファリサイ派の人々と律法学者たち」にも同じように、神に従っているつもりでも実は神のみ心から離れてしまっていることに気づくようにと、一緒に失われた者の回復を喜ぶようにと語りかけるのです。 兄息子は終始父親のそばにいて、「父の言いつけに背いたことは一度もありません。」と言い切るほど父親に一貫して忠実でした。 自分勝手に父の家を出て行って前触れもなく帰ってきた弟を父親が無条件に赦し、元のまま父の家の一人として迎え入れたことに兄は怒って、父の家に入ろうとしない。 父親は、弟に対し「見つけて憐れに思い、走り寄ってきた」と同じように、兄に対しても「家を出て行ってなだめた」と言います。 兄は、「お父さんに忠実に仕え長年我慢してきたことが、今や報われていない」と憤りを顕わにするのです。 息子と父親という関係ではなく、まるで主人と奴隷関係であるかのようです。 「従順な息子」という自分が造り上げた「偽りの自分」を演じてきたのでしょう。 ここに至って、父親の思いとの決定的な隔たりが生じ、父の家に入ることができなくなったのです。 父親は「子よ、お前はいつもわたしと一緒にいる」と、弟が帰ってきたからといって兄に対し態度を変えたわけではない。 むしろ、兄と父親の今までの関係の「ありのままの姿」が浮き彫りになったのではないでしょうか。 この爆発した「怒り」こそ、自分を絶対化する位置に一時的に置いてしまうのです。 「ファリサイ派の人々や律法学者たち」こそ、神を神とし、誰よりも真剣に考え行動し、その熱心さが嵩じて怒りへと沸騰し、自らを絶対者の立場に押し上げてきた人たちでしょう。 兄息子は、父の思いは二の次で、自分が貫いてきた自分の誇りが第一でしょう。 父親は悔い改めて戻ってきた弟にも、弟を家族として認めようとしない兄にも、共にいて二人を支え、見えていない二人の暗闇を照らす光なのではないでしょうか。 父親とは父なる神であり、主イエスです。 兄と弟は混在する私たちです。 待ち受ける神ではなく、憐れみ深く出向いて来られる神を示しておられるのです。 弟は放浪の末、父の憐みのもとにある自分を見つけ出したのです。 兄は自分が父のもとで失われた者となっていたことに、これから気づかされていくのでしょう。