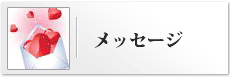「キリスト者の誇りとは」 コリントの信徒への手紙二1章12~14節
パウロは、コリントの教会の人たちとの間に発生した問題を赤裸々に語ります。 パウロが危惧したことは、パウロ個人に対する批判のことではなく、パウロが使命としている異邦人宣教として語ってきた主イエスの福音が歪められて、その福音に対する疑いが起こっていることです。 自分自身に対する弁明ではなく、福音の内容に対する誤解を解くことだけを念頭にパウロは行動したのでした。 「このような確信に支えられて、わたしはあなたがたがもう一度恵みを受けるように」と呼びかけています。 前もって書き送った「涙の手紙」により、コリント教会の人たちとの関係が好転したとは言え、今もなお完全に一つとなり得ていないコリントの教会の人たちを「あなたがた」と呼んで、パウロは個人的な私信ではなく主イエスの福音に支えられているすべての信仰者を含めて「わたしたちは」と言って呼びかけるのです。 「わたしたちは世の中にある」と言います。 教会の群れはこの世の中に存在し、決して現実の外にあるのではありません。 従って、少し気を許してしまうと、いつの間にか「世の中」と全く変わらない、人間の知恵が闊歩する事態に容易く陥るのです。 教会は神のみ心を尋ね求めながら歩む群れである。 なのに、今やコリントの教会がそうした教会であることを捨て去ろうとしている姿にパウロには映ったのでしょう。 創立に関わった指導者パウロ個人との人間関係に関わる枝葉末節の軋轢の問題ではなく、神のみ心に従った群れとして今後も存立することができるのかという問題であると見極めたのです。 パウロは、「人間の知恵によってではなく、神の恵みの下に行動してきました。」と明確に述べています。 教会は私たち人間の働きや知恵によってではない、主イエスの働きである。 その都度のご都合で自分勝手に判断し、宣教を推し進めてきたのではない。 神の憐れみ、神の赦しに支えられて、「神から受けた純真と誠実によって、神の恵みの下に行動してきました」と言うのです。 ここでパウロは「良心」という相対的な言葉をもって、「信仰そのもの、神のご真実そのものにかかわること」を忍耐しながら呼びかけるのです。 自己中心的な思いと、神のみ心に従おうとする思いの狭間で、「神の恵みの下に行動してきました。 このことは、良心も証しするところです。」と、マルティン・ルターが語る「神の言葉に縛られている良心」を痛めることなく、偽りなく語るのです。 外に現れ出てくる言葉と行動と、内に秘められている思いとが一致していないのは、今、コリントの教会を席巻している偽教師たちの方である。 正しく導いているようで、パウロ個人を無きものとし、自分たちの思いを果たそうとする巧みに人間の知恵によって生きていく生き方に、パウロは警鐘を鳴らすのです。 そして、「このことは、わたしたちの誇りです。」と言います。 「誇り」とは、その人が何を拠り所として生きているのかを示すものです。 キリスト者が避けなければならない「誇り」は、この世のこと、自分自身のことに対する「誇り」でしょう。 パウロは「誇る者は主を誇れ」と言います。 パウロ自身の「誇り」ではありません。 パウロが、コリントの教会の人たちの「誇り」、コリントの教会の人たちが、パウロの「誇り」だと言うのです。 自らの生きた足跡が実となり、「誇り」となるものが神さまから与えられる。 「終わりの日」には、完全に与えられることになる。 パウロはその照準をもって、この世の現実の今を生き、コリントの教会の人たちとの和解に向かったのです。 もし、この「誇り」を「喜び」と解するなら、パウロとコリントの教会の人たちとの関係の回復が果たされるなら、互いにその回復を導いてくださった神を喜ぶことが生まれ出てくる。 主を誇りとし、神のみ前に恥じない行動と思いをもって生きるキリスト者の誇りと喜びは、互いに反目し合っていたとしても持つことができるのではないでしょうか。