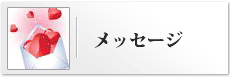「生きる望みさえ失った苦難から生まれるもの」 コリント二1章8~11節
コリントの教会の人々の深い悔い改めの後に、パウロは「和解の手紙」を記しています。 自分を裏切った人々も、自分を激しく罵った人々も赦し、同時に、和解へと導いてくださった神さまへの賛美と感謝の思いが「和解の手紙」には滲み出ています。 その手紙の一部分である今朝の聖書箇所に、パウロは「アジア州でわたしたちが被った苦難をぜひ知っていてほしい。 知らずにいてほしくない。」と言います。 使徒言行録19章に記されているエフェソでの騒動のことです。 アルテミス神殿の模型を銀で造り、利益を得ていた銀細工の職人たちが、偶像礼拝を否定するパウロたちの教えに対し激しく迫害したのです。 パウロは自身の実体験を美談として示すのではなく、むしろ、敗者としての実体験を赤裸々に語るのです。 しかし、この体験でこそ、神を頼りにすることになりました。 神がこれほど大きな死の危険からわたしたちを救ってくださったし、これからも救ってくださるにちがいないことが分かりましたと言うのです。 神のもと近くに留まるなら、測り知ることのできない神ご自身を知ることになります。 その神によって与えられる苦難や悲しみや喜びには意味があることを知らされるのです。 福音書では、「唯一のまことの神と、その神がお遣わしになったイエス・キリストを知ること、これが神によって与えられる賜物である。 永遠の命である。」と宣言されているのです。 今まで味わってきた恵みの実体験に支えられてきたパウロの、自身の使命について果たしてこれが神のみ心であるのかという信仰の根幹を揺るがす激しい葛藤であったのでしょう。 アブラハムがその息子イサクを焼き尽くす捧げものとして差し出すようにという神の命令に接したとき、また、すべてのものを奪い取られてしまったヨブが、それでも神さまへの信頼を失わず、友人や家族にまったく理解されなくとも、神のみ心だけを示してほしいと頑強に神に迫ったときのことを思い起こします。 パウロは、信仰者としての絶望を味わったのです。 問題の解決や具体的な助けを求めたのではなく、神のみ心が分からない、神から見放されてしまったのではないかという、信仰者の根本的な深刻な戦い、信仰があるがゆえの苦しみでしょう。 パウロは、これほどの苦しみを味わなければ分からないことがある、見えてこない景色、学べないことがあると分かって、「生きる望みを失った、死の宣告を受けた」と思わされるようなところからでも、「並み外れた偉大な力」によって救い出してくださるお方であることを改めて知って、このことを「知らずにいてほしくない」と赤裸々に語るのです。 私たちは苦難を求める必要はありません。 苦難そのものが問題なのではなく、苦難の中でこそ神から与えられることがあるのです。 私たちが経験したことのないパウロの経験から、パウロが「これほど大きな死の危険からわたしたちを救ってくださったし、これからも救ってくださるにちがいいないと、わたしたちは神に希望をかけています」という信仰を憶え、互いに執り成し合う祈りをささげることが赦されているのです。 私たちは苦難が臨む時、目や耳や心を目の前の苦しみに奪われてしまいます。 外的な変化ではなく、内的な変化、苦しみや悲しみそして喜びをどのように受け止めるのかによって、苦しみや悲しみそして喜びの内容が劇的に変わるのです。 「わたしたちが悩み苦しむとき、それはあなたがたの慰めと救いになります。 また、わたしたちが慰められるとき、それはあなたがたの慰めとなり、あなたがたがわたしたちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。 あなたがたについてわたしたちが抱いている希望は揺るぎません。 なぜなら、あなたがたが苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると、わたしたちは知っているからです。」(6,7)と語るパウロとコリント教会の人々の交わりの在り方のように私たちもかくありたいと願います。