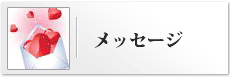「死んでいたのに、生き返ったから」 ルカによる福音書15章11~24節
人の死を「天に召される」と表現します。 私たちとは相容れない神の性質を持ちながら、私たちと全く同じからだを背負わされてこの世を歩んだイエス・キリストでした。 神のみ言葉だけを仰いで、からだが持っている「弱さ」をもちながらこの世を歩み通したお方でした。 ついに、この世のからだに死んで、「よみがえり」という父なる神が備えてくださった道を人間として初めて体験し神のもとへ帰って行かれたのでした。 キリスト者とは、このイエス・キリストに結ばれて生きる、新しく変えられた者ということです。 「死によってすべてが終る」人生から、「新しいいのち」という上着を着せられてそのままのからだで用いられ、この世に生かされていく。 「からだの死」を越えて、イエス・キリストに結ばれて「神のもとに帰っていく」人生に変えられる。 メメント・モリ(死を覚えよ)とは、この地上での歩みのために授けられて生きる「命」を覚えよ。 その背後にある「神のご愛」を覚えよということです。 「放蕩息子のたとえ」に、独りで自分の思い通りの人生を送ろうと父の家を飛び出した弟息子の悔い改めが語られています。 自分に分け与えられた財産を使い果たし、食べることにも窮するまでになってしまった。 孤独になった放蕩息子は「我に返った」とあります。 父の息子であったという当たり前と思っていた恵みを捨ててしまった、忘れてしまった思い違いに気づかされ悔やんで、「父のもとに帰ろう」、息子と呼ばれる資格はないと自らの過ちを告白し、雇い人の一人に願い出ることを決断するのです。 父親にとっても、父の元を離れることなく忠実に仕えていた「孝行息子」である兄息子にとっても自分勝手な「放蕩息子」であったのです。 恥ずかしながら父の家に戻って行った「放蕩息子」を、「まだ遠く離れていたのに、家に向かって帰ってきている放蕩息子を見つけて、憐れに思い父親自ら走り寄って行った。 何も言わないうちに、首を抱き接吻した。」と言います。 息子の弱々しい懺悔の言葉を父親は遮るかのように、誰が見ても父親の息子であると分かるように、息子としての資格を示す「一番良い服、手にはめる指輪、履物」を用意させたのです。 父親は一日たりとも放蕩息子を忘れることはなかった、家を飛び出した過ちを問題とはしなかった、過去にとらわれず無条件に抱きしめ受け入れた、そればかりではなく父親の家で祝宴を開こうとしたのです。 その時の父親の言葉が、「この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。」とこのたとえを締めくくるのです。 この「たとえ」の主人公は「放蕩息子」でも、「孝行息子」でもなく、「父親」です。 語る中心の内容は、「放蕩息子の悔い改め」ではなく「父親の喜び」です。 自分が似せて創造した人間が自分のもとを離れてしまっても、自らの過ちに気づくことを忍耐強く待ち続ける天地創造の神の姿に映らないでしょうか。 恥ずかしげもなく我に返って戻ってきた人間を無条件に再び受け止め、抱きしめる天地創造の神の姿に映らないでしょうか。 父親は、「放蕩息子」も「孝行息子」も決して比較などしていないのです。 どちらにも、謝罪を求めることさえも求めていないのです。 父の家の者には、「死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。」 「孝行息子」には、「お前の弟は死んでいたのに生き返った。 いなくなっていたのに見つかったのだ。 祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。」と「父親としての喜び」を語るのです。 父親の悲しみも喜びも共にしていない「放蕩息子」にも、「孝行息子」にも、自分のような父親になるようにと願っているのではないでしょうか。 イエスは、「父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛してきた。 わたしの愛に留まりなさい。」と言われているのです。